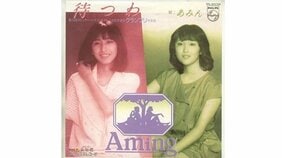中国経済が直面する「失われた20年ないし30年」
不動産バブルの崩壊以降、一部の研究者の間で中国経済の日本化が議論されている。現象面では似ているところがあるかもしれないが、本質的には異なる問題だ。
米国スタンフォード大学客員研究員の許成鋼(専門は理論経済学)は、目下の中国経済は構造的に、政府による経済統制という点で1970年代のソ連経済とよく似ていると指摘している。
30年前の日本のバブル崩壊は、基本的に市場の失敗だった。後処理の段階で政府が失敗を犯し、立ち直るのに時間がかかり、失われた30年を喫した。
それに対して、中国の不動産バブルとバブル崩壊は、政府の失敗が引き起こしたものだ。
中国政府は不動産開発を経済成長の牽引役として位置づけた。土地の公有制を堅持し、不動産課税、すなわち、固定資産税は導入してこなかった。
そのため個人にとっての不動産投資は、低コストでよりたくさんの不動産を所有する一攫千金のゲームとなった。不動産投資ブームについて習政権執行部も危機感を抱き、習主席自身は「家は住むためのものであり、投機の対象ではない」と発言したが、投資の禁止を呼びかけるだけでは意味はなかった。
過度な不動産保有を制限したいのならば、不動産関連の課税を導入する必要があったのだ。
不動産投資は個人の自由として法的に認められている。不動産投資が過熱したのは、地方政府やデベロッパーの不正行為に加え、個人にとって機会コストが安いからである。
過熱し過ぎた不動産投資を冷やすためには制度を改革する必要があるが、政府共産党は政策を立てるよりも先に市場に直接介入しがちである。
政府共産党の市場介入は即効性がある半面、経済のハードランディングをもたらすリスクも高い。習主席の呼びかけは市場を直接統制するものであり、往々にして逆効果となる。