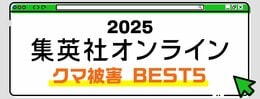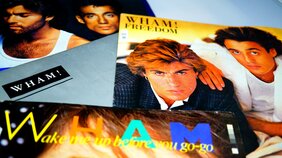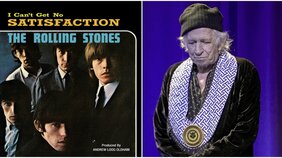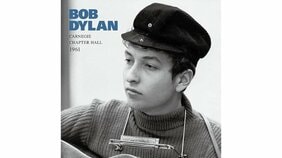介護ビジネスは“オイシイ”商売か
「老人は歩くダイヤモンド」
2022年の夏、ある広告会社の社長が私に、そう話したことがある。東北地方で介護施設を手掛けている知人が、老人相手のビジネスは儲かると語り、老人をダイヤモンドと表現していたそうだ。
この介護事業者の本業は不動産業で、多角化経営の一環として小規模のデイサービスを数店舗経営しているという。今後も事業を拡大していく予定だと嬉しそうに語っていたというのだ。
「介護ビジネスは、入金元が自治体や都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)だから、民間対民間で行う商取引に比べて、確実に収入を得ることができる〝オイシイ商売〟。
しかも他の介護関連業者と組んで、住居から食事、それに医療まで、高齢者の生活を丸ごと囲い込める。小さな石ころが大きな価値を生むから、まさにダイヤモンドみたいだというわけ」(広告会社社長)
まるで高齢者を食い物にするような例えだが、介護業界には、こうした経営者が一定数いるのも事実だ。
介護保険の給付費は年々増加傾向にある。厚労省の「介護保険事業状況報告」などをみても、2020年度の給付費は10兆円を超えており、前年度と比較し2.7%増えた。
そして介護業界は主に、営利企業や医療法人、社福(社会福祉法人)によって支えられている。
厚労省がまとめた「開設(経営)主体別事業所数の構成割合(詳細票)」(平成29年10月1日現在)によれば、訪問介護事業者の約66%は、営利企業が運営している。
福祉用具の貸与や販売の事業に関わる者の90%以上が営利企業だ。特養と呼ばれる介護老人福祉施設は、約95%が社福の経営。公益性の高さから、社会福祉法において、原則的に国と地方公共団体又は社福が経営すると決められているからだ。
老健(介護老人保健施設)は、医学的管理の下における介護やリハビリを行うという性質から、75%が「医療法人」の経営である。
また、介護の問題に直面したとき、最初に相談する地域の包括は全国に5351か所(令和3年4月末現在)あるが、このうち市町村が運営しているのは20.5%に過ぎない。それ以外は「委託」という形で民間事業者などに運営を委ねているのだ。