亡くなってから見つけた母の雑記帳。毎日続けられるものが欲しかったんじゃないか。
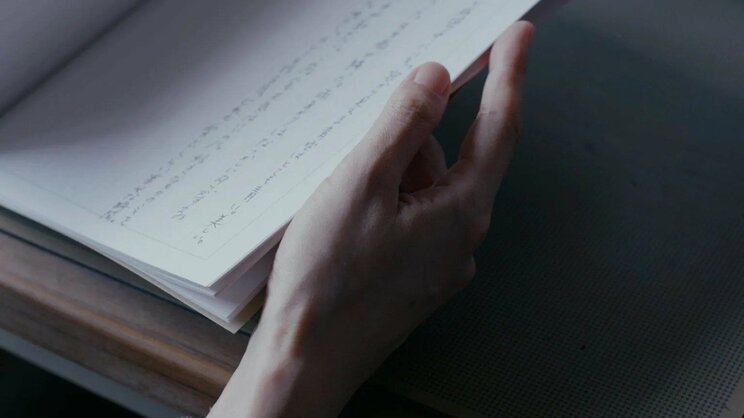
──『はだかのゆめ』は映画にも出てくる甫木元監督の90代のおじい様と、おかあさまが生前書いていたノートの言葉をもとに始まったと聞いています。この作品を見て触発されて、私の書き残している日記など、息子は読みたいだろうかと思って電話で聞いてみたら、「俺は読まないからどこかのタイミングで目につかない場所に移動させるか捨てて」と言われて、そうかと受け取ったのですが。
「僕も亡くなってから見つけたんです。でも、読んで欲しくて残されたっていうものではなく、僕が読むことまでは考えていなかったと思います。本当に一日、一言だけの日記というか、雑記帳ですね。今日、ツバメが飛んできたとか、そういうもの。あれが、誰か、人に読んでもらおうと思っていたら、また違う内容だったんじゃないかと思います。病気になってから、調子がいい日と悪い日の差が激しくて、あまり何もできなくなっていって、それでも毎日続けられるものが欲しかったんじゃないかな。生きている時は聞けなかったですけど、なんとなく、今はそう思います。
一行だけの文章でも、家族だから、なんとなく、この文章にある感情の伝わり方ってあるじゃないですか。土地の見方とも一緒だなとも思ったんですけど、その関係性だから読み取れることもあって。中には、母が人に見られたくないことも書いてある。それをそのままセリフにするのではなく、母が残したものを記録するっていうか、母と実際に生活していた家で、母親と行った時間を映像にすることで、母と歩いた道や風景も含めて、母の気配を記録する感じになったらいいなと」
四万十川には、川に沈んでしまうことを前提とした橋がかかる。90歳のじいちゃんのいう、ま、なるようにしかならんの言葉。

──そのお母様の記憶を投影した母親を唯野未歩子さんが演じているのですが、彼女は漆黒の闇の中、四万十の川に行き、定期的に懐中電灯であたりを照らす。甫木元監督が活動されているバンド、Bialystocksに『灯台』という曲がありますが、これまでの長い月日の中、四万十の川の猛威に吞み込まれていった人たちの魂を誘導する光に見えますね。
「最初から、四万十川の持つ穏やかでない面を映画で描こうという意識はありました。映画にも出てきますが、沈下橋という、増水時に川に沈んでしまうことを前提とした欄干のない橋が四万十川のあちこちにあるんですけど、そういう自然に抗うことをはなからやめて、そのままを受け入れるという高知の精神性がすごくおもしろくて。
あと、埼玉から行って驚いたのは、みんなすっごくお酒を飲むんですけど(笑)、流れに身を任せるというか、人柄的なことも含めて、高知の自然とすごく結びついている。よく、みんな、土佐弁の『なんちゃない』って言葉を使うんですけど、『なんてことない』『どうってことない』という意味で、うちのじいちゃんは90歳になったからこそ、そう言うのかもしれないけど、『ま、なるようにしかならん』と。水難というのは、この映画の一つ、キーワードではあるかと思いますが、それをキャストには事前に伝えていません」
──おじいちゃんはすごい存在感ですよね、オイル缶に藁を敷き詰め、串刺しにしたカツオの塊を豪快に燃え盛る中、炙る場面が出てきましたが、まさに「ザ・高知の男」。いつもああやって、カツオのたたきを作っているんですか?
「そうです、そうです(笑)。じいちゃんは畑でいろいろ野菜を作っていて、高知は魚もおいしいし、埼玉から移住して一番、驚いたところです。ちっちゃい頃から夏休みや冬休みはじいちゃんのいる四万十が帰る場所で、その距離感も近すぎず、遠すぎず、全ていろんなことが鮮やかに感じられる距離。祖父がここに90年、ずっと住んでいるというのが一番でかいですけど、移住した直後から、夕飯のとき、母と祖父が話す土地の昔話や家族の歴史をまず、書き取るということから、この作品は始まっています」
唯野さんにはただならぬ危うさを、青木君にはいった場所に反応する要素を感じた。

──母親役に唯野未歩子さん、主人公のノロ役に青木柚さんをキャスティングした理由は?
「唯野さんは黒沢清監督の『大いなる幻影』(1999)での、どっちに転ぶかはわからないただならぬ危うさを見て、青木柚君との二人の組み合わせはいいんじゃないかと思いました。二人のお子さんを持つお母さんであることは後から知りました。
青木君はプロデューサーから提案してもらったんですけど、『はだかのゆめ』では登場人物の佇まいでどうにかなる話だと思っていて、柚君って動きが面白いなと思って。単純に歩くとか、座るとか、1つ1つの動きに自然と目がいっちゃう不思議な人だなと。ただ、それだけではなく、どこの場所に行っても同じ演技ができてしまう人じゃなくて、行った場所に反応しちゃう人がいいなと考えていて、そこの要素も柚君ならと思いました」
死が迫ってくるといっても、母は慌てる感じもなく、日々できることをやっていた。

──自分としては、独特の死生観を培ったバックグラウンドはどのようなものだと感じていますか?
「祖父にも通じますが、父親と母親の人柄じゃないですけど、『ま、人は死ぬんだ』っていうのは、結構ちっちゃい頃から現実的な話として聞かされていて、夢物語ではなく、身近にある感覚として自分の中にはあるのかもしれない。あと、単純に父と母、2人とも看取れたので、死ぬ直前を目撃したことが1番でかいかもしれないです。二人ともガンだったんですけど、傍から見ると意外に病であることがわからないというか。母親はあまり自分から人には言わないようにして、誰にも病気のことは連絡していなかったから、亡くなってから、みんなが驚くという感じだったんですけど、死が迫ってくるといっても、なにかやり残したことをやるでもなく、慌てる感じもなく、日々できることをとにかくやる。そういう毎日を過ごしていました。
母はピアノの先生で、演劇の戯曲での演奏もしていたんですけど、そちらの顔を作品にするっていう感じじゃないんだと思って。そちらよりも、ガンになったからこそ、日々、淡々とやれることをこなす姿が印象に残っている。父も母も二人とも、花の写真を撮ったり、家に花を飾るようになったり、自分の身の周りを少しずつ、ちょっとだけ変えていく作業の方に意識がいっている感じがすごくあった。死と生活が地続きな感じで、考えてもしょうがないじゃん、ということを本当に感じたんです。亡くなってから、意外と夢にそんなに出てこないんだなと感じたりもします」



──亡くなった方のお話ばかり伺って申し訳ないのですが、大学の恩師である青山真治監督も2022年に亡くなられました。『はるねこ』『はだかのゆめ』とプロデューサーを務めた仙頭武則さんが追悼文に書かれていましたが、青山さんは甫木元監督のことを心配して、病気の進行を亡くなる直前まで言わないでくれと頼まれていたそうですね。
「青山さんらしいな、と思いました。母親が亡くなって僕が最初に電話をかけたのが青山さんだったんですが、その経緯も知っていらしたので、自分がガンだって言いたくなかったんだろうなと。でも、一緒にいて体調が悪いのはわかるし、しんどうそうだし、母親を見ていたのでガンなんだろうなというのは感じていましたが。2019年に、青山さんが高知のじいちゃんの家に来てくれて、何日間か一緒に生活したことも、映画の中に大きく反映されているかと思います。前野健太さんが演じるおんちゃんの一部にはなっているかなと」






























