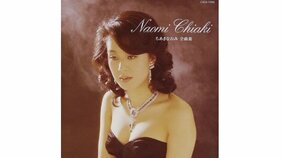原作と読者をリスペクトした、等身大の映像化を

「映像化は小説の世界観を知ってもらうための最大のプロモーション。これに勝るものはないので、できればやってもらいたいと、ほとんどの作家が思っているでしょうね」
作家にとって映像化の意味を問うと、池井戸潤氏はストレートにそう答えた。過去に出版した作品も含めてその多くがドラマ化、映画化されており、出版界だけでなく映像界からももっとも新作を求められている池井戸氏だが、「ただし……」と、言葉を続ける。
「欲を言えば、できるだけいい映像化を目指していただきたいというのが正直なところです。僕の思ういい映像作品とは、原作やそれを読んだ読者のことを大事にしていると感じられるもの。僕の作品は銀行や会社など仕事の現場を舞台にしたものが多く、読者の多くも現役で仕事をしていたりビジネス経験があったりする。だから、そうした場面のディテールが甘く矛盾が生じていたり、こんなことはあり得ないというご都合主義の作りになっていたりすると、がっかりされてしまうんです。逆に、リアリティを大切にした質の高い映像になっていれば、納得度は高いと思います」
その点からも、まもなく公開される映画『アキラとあきら』(8月26日公開)は、原作者も頷ける出来だったようだ。小さな町工場を営む地方の家に生まれ、幼い頃に倒産を経験した山崎瑛(やまざきあきら・竹内)と、伝統ある海運会社の創業家の長男として期待を一身に背負って育った階堂彬(かいどうあきら・横浜)。同じ名を持つ2人の青年が、それぞれの理由から銀行員という職業を選び、切磋琢磨する青春の日々を描いた同作は、ほぼ全編、彼らの職場を舞台に物語が展開する。生きたビジネス用語が飛び交う中で自然な所作を求められる、ハードルの高い撮影への挑戦が、見事に結実していたという。

©2022「アキラとあきら」製作委員
「まず、シナリオがとてもよく練られていましたね。長い原作をうまく構成していて無駄な台詞がひとつもなく、さらにそれらが有機的に結びつき、高い次元で融合していた。とくに心配していたのが、主人公2人が最初に火花を散らす新入行員研修でのプレゼンテーションの場面。銀行業務にまつわる監修がきっちりなされていて、竹内さん、横浜さんをはじめとした俳優陣も、難しい台詞ややりとりをスムーズにこなしていました。
そして、ビジネスシーンを描いた作品としての完成度の高さに加えて、小説を書くときに大切にしている、人間を誇張なく誠実に描く姿勢がごく自然に実践されていたこと。結果、実にヒューマンな青春物語に仕上がっていたことがうれしかったです。青春ものや恋愛映画を得意とされる三木孝浩監督のお仕事は、今回はじめて拝見しましたが、台詞や心情を大切にした映像は、まさにあるべき姿だと。起用を提案したプロデューサーが話していた、“恋愛を撮れる人は人間を撮れる”という言葉に嘘はなかったと、あらためて感じ入りました」