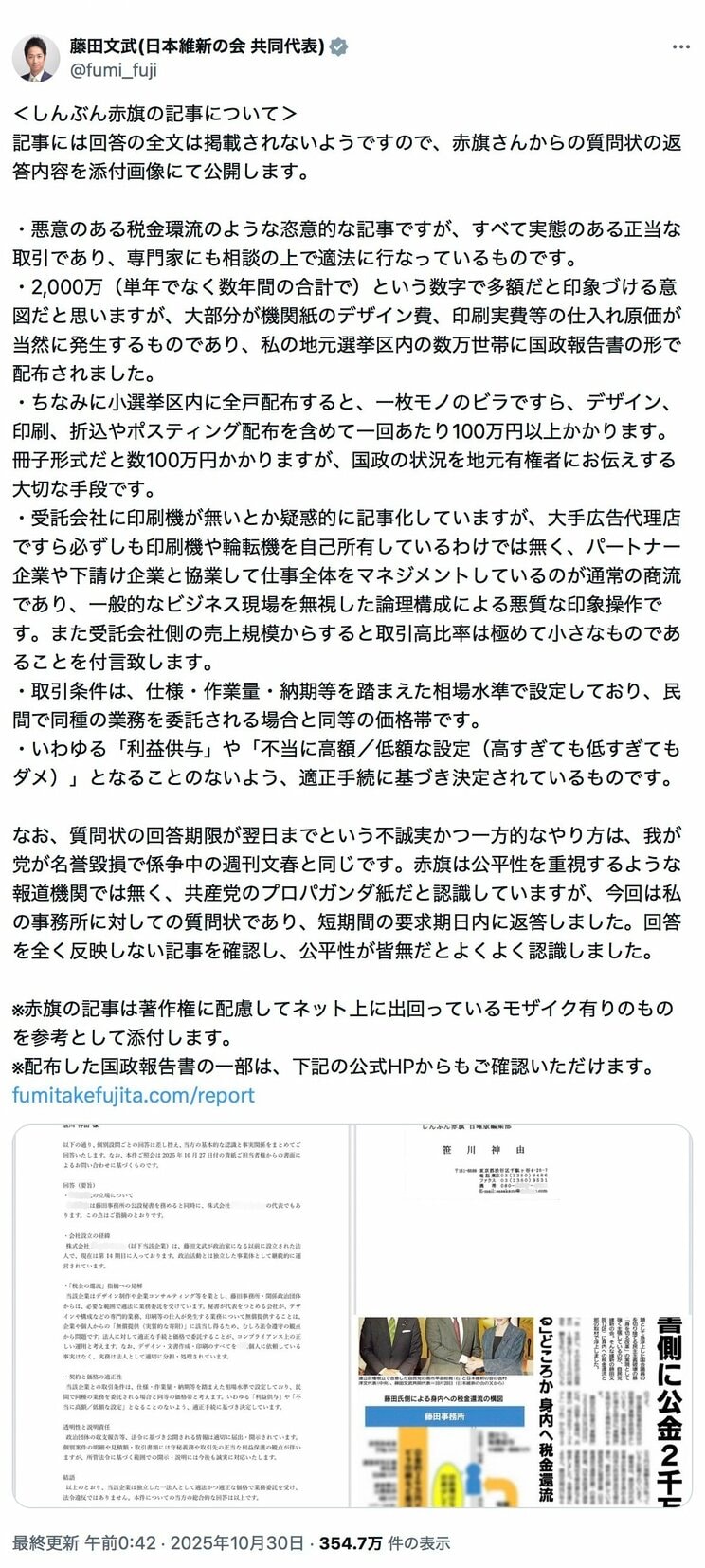自身や身内に対してはその基準を緩めていないか
例えば、学校の先生がテストを採点する際を想像してみよう。先生は自分の子どもにだけ100点をつけた。ルール上、先生は自分の子どもの答案も採点してよいことになっている。
しかし、他の生徒や保護者はどう思うだろうか。「ズルい」「不公平だ」という声が上がるのは当然である。この場合、たとえ先生が本当に公平に採点したとしても、「見た目」が公平ではないため、先生への信頼は失われる。
「外形的公正性」とは、まさにこの「見た目でズルいと思われるなら、公正ではない」という感覚に基づいている。これは、政治家が国民の信頼を失わないために、法的な正しさのさらに手前で、疑念の芽を摘むための「予防的な正義」として機能するとされる。政治の信頼を守るための、いわば「疑わしきは避ける」という行動規範である。
しかし、この概念が、その提唱者自身によって恣意的に運用される時、それは公正とは真逆の、不公正を生むこととなる。
橋下徹氏が藤田文武氏を断罪した「外形的公正性」という物差しは、彼自身の過去の言動にこそ、鋭く向けられるべきである。彼の発言の一貫性を検証すれば、その公正性が、時としてダブルスタンダードにまみれているかが、わかるだろう。
橋下氏は、吉村洋文氏(大阪府知事、維新代表)に対しては、常に擁護的な姿勢を取り続けている。例えば、かつては「飲み食い政治」そのものを「永田町の古い慣習」「領収書抜きの飲み食い政治の撲滅!」と強く批判していた。
しかし、吉村氏が維新の代表に就任した2022年以降、橋下氏の批判は「<ルールなき>飲み食い政治」へと矮小化された。つまり、「ルールさえあれば飲み食いは容認される」という、批判の基準を一歩後退させているのである。
一方、藤田氏に対しては、法的な問題がないにもかかわらず、「外形的公正性がない」と即座に断罪した。これは、橋下氏が批判の対象を「外見の印象」で選んでいるとしか言いようがない。
橋下氏が主張する「見た目の公正性」は、他者に対しては厳格に適用されるが、自身や身内に対しては、いとも簡単にその基準が緩められているのではないか。