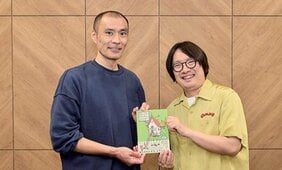「大島史観」で書いた、少女漫画誌の歴史
── 少女漫画誌について書こうと思われたのは、いつ頃でしょう。
最初に編集者に「書く」と伝えたのは十年以上前……(マーガレット五十周年を記念した)「わたしのマーガレット展」があった頃です。ただ書きたい気持ちは強くても、どう書けばいいのかはさっぱりわからず、そのままになっていたんです。でも二〇一九年に『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で直木賞をとった翌年、お祝いしてくださった古い知り合いが過去に少女漫画の編集者だったことがわかって。当時の話を聞いているうちに、「あれを書く時がやってきた!」と。どこに焦点を当てればいいのかが見えました。
── 「編集部」を書くという発想もそこからですか。
それはもとからですね。小学生の頃から「これを作った人は誰なのか」が気になるタイプでした。「マーガレット」編集部のことも、あそこには一体何があるのかとずっと気になっていて。あの時代の少年漫画の編集部の話はたくさん読めますが、少女漫画の編集部の小説は読みたいと思ってもほぼなかったんです。それなら私が書くしかないや! と。
── 当時を知る方にたくさん取材をされたそうですね。
編集者はもちろん、漫画家さんとそのご家族、製版所の方、カメラマン……いろんな方に取材しました。もうね、お話が面白くて面白くて。子どもの時に聞きたかったことをいっぱい聞きました。たくさんの方々が協力してくださったので、それを残さなくては、という気持ちも強かったです。「こんなに長い小説になっちゃったけど、大失敗になる可能性もあるな……」と思ったりもしたんですが、つまらないものになったとしても、この時代の少女漫画編集部のことをちゃんと取材して書いたという意義はあるはずだから、許してもらえるかな? と。「大島史観」で書いた、少女漫画誌の歴史ですね。私にとっての真実を書きました。
── 実在する作品名や漫画家の名前は出てきませんが、想像がつくものはありますね。それを考えながら読むのも楽しいのですが、そこに重点を置いた小説ではないと感じました。
そうなんです。『うまれたての星』というタイトルにしたのは、当時の編集部まるごと、その宇宙を書きたかったからです。編集者には最初「こういうものが書きたい」と、ジグザグした星の形を描いて見せたんですよ。誰か一人が主人公ではなくて、いろんな人が持っているものが組み合わさって、きれいな球体ではない星ができるんです、と。それをまるごと描きたいと伝えました。
── 取材を始めてからはすぐに物語は固まったのでしょうか。
ずっとグラグラしていました。本当に少しずつ、イメージを膨らませていきましたね。取材したものを、一回全部自分の中に入れるんですよ。入れて、ろ過する。そうすると文字になる。連載を始めてからも取材を続けていたので、なかなか方向は定まりませんでした。
── 一つの大きな筋が通っていると感じて読んでいたので、意外です。
大きい筋は何もわからないんですよ。小説が連れて行ってくれるので。私がちゃんと小説の下僕になれるかどうか、なんです。
── 自分で「こうしよう」と思って書くわけではない、と。
そうですね。「これは小説が求めている一行かどうか」の検証に時間がかかります。自分で「こうしよう」と思った一行を入れると、その行が後々まで話をおかしくして、失敗する。取材した漫画家さんも同じことをおっしゃっていたんですが、漫画家さんの場合はネームを編集者に見せますよね。この小説の「小柳編集長」のモデルになった編集者にネームを見せると、どこでおかしくなったかを指摘されるんですって。
── なんと……! 鋭い編集者にはわかってしまうのですね。
ゾクゾクッとする話でしょう。教えてくれる人がいるっていいなと思いましたね。小説にはネームがないので。
少女漫画から受け取った良きものは、「熱」だった
── 少女漫画が生み出される場所の持つわくわく感だけでなく、泥臭さや狂気のようなものも強く伝わってきます。特に後半、『ベルサイユのばら』と思われる作品が登場し、編集者も読者もみな常軌を逸していく── というくだりは圧巻でした。
取材を忠実に反映しただけなんですけどね。読者コーナーには実際「『ベルばら』は私を狂わせる」という投稿が載っていたんです。書くにあたって、三回くらい『ベルばら』を読み直したんですが、これは女の子たちへのエールの物語だなとつくづく感じました。だから女の子たちがあんなにも強く反応したのだと思います。
── フィクションの持つ力、凄みが、伝わってきました。
フィクションは、人の心をそそのかすものだと思うんです。私もそそのかされて、こんなわけのわからない人生を歩んでしまいました(笑)。そそのかす、はちょっと嫌な言い方ですけど、フィクションは豊かさを教えてくれるものですよね。「今あるものでOK」で終わらせるのではなくて、豊かなものはまだ「こっち」にいっぱいあるよ! ということを見せることができる。今の時代、「こっち」が痩せつつある気がしているので、私も小説でそれを見せたいというか、思い出そうよ! と言いたい気持ちがあります。
── その豊かさに小学生で触れることになった千秋という「週デ」の熱心な読者が登場します。
小学生だった私が、実際に体験していたことをのせて書ける人物ですね。当時、漫画を買いたいがために、親に頼んでお小遣い制に変えてもらったんですよ。それでも足りなくて、「読ませてあげるから」と妹にも半分お金を出させて買うような小学生でした(笑)。
── その小学生が、その時感じていたことをこうして小説にしたのですね。
感無量です。ちょうど還暦を迎える頃に書いていたんですよ。人生のいい一巡りだな、と思いました。すごく良きものを、私は少女漫画から受け取ったとずっと思っていて。それが何かを知りたかったんですが、書きながらそれは「熱」だとわかった。編集部と私は、ダイレクトに熱をやり取りしていたんです。熱って、伝わるんですよ。子どもにも伝わる。小説の最後に出てくる「デイジーから受け取ったきらきら光る欠片」を、私はずっと持っていたんだなとあらためて感じました。