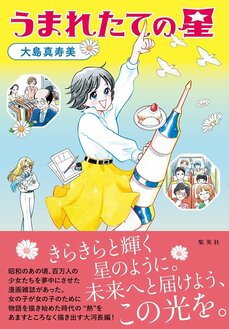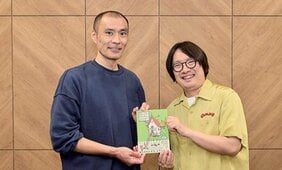ちっちゃな目覚めや決意の積み重ねが、世界を変える
── 読んでいて強く思ったのが、昔の話ではまったくない、終わっていない話だ、ということでした。
懐かしい昭和の話、ノスタルジーの物語にはしたくありませんでした。だって今、私が書くものだから。読み終わった後に、「ここに立っている私」に戻ってきてほしかったんですよ。読んでいる人は、最初はジグザグの星を見ているわけですが、そのうち「あ、私もそこに立っていたんだ」と気づくというか……。
── 「別デ」に掲載されたある漫画の最終回を読み終えた牧子が、「私も生きてるんだ」と思うくだりで、読者はそれに気づくと思います。それと読後は登場人物たち……特に女性たちみんなと、手をつないでいる気持ちにもなりました。
今回は、そういったフェミニズム的な要素が強くなったんですよ。書き始める前には、まったく思っていないことでした。取材中に「当時、女性編集者は誰も漫画家の担当をできなかった」と聞いて。女の子が女の子のために漫画を描いているのに、女性の編集者はそこから抜けていた。驚きました。
── 女性たちは、取材記事や懸賞ページを作ったり、漫画家の身の回りのことを引き受けたりする様が描かれています。
当時の彼女たちの悔しい気持ちを受け取ったのだから、これはもう書かねばならんぞ! と思いましたし、書いていくうちに、そのことが大きくなっていきました。
── 女性たちの意識が、世代の違いによって少しずつ異なるのもリアルですね。
そのレイヤーはすごく大事だと思うんです。そこを繊細に書き分けないと、ジグザグの宇宙ができないと思いました。
── 戦前生まれのベテラン記者の修子や契約社員として編集部を支えてきた育江ら先輩たちが、自分の状況は半分受け入れつつ、新しい考えを持つ後輩女性や若い漫画家を応援しているのも素敵です。二十代の編集者・克子と美紀が、離れていても互いを励みに思う関係性にもぐっときました。
修子さんとして書かせていただいた方に取材した時に、「私は女の人の味方だったのよ」っておっしゃったんですよ。「どうして私が女の人の足を引っ張らなくちゃいけないの」と。世界って、一気には変わらないじゃないですか。本当にちっちゃな目覚めとか、ちっちゃな決意が、ミルフィーユの層のように薄く薄く積み重なることでしか、変化しないんじゃないかと思っていて。彼女たちが、葛藤がありながらもちょっとずつやり続けてきたから、今がある。取材に同行した女性編集者も「今の自分がいるのは先輩たちのおかげなんですよね」と、毎回感動していました。
── 「シスターフッド」という言葉が何度も浮かびましたが……やはり意識していたわけではないのですよね。
まったく(笑)。でも、今だからこう書いたのかもしれない、とは思います。十年前に書こうと思った時は「#MeToo運動」もまだなかったですしね。小説って「今必要だ」という時に世に出てくるんですよ。私はそれに沿って書いているだけだと思います。
── 先ほども「小説が連れて行ってくれる」とおっしゃいましたね。
「こういう形で私は本になりたい」と、小説が決める。だから今、フェミニズム的なものとして、この小説がここに書かれたのだと思います。今、弱いものに対する目線の向け方が変わってきているというか、世の中がまたマッチョな方向に動いているでしょう。反動が起きている気がしますよね。だから今、この小説を読んでほしい、という気持ちもあります。
── 作中の男性の編集者にも、世代や考え方の違いがありますね。先ほどの小柳編集長以外だと、保守的な女性観の編集者が何かに気づいたり、漫画に疎かった若手編集者が女性漫画家に対して「鵺か」と畏怖のような感情を抱くようになったりもします。
ここに出てくる男性たちも、女性に意地悪をしているわけではないんですよね。女の人が同じ編集部にいても見えていないだけ。女性にやれるわけがない、というのが通常運転の社会だった。取材させてもらった男性は、みなさんすごくいい方で。この小説で女性たちの状況を読んだら「そうだったの!?」と驚くかもしれないですね。
── 書き終えてしばらく経ち、どんなことを感じますか。
最後が読めてよかったな、と。今回は長い話だったので、ここまで書いて最後の一行を知らずに死ぬなんてあんまりじゃない? と思っていたので(笑)。書くのが本当に楽しかったです。自分で書いて自分で読んで、自給自足です。
── 書いたものを「読める」ことも楽しいのですね。
私の中では、書くことと読むことにあまり差がないんです。自分が知りたいと思うことを、別の人が書いてくれたら、それを読むのでも全然構わないんですよね。
── 『あなたの本当の人生は』で小説、『渦』で人形浄瑠璃など、大島さんが書いてこられた創作にまつわる物語にも、まさに今おっしゃったことが反映されていますね。作り手と受け取り手の間にも、一人の作り手とほかの作り手の間にも境がないというか。今回も「あなたがいるもの。私じゃなくたっていい」や「おっきな生き物なんですよ。私たちはきっと」というセリフがあり、みんなで何かを作っている、担っているイメージが浮かびます。
本当にそう思っているんですよ。「どこかに接続している」感じかなあ。先ほどからお話ししているように、本当に自分が思ってもいない一行を書くことがあるんですよね。それがすごく面白い。この小説の最終回のあたりは特に、自動筆記みたいに書きました。『渦』の時も至福だと思って書いていたんですが、また別の楽しさでした。集中する時、今まではキューッと細い「線」の中に入っていく感じだったんですが、今回は「丸」だったんですよ。丸い何かにスポーンと入っていく感じがしました。……何を言っているんだ? という感じですよね(笑)。
── いえいえ、人によって感じ方は違うとは思いますが、読み終えた人にはピンとくると思います。先ほどおっしゃった「ここに立っている」感覚、読後に登場人物たちと手をつないでいるイメージなどが、「丸」という言葉に集約されていると感じます。
わあ! 丸い感じ、伝わるんですね。嬉しいです。
── 大島さんが受け取った「きらきら光る欠片」は、今どうなっていますか。
あるんじゃないかな、ここに。まだまだいろんなことをやりたいっていう気にさせてくれると思います。これを読んだ人にも、そういう気持ちになってもらえたらと思っているんです。当時の「週マ」や「別マ」の中心読者は私より少し上の、六十代から七十代くらいだと思うんですが、だんだん体力も落ちて元気がなくなってくる頃かもしれなくて。そういう方がこの小説で、十代の自分が少女漫画から受け取っていたものが言語化されているのを読んだら、自分の気持ちをもう一度違う目で見られるかもしれない。それは、これから生きていくにあたって良きものになるんじゃないかな、と思うんです。
── 胸にしまっていた欠片を、取り出してもらいたいです。
そうですよね。まずはその年代の方たちが読んで、次にその人の娘さん、さらに若い人たち……と読んでもらえたら嬉しいです。