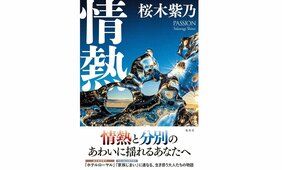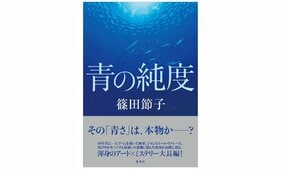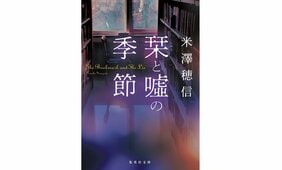「私はあなたを見ている」、その視線を感じるだけで救われる人がいる
── 今回の物語の舞台は、どのような経緯で選ばれたのでしょうか。
この作品は、舞台を決めることから始まったんです。最初のきっかけは、集英社の編集部員の方から、日本の東海地方のとある団地を舞台に小説を書きませんかというお話をいただいたことでした。そこは、ブラジルの方が多い団地だったんですね。私はこれまで何度か団地を舞台にした小説を書いてきましたが、日本人だけが登場するのは不自然ではないかなと思っていました。今の団地には、外国からやってきて日本に帰化した方もいれば外国籍の方もいる。いろいろな国の人たちが交じって暮らしている今の団地のことを、ぜひ書いてみたいと思ったんです。ただ、ある理由で取材が難しくなってしまい、東海地方の団地の話は、なしになってしまって。でも、やっぱり団地の話を書きたいという思いが募って、東京近郊で取材ができる所はどこだろうと探した結果、神奈川県のとある団地をモデルに書いてみることにしたんです。
── 小説では「紅葉団地」という名称で登場しています。
モデルになった団地は、ベトナムの方がたくさんいらっしゃるんです。神奈川にはインドシナ難民(※一九七〇年代にベトナム、カンボジア、ラオスの社会主義体制への移行に伴い、迫害を恐れて国外に脱出した人々)をサポートする「定住促進センター」があり、そこで紹介を受けた方たちがこの団地に住むようになったんですね。その後、子どもやお孫さんも生まれ、数世代にわたって団地で暮らしている。その現実を知った時に、子どもたちの話が書きたいなと思いました。そこから、難民三世のヒュウというベトナム人の男の子と、桐乃という同い年の日本人の女の子が生まれました。
── 団地、お好きなんですね。
好きですね。今も残っている団地って六十代、私と同い年ぐらいの建物が多いと思うんです。私は東京の稲城というところで生まれ育ったので、子どもの頃、多摩ニュータウンができるのを間近で見ていました。自分の家は、商売をしている古い家だったんですが、団地に住んでいる友達の家に行くと、ものすごい近代的というかピカピカのおうちで、うちにはない文化がそこにあって。子どもの頃は団地って、憧れの場所でした。給水塔も大好きなんですよ、あのフォルムが(笑)。今は多摩のほうに住んでいるんですが、電車に乗っているといつも、多摩ニュータウンの団地の給水塔が見えるんです。もしかしてあの給水塔ってほぼほぼ私と同じ年ぐらいかなと思うと、歴史を感じるし、「あの給水塔はどんなことを見てきたのかな?」というイメージが湧いてきた。そのイメージもまた、この作品に繫がっていったんです。