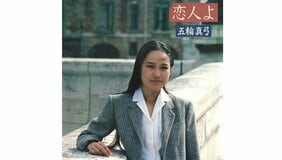デザインは“行動を導く設計”であるべき
––––書籍の中で印象的だった言葉に、「バッテリー家電は不経済」というものがありました。これはどういう意味でしょうか?
一番の理由は、出力が弱いからです。とあるメーカーのコードレス掃除機なんて、出力が足りなくてゴミを全然吸わない(笑)。それに、「家の中で使うのに、なぜわざわざ無線にするの?」と思うんですよ。ルンバのように“動かすことが前提”の機器なら別ですが、固定して使う家電までバッテリー式にするのは合理的じゃないと思います。
有線のほうが安定していて、パワーも強いし、壊れにくい。バッテリー式は、交換のたびにコストも手間もかかります。だから「バッテリーだから便利」という思い込みは一度疑ってみたほうがいいと思いますね。
––––家電の「デザイン」については、どのように考えていますか? 最近は見た目の美しさを重視した“デザイン家電”も人気ですが。
私はデザイン家電が嫌いなわけではありません。ただ、「意匠のための意匠」は嫌いです。意匠デザインと機能デザインがごっちゃになっている製品が多いんですよ。本来、意匠は機能と一体になって初めて意味がある。
デザインは人の行動を導くための設計であるべきで、ここで大事になるのが「アフォーダンス」という考え方です。見ただけで「どう操作すればいいか」が自然に分かる形や配置になっているか。ボタンを減らして見た目を整えても、誤操作が増えたり手順が複雑になったりするなら本末転倒です。
––––ズバリ、日常生活で家電を使いこなすコツは何でしょうか?
「説明書をちゃんと読むこと」です(笑)。多くの人は読まないまま「使いづらい」「壊れた」と言うんですが、メーカーが一番効率的な使い方を丁寧に書いているんですよ。たとえばホットクックの場合、「スパゲッティを茹でるとき、お湯は1000ccだけ」と説明書に明記されているのに、なみなみ水を入れて壊してしまう人が本当に多い。
私は買う前に説明書を読むこともあります。特に「お手入れが面倒かどうか」は必ず確認します。そこを読むと、製品が自分の生活サイクルに合うかどうかが見えてくるんです。
それと、導入したあとは、“使わなくなる理由”を徹底的に潰していきます。充電が面倒ならスタンドを買う、取り出しづらいなら場所を変える。そうやって使うハードルを下げて、自分の生活動線に組み込んでいく。これが、家電やテクノロジーを使いこなす確実な方法だと思います。