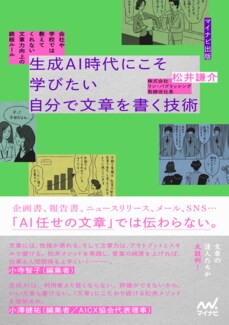0か1かではなく、適切な分量で
いわゆる文章術の解説書などを見ると「わけのわからないカタカナ語は理解を妨げるだけ! かっこつけずに日本語で表現しましょう。俺たちは日本人だ! ビバ大和魂!! 一富士二鷹三茄子―!!!」という説明がよくあります。
しかし、世の中には「日本語にすることで、どうしても理解が遅くなる」ワードというものもあるのです。
先に触れた「リテラシー」はどうでしょうか。これ、書籍によっては「『知識・教養』と言い換えよ」と説明しているものもありますが、先ほどの文章で「知識」と変換したら、どうにも物足りません。
「必ずしも同じ知識を有しているとは限らないから」……いかがでしょう。この日本語変換で、言いたいことはしっかり表現できていますでしょうか。私はそうは思いません。
そう、「リテラシー」とは、「ある分野に関する知識や、活用する能力」くらいの幅を持つ意味なのです。すなわちこのケースではカタカナ語のままでいくか、表現をさらに丁寧にし、「読者の皆さんは、必ずしも同じレベルでの知識やスキルを有しているとは限らないから」とするのがよいのです。
どちらがより適切なのかは、読み手の特徴やスキルなどを勘案し、書き分けると親切でしょう。
日本語文章は「ある程度カタカナ語があるほうが読みやすい」
また、現代の日本人はカタカナ語にある程度慣れており、「一定量カタカナ語があるほうが読みやすい」という状況にあります(もちろん年代などによる差異はあります)。前述のCSRに関わるカタカナ語表現を、日本語だけにしてみました。
当社における企業の社会的責任とは、企業運営上の利害関係者に対し、厳密な法令順守と企業統治の徹底を行うことが下地にあると考えます。そのためにまずは、製品の原材料・部品の調達から販売に至るまでの一連の流れを透明にする必要があり、同時に各工場と緊密な協力・互助関係を築いてまいります。
古語か。というくらい堅いです。バランスを調整してみましょう。
当社のCSRは、各ステークホルダーに対し、厳密な法令順守と企業統治の徹底を行うことがベースにあると考えます。そのためにまずは、サプライチェーン(製品の原材料・部品の調達・販売までの流れ)を透明にする必要があり、同時に各工場と緊密なパートナーシップを築いてまいります。
このくらいが読みやすく、理解しやすいはず。「サプライチェーン」のように、共通認識が高いのか低いのか判断しづらいものは、カッコで補足を入れてあげるとよいでしょう。
え? カッコ? まぁこれは「カッコ」でも「括弧」でも「かっこ」でも、どれでも大丈夫。こちらは統一表記の問題となります。

■まとめ
・「カタカナ語」には単語以上のニュアンスを含んでいるケースも多い。
・「カタカナ語はすべて日本語にすればわかりやすくなる」は間違い。
・大切なのは、書き手と読み手の間にある「共通理解」の幅を把握すること。
文/松井謙介