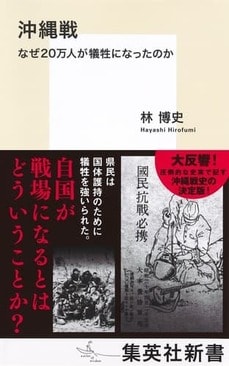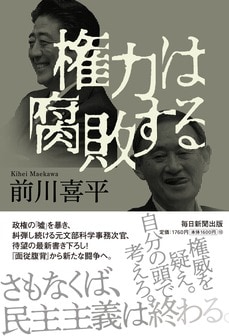1997年に発足した「つくる会」と教科書議員連盟
前川 私も若い頃にイギリスに2年間、留学させてもらいました。1980年代ですから、サッチャー首相が出てきた頃で、サッチャーが出てくるまでのイギリスは低迷していて――サッチャーの政策がよかったかどうかは検証が必要でしょうが――日本では「英国病」という言葉が使われイギリス人をバカにするような議論がずいぶんありました。
「あんなふうになっちゃいけない」と。でも今の日本はまさに「日本病」です。40年前に英国病と言っていたイギリスよりもひどいかもしれない。今、林さんがおっしゃったようにバブル崩壊後の30年というのは、「自信喪失の裏返しの空威張り」みたいなものが出てきたんじゃないかという気がします。ちょうど、歴史教科書に対する政治家の攻撃が始まったのも、その頃です。
直接のきっかけは、いわゆる従軍慰安婦問題でした。1991年に韓国で金学順(キム・ハクスン)さんという女性が本名を名乗って日本政府を訴えたことです。それまで実名を名乗って出てくる人はいなかったんですが。それがきっかけで、いわゆる従軍慰安婦問題は日韓の外交問題になりました。
それに対して当時の自民党は宮澤喜一内閣で、今よりずっとまともというか自民党内でもリベラルな人たちが政権を持っていたので、「日本政府の責任で調査します」と約束して、調査の結果を踏まえて、当時の官房長官の河野洋平さんが93年に河野談話を出しました。どこまで学問的に正しいかということは別の問題としてあるかもしれませんが、「総じて強制性があった」ということを認めた上で、おわびと反省の言葉を述べて、さらに「歴史研究と歴史教育を通じて次の世代にも伝えていく」と約束しました。
それまでも中学、高校の教科書で従軍慰安婦の問題を扱ったものはあったんですが、河野談話が出たことがきっかけで全ての中高の歴史教科書に従軍慰安婦が載りました。95年度の検定の際には中学の歴史教科書で全ての教科書会社が載せるようになり、その教科書検定の結果がわかったのが96年3月。97年度から実際にそれが使われ始めました。
そしてこの96年から97年にかけて、慰安婦問題を学校教育で扱うことに対する右派の反発がどーんと出てきた。自民党の中に「教科書議員連盟」(正式名称「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」)が結成されて、初代会長になったのが中川昭一氏、初代事務局長が安倍晋三氏です。中川氏も安倍氏も当時は40代前半で、彼らが「従軍慰安婦のことを教えるな」と言い始めた。
学者の中からも、藤岡信勝氏(*)らが「こんな教科書でいいのか」と言って、「新しい歴史教科書をつくる会」というのができました。この「つくる会」が、「日本国民であることを誇りに思えるような歴史教科書を作るんだ」というようなことを言って、日本の国家、あるいは政府が行った過去の負のでき事、侵略戦争や植民地支配、それに伴う非人道的な行為などを子供たちに教えない、教えないどころか、なかったことにしてしまう。
そういう歴史教育をやろうとした。そんな「つくる会」の歴史教科書と、自民党のタカ派グループの教科書に口を出す人たちとが連動していった。
この人たちは歴史教育だけでなく道徳教育も推進してきた。「戦前の家父長制をもう一度作り直したい」というようなイデオロギーが背景にあると思います。
彼らは歴史教育に関して言えば、南京虐殺を否定する。従軍慰安婦の存在は認めているんだけれども、「自らの意思で、商売のために行った売春婦だった」として、「意に反して仕事をさせられたというのは間違いだ」という言い方をします。
もう1つが沖縄戦の集団自決について。「これは住民の愛国心から行われた自発的な行為であって、軍隊が強制したり命令したりしたことじゃない」と教えさせようとして、特に中学、高校の歴史教科書に口を出すようになりました。
歴史教育は、小学校では6年生、中学校では3年生で主に日本史を教えるわけです。高校では、かつては世界史が必修で、日本史は必修じゃなかったんです。これに対してはむしろ右派、自民党のタカ派の人たちから批判があって、「ちゃんと日本の歴史を教えろ、高校で日本史を必修にしないのはおかしい、日本人なんだから」と。
確かに世界史が必修で日本史が必修でないというのはおかしかったと、私も思います。ただし、自民党タカ派が「日本史を教えろ」と言っているのとは、また違う意味です。彼らが言っていたのは、日本人として誇りを持たせるとか、皇国史観の復活みたいなことですから。
* 藤岡氏は産経新聞『正論』常連執筆者で、教育学者・教育評論家。宗教団体「キリストの幕屋」で講演会を何度も行い、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)系のメディア「世界日報」に寄稿し、幸福実現党の党首と対談するなど、宗教団体や関連団体とも関係が深く、また参政党の学習会でも講師を務めている。
構成/稲垣收