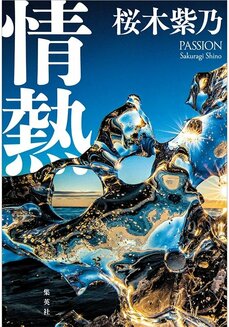男の肩にぴらぴら載ってるプライド
桜木 老人のヒモ、朗人という人物はどうですか。大竹さんから見て。
大竹 ヒモってさ、あんなに優しくないんだよね。
桜木 (笑)。根底から覆さなくても。
大竹 俺の場合はね。俺は威張ってるヒモだったから。ラーメン屋に入る前に、女に「財布」って言って財布預かって、俺がその財布からラーメン代を払って、チップもあげて、店を出てから財布を女に返していたからね。
桜木 職業ですね。ヒモという職業。大竹さんにとって、こうあるべきというヒモ像を演じていたわけでしょう。心がどこにあるかは別に置いておいて、ヒモをまっとうしようとしていた。
大竹 へりくだってたらヒモになれないと俺は思ってるわけよ。俺のヒモ道は。
桜木 ああ、ヒモ道。
大竹 でも、優しいヒモもいるんだろうね。そういえば、俺の知り合いに愚にもつかない駄目なやつだけど、女にモテるやつがいるのよ。それはもう優しさの塊みたいな男なの。顔がいいわけでも何でもないんだよ。でも、モテるんだ。女はそいつから優しくされることで、いままで生きてきて味わったことのない気持ちになっているんじゃない? そういうヒモもいるのかもしれない。
桜木 どこにでもヒモの働き口はあるってことですね。女が多様なので。
大竹 一つ言っておかないと。威張ってはいたけど、俺はやくざのヒモとは違うからね。やくざのヒモは、女を蹴飛ばして殴った後に、赤チン塗ってあげるようなところがあるじゃない。殴っておいて抱き締めるみたいな。
桜木 そうですね。いにしえのやくざ映画を観てると、そんな感じが多いですよね。私はさんざんやくざ映画を観てきたんですけど、なぜ「ひも」でああいう優しい男を書いたのか自分でもよく分からない。大竹さんからヒントを得たせいですかね?
それと、うちはいま私が生計を立てているんです。そのことがちょっと影響しているかもしれない。夫は六十六になったんですけど、最初の何年かは大変だったんです。つまらないことで何度も衝突して。やっぱり男のプライドがあったんだと思います。
大竹 大事だからね、男のプライドは。
桜木 男はプライドで骨格を保っているようなところがありますよね。
大竹 おっしゃるとおり。
桜木 夫がずっと家にいるようになって、最初の頃は「一緒に御飯を食べる時は仕事のことは考えないで」って言われていたんですが、そのうちに私が「そんなことできない!」ってちゃぶ台返ししたんです(笑)。どうやってこの関係の着地点を見つけようかと思っていたら、ある時急に夫が家事をすべてやるようになったんです。
大竹 ほう。
桜木 驚いたのが、彼は洗った洗濯物をちゃんと畳んでタンスにしまうんです。私、あんまりまめなほうじゃないんで、畳むのが面倒くさいって、下着を重ねたままでしまうこともありました。
お風呂に入る時に脱いだものをかごに入れておけば洗濯してくれるし、脱衣所にはきれいに畳まれた洗顔用のタオルやバスタオルが重ねて置いてある。ふっと思ったのが、ホテル住まいみたいだなと。その時、ああと思ったんです。彼はこっちにすることに決めたんだと。それから私は食事の後の洗い物をしなくなりました。私が洗い物をしたりすると、気を遣っていることになってしまうんで、夫に甘え切ることにしました。
大竹 なるほど。正しいですね。
桜木 ヒモじゃないんですよ、決して。夫は四十年間、公務員をやって、子供たちを大学へ行かせて、その後で私が小説で稼ぐようになったんです。
大竹 売れてるタレントの亭主になる男っているじゃない。それがADだったりすると、結局うまく行かないのよ。それはなぜかって言うと、女の稼ぎで食ってるから男のプライドがキープできない。プライドを持つことを諦められれば女房とうまくやれるんだろうけど。
桜木 諦めないと駄目なんですかね。
大竹 昭和生まれの男がバスタオルを畳めるようになるには、どこかで諦める、切り替える決断がないと。
桜木 うちの夫にはその決断があったんでしょうね。ある時、あれ? って思ったから。
大竹 男のプライドもね、考えてみれば大したことないのよ。プライドって言えるかどうか分からないぐらいの大したことないものなんだけど、自分の肩にぴらぴら載ってるわけ。捨てちゃえば何てことないのになかなか捨てられないんだな。
女優でも、お笑いタレントでも、食えない男とくっつく人がいるわけですよ。男は薄っぺらいぴらぴらを取っちゃえば本当に楽しく暮らせるんだけど、それがなかなかできない。専業主婦と同じだからできるはずなんだけどね。
桜木 家庭の中での役割を男女逆転した時に邪魔になるのが男のプライドだとすると、それって昭和を引きずっているってことですよね。私たちが形成されてきた昭和ってどんな時代だったかを、考えるきっかけにもなりますね。
大竹 男女関係なく、手があいているほうが家のことをやるというのが当たり前になっていくんだろうね。
桜木 うちの夫は家事労働ってこんなにあったのかって驚いてると思います。掃除だけでも居間、寝室、台所、水まわり、お風呂など。最近犬を飼い始めて、モルモットと犬がいるんですけど、私も含めて朝から晩まで誰かに餌をやってます。ありがたいです。

五十代の最後の三年間で書いた六本の短編
――『情熱』に収録されているほかの作品には、中高年が恋愛の手前で引き返しているような関係が描かれていることが印象的です。それはなぜでしょうか。
桜木 きっかけひとつ、っていうのを、何となく知ってる世代なのはたしか。女子大生とでも仲よくなれちゃったりするわけですよね、大竹さん。
大竹 うん。
桜木 何か自分にとってのスイッチというかきっかけがあれば、すーっと恋愛関係に行けると思うんですよ。ちょっとした踏ん切りというか。でも、この世代が恋愛に行かないというのは、分別じゃないかとも思うんです。
その分別は何に支えられてるのかなって、書きながら思っていました。恋愛になりそうな時に情熱と分別があって、ある程度の年齢になると、分別をちょっとだけ重くしておくことで自分が保たれるのかも。弱さとうまくつき合うというか、そういうことってないですか。あえて恋愛に行かないという。
大竹 行ってから考えたっていいじゃん。
桜木 えっ、まさかの反応。
大竹 「兎に角」だっけ。『情熱』の最初の一編。十代の頃に文通していた二人が、四十年経ってカメラマンとヘアメイクで再会するじゃない。でも恋愛に行かないよね。行って駄目になるほうがロマンチックじゃない? でも、四十年経って何事もないというのも、いい感じはいい感じなんだよね。
桜木 期待もほのかで、結果もほのかというのがいいなと思うんですよね。付かず離れずが何となくよろしいのではと。
大竹 たしかに「兎に角」は桜木さんのその書き方のほうが正しいと思うんだけど、『情熱』には恋愛に走ってしまう話は入ってないんだっけ。
桜木 入ってないんです。そういう話を若い頃から書いてきたんですよ。デビューした時に「新官能派」という触れ込みだったくらいですから。年を取って、やっと恋愛に行かない関係が書けるようになってきました。
大竹 クリント・イーストウッドが最後までプラトニックなままの関係を映画にしていたよね。あの方、年を取ってから、恋愛に行かない話をやってる。『ミリオンダラー・ベイビー』なんかね。
桜木 あの映画よかったですね。
大竹 男の側からは恋愛に行かない。女の人がどう思っているか知らないけど。
桜木 なだれ込まないんですね。
大竹 俺はもう年だから男の側が行かないのも分かるけど、自分だったら行くかもしれない、と思うだけは思ってる。行かないのは相手に失礼なんじゃないかと。
二人で飲んでいて、女の人から「じゃあね」って言われたら「あ、行かなくてよかったんだ」と思うけど、なかなか「じゃあね」って言われないと、誰が背中を押しているのかは知らないけれど、男から行かなきゃ、と使命みたいなものを感じる時もあるね(笑)。早く「じゃあね」って言ってくれよと思いながら。
桜木 受け身なんですか。
大竹 それは受け身でしょう。
桜木 女があっての恋愛なんですか。
大竹 そう。俺からは行かない。年食ってハンデがあるから、行かないというより、行けない面もあるけど。こいつ、「じゃあね」って言わないぞ、「またね」も言わない。じゃあ、どうすんだよ、終電の時間が過ぎたら行くべきなのか……と。
桜木 そうか、都会には終電があるんだ。そこがひとつの分岐点になる。
大竹 分別で行かない男はなかなかいないと思うけどな。
桜木 じゃあ、私の書いてるのは絵空事になっちゃうなあ。美し過ぎる話になってしまいますね。
大竹 分別じゃなくて、肉体的な条件とか、いろんな理由で行かないというのはあると思うよ。「ひも」の朗人みたいに性的なことが駄目になっているとか。
桜木 いましみじみ考えちゃいました。『情熱』は私の五十代、五十七から六十手前にかけての三年間に書いた六本なんですが、この三年間を振り返るに十分な六本だったなと思います。私、こういう穏やかな、心が波立たない老後を選んだんだと思いました。だから、書いていてどれも自分が見えてくるお話だったですね。
小説のように前後を考えて行動はできない
大竹 さっきの「兎に角」の話に戻るけど、恋愛関係に進めるのに行かないのはやっぱりいいよ。
桜木 いいですか。
大竹 それがいいよ。行っちゃったら身も蓋もない、やっぱり。
桜木 身も蓋もない。うーん。何か終わりを前提とした始まりにはなりますね。
大竹 こう言うのは失礼かもしれないけど、読みながら、恋愛関係になってから別れることになってもいいんじゃないかな、ともちょっと思ったのね。まだ遠い先の話だから、どうなるか分かんないじゃないですか。それはこっちの妄想だけど。
桜木 大竹さんは分別でなく、情熱派?
大竹 いやいや、情熱なんかはないけど。小説の中では、恋愛関係に進んだらどうなるかとか、いろんなことを頭の中で考えるだろうけど、ふだんはあんまり考えないからね。どうなってしまうかなんていう先のことは。小説にはことの前後が出てくるから冷静に読めるけど、現実では「とんでもないことになっちゃったぞ」って後で思うようなことをやらかしてしまう。「どうしよう」って後で思うんだけど。その場は考えられないんだよね。
桜木 後先のことを考えないという点では、私は男女のことよりも小説のほうがそうですね。これを書いたらあの人がどう思うかとか考えたら書けないので一切考えてない。ものを書く人って、何かを犠牲にしてまで書くとかそんな気負いはなくて、自然と書かなきゃいけないところに行っちゃうんじゃないかな、気持ちが。
大竹 それは使命なのかなあ。
桜木 そういうふうになっちゃっているんだと思います。もう習い性というか。書かないと前に進めないような気がするんですね。
大竹 もう全身小説家じゃないですか、それは。前を向いて歩いてればネタに当たる。それが小説になるわけだから。
桜木 気をつけてくださいね。小説家と付き合ったら、ケツの毛まで抜かれますよ。
大竹 あ、そう?
桜木 では私も、大竹さんと終電を逃してみようかな。
大竹 俺、もうあんまりケツ毛も生えてないんですよ。
(2025.6.20 浜松町にて)
「すばる」2025年9月号転載