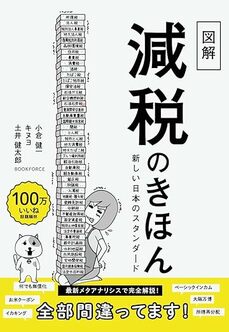行政の大きな課題は「税金の使い方」
ひるがえって、私が愛する日本における行政の大きな課題は「税金の使い方」である。
年金は若い世代ほど損をする仕組みであり、子育て支援も効果を上げていない。役所の無駄遣いや天下りなど、税金が正しく使われていない例が多い。
日本国憲法は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とあるが、前文には「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」(政治の力は国民から来ており、国民の幸せのために使うべきもの)としている。
税金は払う必要があるが、その目的は「国民の生命と財産を守ること」なのである。
この問題を解決するには、税金のルールを定める必要がある。税金の上限を決めたり、使い道を明確にすることが重要である。
都道府県や市町村に権限を与え、地域ごとに工夫できるようにすることも良い方法である。増税して行政を拡大する自治体と、減税して民間活力を生かす自治体が競争できる状況を作るべきなのだ。
様々な実証研究で「減税が答え」だと示しているが、日本の中央政府は地方の競争を妨げている。
本当の愛国心とは
イスラムの学者イブン・ハルドゥーンは「税金が低いと人々は元気になり、文化も発展する」と述べた。高い税金は人々の暮らしを苦しくするだけでなく、社会の発展を妨げるものである。
税金は政府のものではない。国民が働いて得たお金を預かっているものである。政府は税金を国民のために正しく使う義務を負う。高い税金を取り、無駄遣いを続ける政府にお金を預ける必要はない。
政府や行政組織ではなく、日本国民と日本社会を発展させる。そのために必要なことをし、阻害するものを批判する。これが本当の愛国心であろう。
文/小倉健一