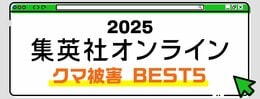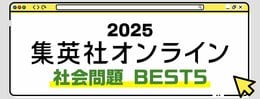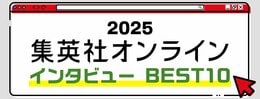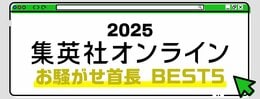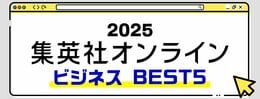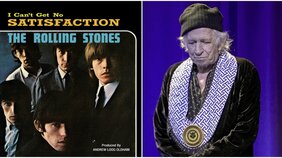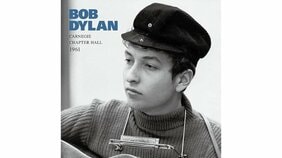「なんで自分たちが損をして、外国人や資本側が得するのか」
先の参院選(2025年7月)では既成政党離れが明確になり、新しい勢力である参政党や無党派系候補への支持が広がった。
その背景には円安がもたらした生活格差・資源配分の偏りが顕著になったことに対する国民の深い不満が形になった結果であったと思う。具体的に言えば長らく円安を放置した結果、インバウンドが円安の恩恵を受けたわけだ。
そして彼らの購買力は爆増の一途を辿った。例えば1ドル=150円であれば、彼らにとっては不動産、株式などの資産をはじめとして、外食に至るまで、ありとあらゆる日本製品が“半額”感覚に思えたのであろう。だから侵食がどんどん進んでいったのだ。
高級ホテル、百貨店、ブランド店、観光地の飲食店などは軒並み活況で、地方経済も一部では潤っているものの、これらは資本のある外資や大手、インバウンド特化企業だけが中心に享受しているだけで、多くの日本の中小企業はその恩恵を受けられていない。
円安に長らく苦しみ続けているのが、国民の約8割を占める庶民層や中小零細企業層だ。円安による輸入物価の上昇が食料品やガス、ガソリン、日用品の記録的な物価高騰を招き、特に価格転嫁できない中小事業者や非正規労働者、年金生活者、子育て家庭などは物価高騰に反して賃金が上がらず、生活が益々苦しくなる一方なのだ。
賃金は全くインフレに追いつかず、実質賃金は26か月も連続でマイナスとなってしまった。この結果、多くの国民が「なんで自分たちが損をして、外国人や資本側が得するのか」と理不尽さ・剥奪感を覚える構造になっている。
国民からの厳しい審判
一方で既成政党である自民党は日銀・経団連と近く、結果的に円安誘導政策を黙認しつづけていることが庶民に対して「生活苦を無視している」という印象を与えたのだと思う。
おまけに石破首相は不評だった給付金を一度は取りやめ、消費税減税に舵を切り始めたものの、結局は財務省に逆らうことができずに再び給付金を持ち出すなど、即効性のある物価高対策よりも財務省の意向を優先させたように映ったことも失望へ繋がったのだと思う。
もうひとつは保守層を取り込みたいという安易な理由から、批判を浴びながらも旧安倍派の「裏金議員」を公認し続けたことも完全にマイナスに働いたのではないか。旧安倍派の議員数は、今回の参院選の結果を受け、2024年9月の党総裁選のときから4割ほど減るなど、国民から明らかな厳しい審判が下っている。