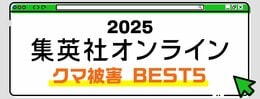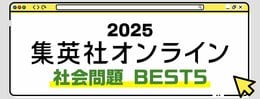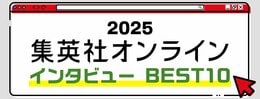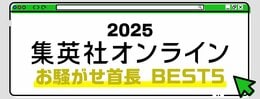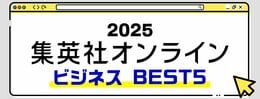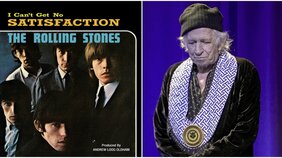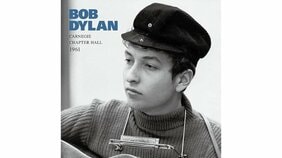公明党も散々な結果に
その結果として自民党右派を凌駕する右派政党が乱立し、自民党はその陰に埋没することになった。自民党の比例代表得票数は、前回1,820万票だったのに対して 今回1,280万票へと、約540万票も減少していて都市部や若年層を中心に自民党離れが起きているのは確実だ。
そして連立与党である公明党も国民寄りの生活者支援の姿勢を打ち出してはいるものの、円安を容認している時点で矛盾が生じており、こちらも散々な結果となった。
2022年参院選では、比例代表において約618万票(得票率 11.66%)だったが、2025年参院選では約521万票(得票率約8.8%)と、こちらも大きく減少している。
この急激な票の落ち込みは、政党としての影響力低下を反映しており、公明党の支持基盤にとっては重大な警鐘と言える。
既成政党離れという点でいえば、野党第一党に君臨する立憲民主党も同じだろう。比例代表での得票数でも 約739万7000票(得票率12.50%)で、2022年から微増しているものの得票率は12.77%→12.50%と、実質ほぼ横ばいだ 。これでは国民からの期待度は限定的だといわざるを得ない。
与野党問わず、既成政党というのは「どの党も自分たちの苦しみに本気で向き合ってくれていない」という中間層以下の怒りが直撃した結果なのだろう。
一方、大躍進した参政党は「生活を守る」「日本を取り戻す」「外資や移民への警戒」といった明確でわかりやすいメッセージを掲げており、それらの期待感から有権者のシフトが増えているはずだ。
円安放置という“経済の歪み”が政治の歪みを生んだ
とくに為替や物価高に対する「感情的共感」「直感的な不公平感」へ訴えることに成功したといえよう。要するに経済のディテールよりも「我々の暮らしを大事にしてくれるのは誰か?」という問いに響く構図だったのだろう。
結論から言えば円安放置という“経済の歪み”が政治の歪みを生んだといえるのではないか。円安放置が作り出した「外資や富裕層に有利で庶民に不利」な経済環境の概念が政治不信・アンチ既成勢力への投票行動に結びついた。
そして、この状況は同時に日本の民主主義の健全性や中間層の“声の通りにくさ”を浮き彫りにしたといえるであろう。
そういう国民の声が多いわけだから、本来は政府も日銀も円高方向へと舵を切り、所得再分配・内需主導の経済モデルへの転換をすべきなのだが、冒頭でもふれたように日銀も財務省も政界も経済界も円安を維持することが税収アップに繋がるし、自動車産業をはじめとする輸出の大手企業が潤うと考えているので、庶民との間には大きな隔たりがある。
だから為替と暮らしの関連を、政策言語として“庶民目線”で語れる政治勢力の出現に多くの国民が沸いたのだと思う。