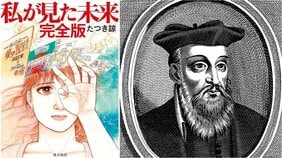フランスの認知科学者が指摘する半真実
フランスの認知科学者、ベンジャミン・イカールが2019年に発表した博士論文「嘘、欺瞞、戦略的省略:定義と評価」は、この問題に鋭い分析の視座を提供する。イカールは論文の中で、嘘や欺瞞、そして意図的な情報の省略がどのように機能するかを論じている。
「曖昧さは、嘘と誠実さの関係において諸刃の剣である。協調的な話し手が世界について不確かな状況では、曖昧さは誠実さのための資源を提供する。それは、偽であったり不当に本当であったりするような、より正確な発言をすることを避ける。そして、それはクオリティとクオンティティのグライス流の公理を満たすための最適な解決策であると間違いなく言える。一方、協調的でない話し手が世界について完全に情報を得ている状況では、曖昧さは欺瞞のメカニズムになり得る」
「我々はそのような2つのケースを区別する。話し手が聞き手から情報を隠すために意図的に不正確であるケース。そして、話し手が曖昧な述語の持つ意味論的な不確定性を利用し、ある意味では真実だが別の意味では偽である発言を生み出すケースである。我々が半真実と呼ぶこのような発言は、嘘とみなされるべきだろうか。その答えは、我々が示唆するように、文脈に依存する。明確な真実性の欠如は、虚偽を断定するのに常に十分というわけではない」
その書類が「在学証明書」や「単位修得証明書」だったとしたら
この分析は、田久保市長の行動を理解する上で極めて示唆に富む。市長が議長に見せた書類が、もし偽造された卒業証書ではなく、例えば本物の「在学証明書」や「単位修得証明書」だったとしたらどうだろうか。
その場合、書類自体は本物だが、それを「卒業を証明するもの」として提示する行為は、まさにイカールが言うところの「半真実」を利用した欺瞞行為にあたる。また、会見で書類の正体について説明を拒み続けた態度は、情報を隠蔽するための「意図的な不正確さ」であり「戦略的な省略」だ。
田久保市長は、言葉や物事の曖昧さを最大限に利用し、有権者と議会を欺こうとした。それは「勘違い」などという生易しいものではなく、計算され尽くした欺瞞の戦略なのである。
文/小倉健一