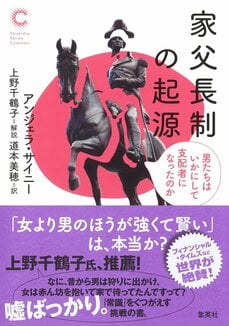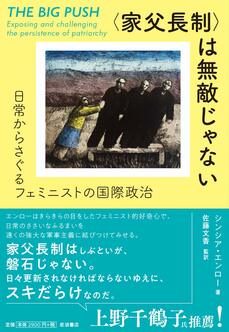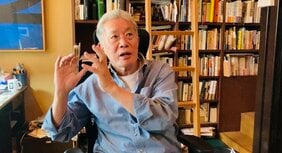私たちの目の前の状況は変えられる!
佐藤 それにしても、『家父長制の起源』の解説で上野さんが紹介してくださった「栄養人類学」のお話は面白いですね。ジェンダーの視点を持って考古学を研究する人が出てきた結果、何がわかったか。これまでの様々な発見が、私たちが生きる現代の価値観のバイアスに左右されていたと判明していく。つまり、私たちは「見たいものを見ていた」ということなんですよね。
従来の、「石器時代にはハンターは男性だった」「女性は火を焚いて子守りをして待っていた」みたいな話も、実はジェンダーの視点を持ち込むと怪しくなってくる。いやいや、ちゃんと女性のハンターもいたし、女性たちは小動物を狩るなど、重要な役割を果たしていたんだよ、と。
あるいは、壁画を描いた人は当然男性だと思われていたけれども、実は壁画アーティストに当たるような人にも女性が含まれていた、とか。そういうことが次々と明らかになっている。その最新の成果が盛り込まれているというのも『家父長制の起源』の魅力だと思いました。
上野 いま、考古学は技術的にものすごく進化しています。年代測定法も、炭素同位法という昔のやり方だけではなく、DNA鑑定もできるようになって、埋葬者の性別だけでなく親族関係もわかるようになった。その成果で古代史がすごく変わってきました。そういうことを書いた上野の解説、力が入っています。是非、『家父長制の起源』を買って読んでみてください(笑)。
『家父長制の起源』の本文では、当然ながら日本のことはあまり扱っていないので、私の解説の中では日本古代史の考古学的な発見についていくつか言及してあります。いま、古代史は日本史の中でもすごくエキサイティングな分野です。テクノロジーが発達して、新しい発見が次々と生まれているからです。
首長として埋葬されていた人が女性だったとか、そこに一緒に埋葬されている人が一族なのか、親子関係があるかどうか、というようなことが全て同定されるようになっている。今までの常識を覆すような証拠がどんどん出てきているわけです。
でも、佐藤さんがおっしゃった通り、私たちがいま生きている社会のジェンダー二元論をそのまま常識として投影した、「古代も同じだっただろう」というような乱暴な解釈が横行している。事実を突きつけられても、バイアスに凝り固まっていてなかなか認められないのが学者だ、ということも書いてありましたね。
佐藤 そうなんです。そこがすごく難しくもあり、興味深いところだとも思いました。同時に、それに抵抗する側、私たちの側が陥りやすい罠についてもきちんと言及されています。
たとえば、上野さんが紹介してくださったチャタル・ヒュユクの女性像。

こうした出土品から、下手をすると「昔は母権社会だったんだ」という主張が生まれてしまう。
かつては女神が非常に力を持っていて、女性が大切にされていた「母権社会」だったという、いわゆる“母権起源説”です。その社会が家父長制の到来によってひっくり返されてしまったんだ、という敗北の物語につながっていくわけですよね。
ところが、そうした発想の根底では、現代のことを不満に思っている私たちの目を通して、「過去を美化する」という単純化が働いてしまっている。これもまた陥りやすい罠だということが指摘されていて、とても優れた点だなと思いました。
と同時に、著者のサイニーは、だからといってチャタル・ヒュユクの母権起源説を提唱したマリヤ・ギンブタスという考古学者を、過剰に批判しすぎることも避けています。
確かに話を単純化してしまったところがあるかもしれないけれど、それはジェンダーの視点が入る前の男性の考古学者たちが「見たいものを見てきた」のと同程度の単純化です。おとぎ話をつくり上げたギンブタスだけが学者として劣っている、という一面的な評価の仕方はしていない。こうした姿勢にも好感が持てました。
上野 母権制起源説というのも、もうひとつの危うい「神話」ですからね。もし人類の起源が母権制だったとしたら、その母権制が家父長制に敗北したことになる。そうなると、今度は敗北が決定論になってしまう。女性の敗北は歴史的に運命づけられていたのだ、という話になりますから。
最後に、『家父長制の起源』から文章をひとつ読み上げてみようと思います。
家父長制は今も常につくり変えられていて、時には以前よりも大きな力をもつこともある。
(『家父長制の起源』350ページ)
近代になって、家父長制は明らかに強化されました。家父長制は時代によって姿を変え、どんどん新しい姿を取っていきます。
でも裏を返せば、「歴史のどこかに始まりのあるものは、必ず歴史のどこかに終わりがある」ということです。そう考えると、今のような真っ暗な状況も永遠に続くわけじゃないって思えるからよいですよね。
結局、家父長制を止められるかどうかは私たちにかかっている。目の前の状況は変えることができるんだ。そういう希望を与えてくれる本ではないでしょうか。