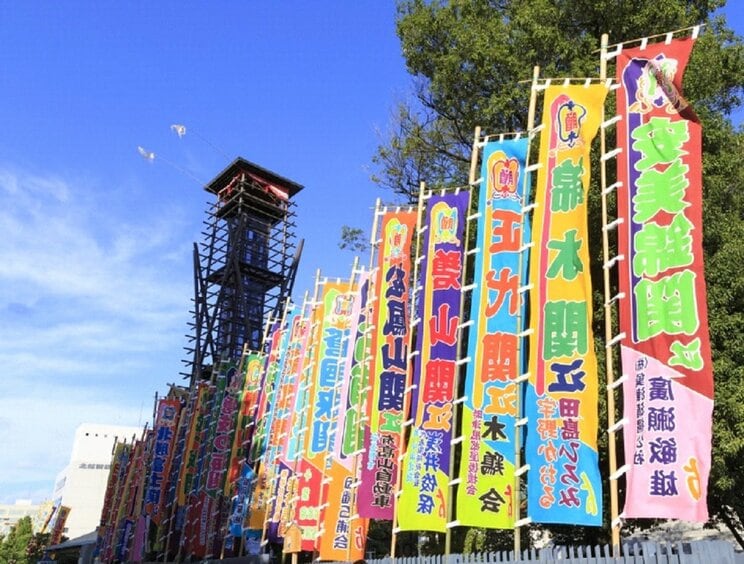「横綱として相応しくない相撲がある」
というのも、豊昇龍が勝った時の取組内容や取組後のふるまいに対して「横綱に相応しい品格ではない」という批判を解説者や好角家から受けることが少なからずあるからだ。
強い相撲の例えとして「横綱相撲」という表現があるが、実際の大相撲においてそれは果たしてどのようなものなのだろうか。
素晴らしい横綱相撲として称賛されるのは、相手の相撲を受け止めてそれを上回るというスタイルではないかと思う。これに該当するのはかつての大横綱である双葉山、大鵬、貴乃花、そして年間86勝4敗という記録を2年連続で残した時の白鵬だろう。
横綱として相手に攻めさせ、技術と経験、そして力で上回る。その姿には気品があり、そして美しさもあることは間違いない。白鵬も双葉山の相撲を研究する中で「後の先」というキーワードを口にしていた時期もあった。
これは相手より一瞬遅れて立つものの、その分、相手をよく見て自分が先手を取って攻めかかる立ち合いのことで、強い力士の一つのスタイルといって差し支えないのではないかと思う。
ただ、このような相撲は誰もが取れるものではない。
国民栄誉賞も受賞した元横綱・千代の富士は体格に恵まれていなかったこともあり、頭を付けての速攻と、「ウルフスペシャル」と呼ばれる豪快な投げが一つのスタイルだったし、朝青龍は曙や武蔵丸などハワイ勢に代表される巨漢力士の時代にスピードで革命をもたらした。
このようにそれぞれに合った相撲があるのだが、横綱は勝って当たり前、負けると批判を受けるという特殊な地位でもあり、ただ勝つこと以上のものが求められる。
「横綱として相応しくない相撲がある」
そうした言葉とともに、特に相手の動きを立ち合いから止める張り差しやかち上げ、虚を突くための変化を繰り出すと、どうしても批判の声は大きくなってしまう。
大相撲のルールで、これらは特に制限されるものではない。現に小兵や下位の力士が格上の力士を相手にこうした相撲を取ると非常に盛り上がることもある。