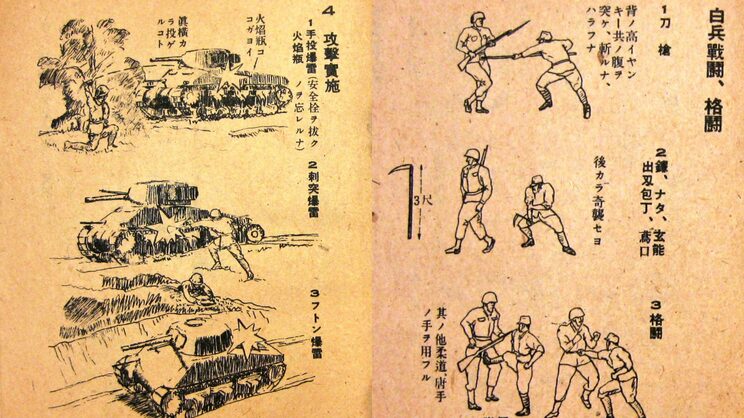「軍が悪かった」という言い方をされるが戦争責任は行政・教育・メディアを含め、「軍官民」にある
林 今の川満さんの話と重なるかもしれませんが、沖縄戦だけでなく、戦後日本社会で戦争を振り返る際に、もっぱら「日本軍が悪かった」ということが語られます。
でも戦争を準備し、実際に戦争を戦うことは、軍だけではできないんです。戦争を遂行するために、異論がある人々を抑圧する、言論を統制する、そして一方で人々を戦争に向けて動員する、そのために人々の意識を変えていく、という行政の役割があった。行政の役割や教育の役割も、極めて大きいのです。
そこについて検証することが、たとえば沖縄戦の場合、これまで非常に弱かった。「日本軍が悪かったんだ」というのは、沖縄では誰もが一致できるところだと思うんですが、「行政の責任」についての検証は弱かった。
今日の日本社会の問題を考えても、別に自衛隊が戦時体制を作っていっているわけじゃありません。一般の行政が、それを作っていっているのです。そこには教育もメディアも加担しています。
ですから沖縄戦を含め、かつての日本の戦時体制がどうやって作られていったのか、行政がそれをどういうふうに作っていったのかということをきちんと説明しないといけない。沖縄戦の場合、そこがすごく足りなかったと思うので、そこをかなり意識しながら今回の本では書いています。
そして、それが沖縄戦に突入するまでだけでなくて、米軍が上陸した4月、それから5月という戦闘のさなかにも、実は行政組織はずっと動き続けていて、日本軍と一体となっていました。たとえば南部だと、ガマの中に隠れているその地域の人々もそうだし、他から逃げてきて避難している人々も含めて、村長とか助役、字の区長、さらに警察とか、行政が軍と一緒になって足腰の立つ者を動員して駆り立てていったのです。そういう行政の役割をきちんと書きました。これは現在の日本の問題とも、まさに重なるので。
今年(2025年)は治安維持法が制定された1925年からちょうど100年なので、治安維持法の問題が少し取り上げられていますが、実は治安維持法を含めた「弾圧のための法規」を適用したのが警察官僚です。
そして実は当時の沖縄の島田叡知事も荒井退造県警察部長もともに警察官僚で、特に荒井警察部長は特高(*1)の経験が多い特高官僚ですから、沖縄の行政が民間の人々を戦争に駆り立てていく上で果たした役割が大きい。それをきちんと見る必要がある。従来の沖縄戦の本では、そこがみんな弱かったと思うので、かなり丁寧に書いたつもりです。
*1 「とっこう」=特別高等警察の略。戦前・戦中の内務省管轄の秘密警察で、国体護持のために国民を監視することが任務。特に共産主義者や社会主義者、反戦論者、朝鮮半島や台湾、満州など日本の植民地出身者を監視・弾圧した。労働者の悲惨な状況を描いた小説『蟹工船』の作者、小林多喜二を逮捕し拷問で殺したことでも知られる。戦争に反対する者を逮捕・拷問・収監した。
川満 そこを本当に丁寧に書かれていますね。林先生がおっしゃるように、そもそも戦争というのは、軍だけではできっこないものです。官だけでもできません。沖縄戦の最中、「軍官民共生共死」というスローガンが使われましたが、まさに軍人も公務員も民衆も一緒にならないと、実は戦争はできない。
だから今現在も、民衆が戦争を正当化してしまうと、もう一気に戦争への道に進んでいくでしょう。沖縄戦をずっと研究してきて、今それが非常に怖い感じがします。今年は80年という節目でもあるし、ここで「軍と官と民の戦争責任」をより明確にしないと。そういった意味で今、特に沖縄県の行政の責任が明るみに出てきていますから、あと一押しが必要です。
私たちが生きている今、国は実際にいろんな法律を通しています。戦争につながる法律が「本当にいいのかどうか」という議論もまともにされないまま、どんどん通されています。でも今ここにいる私たちは当事者なのです。そういう当事者としての戦争責任という部分も、沖縄戦を通して明らかにすべきじゃないかと考えています。