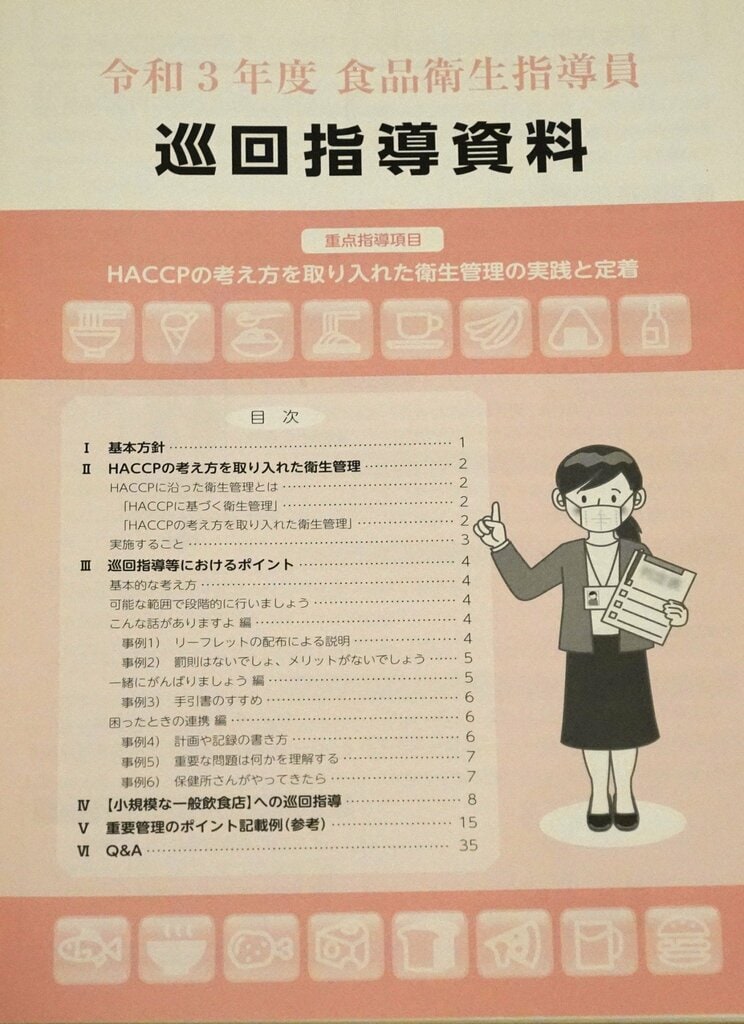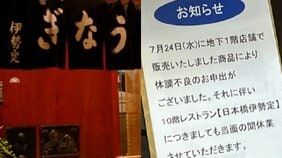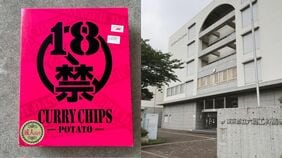指導員が死亡するとその日を退任日とし、同じ日付で息子を後任者として登録
「当然身に着けるべき技術がない。無免許運転と同じです。そうした人たちが飲食店を巡回してきたわけです」
この問題を告発した山梨県食協の内部事情を知るAさんはそう話した上で、なり手不足との口実が通らない別の問題も告発した。
「私自身が知らない間に、私の名前が指導員として登録されていたんです。指導員数を増やすためです。登録された何年も後に気づきました」
Aさんによると、県食協関係者には指導員活動をしないのに登録されている人が他にもいるという。さらに「指導員が死亡すれば店を継いだ息子さんらを後任者として登録することも起きていました」と続けた。
この指摘をX専務理事に問うと「わからない」との返答だった。D氏は「そんなことはないと思う」と否定した。だが集英社オンラインが確認した内部資料には確かにAさんの名が指導員として記載されている。また、県東部の地区食協では保健所職員2人を指導員として登録していたことも発覚している。(♯2)
なぜ指導員数を水増しするのか。日食協によると、昨年2月、ある新聞社から「本人が知らない間に指導員になっていた人がいるらしい。補助金を実際より多く受け取るためではないか」との問い合わせがきたという。
この疑念に日食協担当者は、「日食協から各都道府県食協への補助金額は指導員数にはリンクせず、前年度の活動実績で決まります。そのため指導員数を水増しする理由はわかりません」と、補助金狙いで指導員を増やす図式は成立しないと否定、新聞社にもそう答えたと話した。
新聞社は結局、問い合わせた内容に絡む記事を報じていない。
だが問題は、山梨県食協からさらに下部組織に支給される補助金だと県食協関係者は証言した。
「例えば2023年度には当時5つあった各地区食協に計約400万円の補助金が県食協から入っており、他に県からの補助金もあります。これら補助金の地区食協ごとの配分額は、所属の指導員数が反映されます。
各地区食協が受けた補助金の一部はさらにその下部組織の『支部』に分配されますが、ここでも支部の指導員の数が多いほど額は増えます。そして、ある地区食協では支部に補助金を配っても、領収証も使途の報告も求めてきませんでした」(山梨県食協関係者)