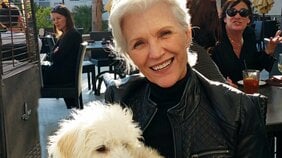ディズニーランド化するプロ野球観戦
――日本のプロ野球だとコロナ禍以降に中野さんが観戦していて、すごく変わった部分などはありますか?
印象論ですが、昔と比べると観客が試合途中に帰らなくなったと感じます。プロ野球のライブエンターテインメントの希少性に観客が気づいたのかもしれませんし、もう一つは「勝ち負けにこだわる」という勝利至上主義の感覚が薄れたのかもしれません 。
たとえば昔なら、横浜ベイスターズ(現在の横浜DeNAベイスターズ)が強かった頃に九回にクローザーの「大魔神」こと佐々木主浩投手が出てきたら、相手チームのファンがゾロゾロと帰途につく光景がよく見られました。
今は勝ち負けだけではなく、自分が応援しているチームを最後まで応援し続ける。負けている状況では若手のチャンスをつかみたくてもがいている選手たちが出てくることもあるので、彼らの頑張りを見守るわけです。以前より解像度が高い観戦スタイルが定着しつつあると感じます。
――「AKB48は高校野球をイメージしていた」と秋元康さんも言われていますが、AKB48以降に発展したアイドルの推し文化や、IT企業が親会社になることで観客を球場に呼ぶ工夫をしていることも変化に関係していそうです。
そうですね。さきほどの解像度高く、より深くスポーツを楽しむという見方が出てきた。もう一方ではIT企業が親会社の球団などはいろんな工夫をして集客しているんですが、すごくディズニーランド的なんです。
アメフトのスーパーボウルのハーフタイムショーなどにかなり影響されていると思いますが、エンターテイメント化が著しくなっています。「ハレとケ」という言い方がありますが、観戦は「ハレの日」で本当に祝祭の日みたいになっていて、もともとあった縁日っぽい要素が拡大してエンタメ化されているんです。
プロスポーツにはもともと国民に対して「運動の奨励」という目的があったことを論じているんですが、それが現代では消えていき、すべて消費文化としてお金を使わせる方向に向かっています。
――客単価を上げていくという企業努力を惜しまないことによって、より消費文化が加速してしまう。
客単価を上げるという流れはコロナ以前からありました。しかしプロスポーツから「運動の奨励」という目的を取り去り、消費文化に全振りすると、スポーツの本義からますます離れていく、ということは意識される必要があると思います。