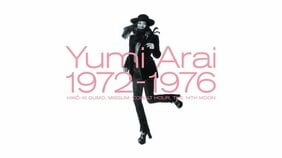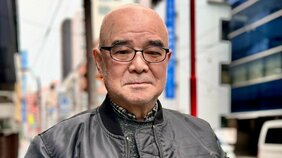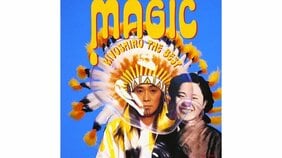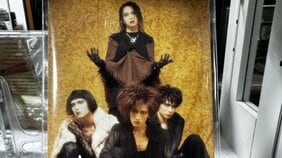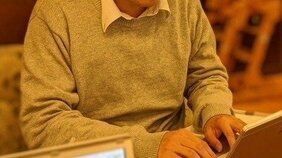「シャングリラ」は「暗い曲のつもりで書いたんです」
――チャットモンチー在籍時には、「シャングリラ」など数々のヒット曲の作詞を担当されました。改めて、自分が書いた歌詞に曲がつけられていくのは、どのような感覚なのでしょうか?
チャットモンチーを始める前から、オリジナルバンドを組んでライブハウスに出入りしていて。その頃から自分で作詞をしていて、書いた詩に曲がつくこと自体はとてもうれしいことでした。それまでは、書いた歌詞を自分の中の引き出しにしまっておくだけだったのに、そこに音が乗って、誰かに届けられる。それが純粋にうれしかったですね。
同時に、不思議な感覚もありました。音楽における歌詞は、言葉だけのときとは違い、感情のようなものが上乗せされる。たとえば、自分ではじっとりとした詩を書いたつもりなのに、曲がつくことで思いがけず明るい印象になったり、悲しい雰囲気に仕上がったりします。
チャットモンチー時代にも、そうした経験がありました。たとえば「シャングリラ」は、歌詞を読めば理解してもらえると思うのですが、もともとすごく暗い曲のつもりで書いたんです。でも、完成した曲はとてもポップな仕上がりになった。そうした経験を通じて、「楽曲と歌詞は、ぴったり一致していないほうがクールかもしれない」と思うようになりましたね。
――ご自身のバンドで作詞されていたときと比べて、他のアーティストへ歌詞を“提供”する際に、意識していることはありますか?
いくつかありますが、やはり「等身大ではない」という点が大きいですね。歌い手が10代の方もいれば、50〜60代の方もいる。たとえばチャットモンチーでは、ボーカルのえっちゃん(橋本絵莉子)の人となりをよく知っていたので、完全にイコールとはいかなくても、自分の声に近い感覚で書くことができました。
でも、ももいろクローバーZや私立恵比寿中学に提供する際は、そうはいきません。誰が歌うのか、どんなファン層の方々が聴くのか――そこはやはり意識して書くようにしていますね。ただ、ファンの方々が好みそうなものをそのまま書くのではなく、いい意味で裏切るような歌詞にすることもあります。
――高橋さんは小説集なども執筆されていますが、それらを書く際と作詞では異なる視点があるのですね。
まさに今回の本のテーマにもつながりますが、小説とは違って、歌詞では「論理」よりも「言葉の響き」や「リズム」のほうが重要になることがあるんです。多少辻褄が合わなくても、そこから生まれる違和感が逆に面白くなることもある。言葉が音楽と重なったときに、リスナーの中でどう“弾ける”のか――そのコンビネーションを一番意識していますね。