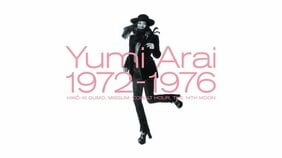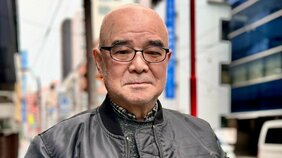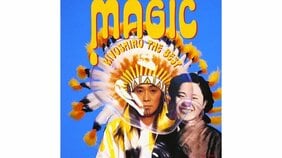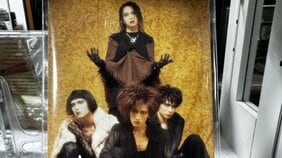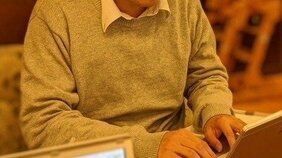デジタルネイティブ世代は表現が上手い?
――近年音楽プラットフォームが変化する中で、若い世代のアーティストの歌詞に対してはどのような印象をお持ちですか?
書籍の中でも触れましたが、たとえば優里さんの「ドライフラワー」。普通、ドライフラワーというと「永遠」の象徴として捉えられがちですが、この曲では「いつかは色褪せる」と表現されているんですよね。それを聴いたとき、「素晴らしいな」と思いました。
もちろん何に影響を受けているかは人それぞれですが、デジタルネイティブと言われる世代は、すでに「表現すること」に慣れているのかなと感じます。
――SNSの発展もあり、「バズる文章」を作るのが上手ということでしょうか?
それもあるかもしれませんね。ただ、それだけではなく、自分自身の体験がそこに加わっていないと、「ドライフラワー」のような歌詞は生まれないと思います。
――チャットツールやメールでのやりとりが一般的になったことで、文章で自分らしさを表現することが難しくなっているのかなと思います。書籍の主題にもなっていますが、「自分らしい文章」とは、どのようなものを指すと思われますか?
「普段、自分が喋っている感覚に近い“ビート”で書く」ということなのかなと思います。ビジネスシーンでは、どうしても自分のありのままを出してメールや文書を書くのは難しいですが、プライベートな文章では、なるべく普段の話し言葉に近い感覚で書くと、自分らしさのある素敵な文章になるのではないかなと。
そういう意味で、今だとスマートフォンの「予測変換機能」によって、自分の言葉のビートが乗っ取られてしまうこともありますよ。たとえば「さすがです!」と送りたいだけなのに、普段使わない「流石です!」と何気なく予測変換で漢字にしてしまう。無意識のうちに、自分のリズムや言葉の選び方が影響されてしまい、文章が自分のものではなくなってしまったり。だからこそ、できるだけ自分のビートを意識しながら、言葉を選ぶことが大切なのかなと思います。
――最後に、『いい音がする文章』を書き下ろすことで、ご自身の中で新しい気づきありましたか?
たくさんありましたね。これまでも「歌詞はビートに近いものがあるな」と何となく感じていたのですが、書きながら見つめ直すことで、それが確信に変わった気がします。
「言葉が好き」ということと「リズムが好き」ということは、まったく同じとは言えないかもしれませんが、どちらも自分にとって同じくらい好きなもの。これからも、今までどおり大切にしていきたいですね。