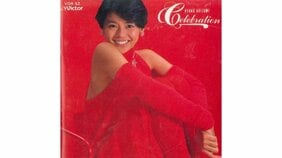それでも農家を続ける理由は…
Aさんの話を聞けば聞くほど、コメ農家を取り巻く現状は厳しく、明るい未来の兆しも感じられない。そして、それは消費者にダイレクトに跳ね返ってくる。
「コメ農家が割に合わないのもたしかだし、一方で今のお米の価格が消費者にとって高いっていうのも事実なんですよ。我々から見れば今までが安すぎたって話ではあるんですが、ある年金生活者の知人は『コメが高くなったから最近パスタばかり食べている』とこぼしていましたよ。何か根本的に手を打たないと変わらない時期にきてるんだと思います。
私自身も、利益もろくに出ないコメ農家をやり続ける理由は、田んぼを放置しておくわけにはいかないという一心だけです。手入れをしなければすぐに雑草や木で荒れていくので、周りの方にも迷惑をかけてしまいます。どうせ手入れをするのならコメを作ろうって、そんな感じなんです。だから代わりにやってくれる人がいれば、田んぼも貸したいぐらいですよ。現に畑も持っていたのですが、畑はもう貸していますから。私の周りはそんな感じの人が多いですね」
降ってわいたコメ騒動や異常高値も、ふたを開けてみれば農業の構造的な問題を国が放置してきたからにほかならないことがみえてきた。
貧困家庭が増えて子どもたちが満足に食事を摂れなくなったのはなぜか。民間に“子ども食堂”なる不思議な食事提供施設が増えたことを美談とするニュースが流れ、フードロスを拡大連鎖するコンビニ弁当やおにぎりを“補給源”にすることを「普通」にした文化とは何なのか。
「根本的な対策が急務」というAさんの懸念が、もはや笑ってごまかせる個人の意見レベルでないことを、政治家や官僚は思い知るべきだろう。
※「集英社オンライン」では、今回の記事についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX(旧Twitter)まで情報をお寄せください。
メールアドレス:
shueisha.online.news@gmail.com
X(旧Twitter)
@shuon_news
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班