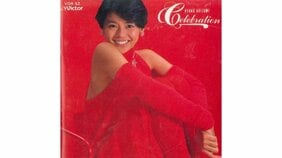15回の墜落事故で米兵65人が死亡
陸海空の自衛隊が保有する中で、オスプレイほど効率の悪い航空機はない。昨年は2回目となる飛行停止があった。昨年11月に米国内で墜落につながりかねない事故があり、一昨年11月、鹿児島県の屋久島沖で墜落し、乗員8人全員が死亡した米空軍オスプレイの事故との類似点が見つかった。
そのため、米軍はオスプレイの飛行停止を決めたのだが、陸上自衛隊も米軍に歩調を合わせて、保有する全17機の飛行を見合わせたのだ。
ちなみに、1回目の飛行停止は屋久島沖の事故の直後のこと。米軍がオスプレイの飛行を停止したことを受け、自衛隊も追従し、その飛行停止は3か月にも及んだ。
オスプレイは米国での開発段階から事故が相次ぎ、これまでに米軍機は15回の墜落事故で米兵65人が死亡している。海軍、海兵隊、空軍の3軍で400機以上のオスプレイを運用しているが、人為的なミスを除けば、屋久島沖の事故につながったナセル内の金属片発生、ローターとエンジンをつなぐクラッチの不具合、猛烈な下降気流が跳ね返って起きる失速など、構造上の問題が目白押しだ。
昨年11月に米国内で起きた事故では、大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」の随伴機だったオスプレイが右エンジンから出火し、緊急着陸している。米政府がオスプレイを安全な機体と考えていれば、随伴機ではなく、大統領専用機として活用しているはずだ。
事故多発を受け、オスプレイはイスラエルなど購入を検討した国はあるものの、実際には1機も売れず、米国は2026年に生産ラインを閉鎖する予定だ。開発した米国以外で唯一、購入したのが日本だ。それも政治案件として導入された。
航空機を含む武器類は本来、ユーザーである自衛隊が選定するが、10年先の安全保障環境を見通して策定する「陸上自衛隊長期防衛見積り」にオスプレイの名前はなかった。オスプレイの2倍以上の人員や物資を空輸できるCH47大型ヘリコプターを55機も保有していたからだ。
なのに、日本がオスプレイを導入することになったのは、米海兵隊が沖縄配備を進めた2012年当時、沖縄から上がった強い配備反対の声に対し、民主党政権の玄葉光一郎外相が「安全性を訴えるため、自衛隊も保有すべきだ」と提案、森本敏防衛相が同調して調査費を計上、これを安倍晋三政権が引き継ぎいで導入を決断したことによる。「沖縄の民意」より「米軍の意向」を優先した政治判断である。
その結果は見てきた通りだが、オスプレイの効率の悪さを示すデータはまだまだ他にもある。陸上自衛隊版オスプレイが訓練に登場する機会は毎年、数えるほどしかない。防衛省は2022年11月、暫定配備先の木更津駐屯地から東京都の立川駐屯地へ訓練としてオスプレイが「月数回飛来する」と発表したものの、実際に飛来したのは翌年2月、3月、4月の各1回の合計3回だけだった。以後、オスプレイは1機も立川駐屯地に飛来していない。まさに「動かざること山のごとし」だ。