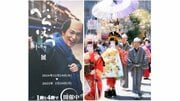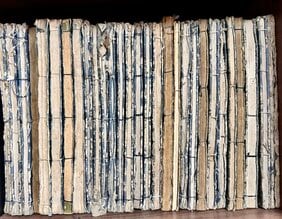吉原が生んだ絢爛豪華な文化と過酷な境遇の二面生
――『べらぼう』が放送されたことで、実際の吉原(現在の地名は東京都台東区千束)に何か変化や影響はありましたか。
渡辺豪(以下、同) 第2回が放送された翌日が成人式の祝日だったせいもあってか、普段は見かけないくらい多くの街歩きの大集団、とくにお年を召した方々がリュックを背負った姿をお見かけしましたね。あんなに多くの人が吉原の街を歩いているのは初めて見ました。
近年メディアで大きく遊郭が取り上げられた作品で言えば、2019年に『鬼滅の刃』遊郭編がありましたが、その時は私の見る限り、聖地巡礼といった街歩きには展開されず、無風でした。コロナもありましたしね。
――『べらぼう』を観た視聴者によるSNSの投稿を見ると、性売買を肯定している、などの批判が多く寄せられています。
『べらぼう』を観る難しさは、史実に基づいているとはいえ、テレビドラマという虚構を用いて描いている点です。もしこれが「史実を忠実に描いた再現映像」であれば、歴史的事実と違いがあれば駄作、正確であれば名作と、観る側に求められることは単純です。
しかし、フィクションを前提とした場合、何を描くのか、何を描かないのか、描くのならどう描くのか、そこは制作側の価値判断が介在しているので、このフィルターを一度通したものを観ていることを自覚する必要があります。
――遊女に関しては、絢爛豪華な側面がある一方、性の搾取構造の中で悲惨な境遇にあった、という歴史があります。
NHKとはいえ、視聴者の期待に応えるため、ある程度は遊郭の煌びやかな側面を押し出すのは避けられないだろうし、娯楽性の強いドラマである以上、そうした展開は当然だとも思います。反面、悲惨な残酷描写をふんだんに入れたからといって、ドラマから得られる喜びや学びは乏しいのではないかと思います。
いわゆる残酷物語的なフィクションは、視聴者に安易なカタルシスを与えるだけです。興味が育たず、そこで「スッキリ」して終わってしまう。民放なら気に掛けないかもしれませんが、当時の社会構造や人々の価値観、背景も含めて描いてほしいなと。受信料を徴収されている私としては、NHKにその水準を期待しています(笑)