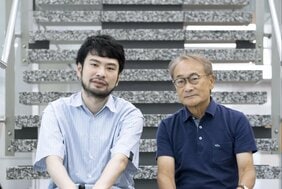小説を書き始めた理由
小池 又吉さんの最初の小説「夕暮れひとりぼっち」も子どもが視点の作品でしたよね。地味なタイプの少年がある老人と出会って、手品にハマる。そのうちに自分でもできるようになると、同級生が「見せてくれよ、友達だろ」なんて都合のいいことを言ってくる。そういう言い方をする同級生がいたし、そういう論理があったなぁと鮮やかに思い出させてくれる作品でした。
又吉 子どもの頃を振り返ると、なんでそんなことになるのかなってことの連続やったんですよ。さっき「ずれ」って話がありましたけど、別の言葉で言うと他人との間で摩擦を感じ続けてたというか。ずっと嫌がらせを受けているような、ほっといてくれへんかなって思うような、そんな感覚を大人にも同級生にもずっと抱いてて。だから最初の小説は、作中のできごとは実際に経験したことじゃないとはいえ、子どものときに感じたことを忠実に表現しようと思って書きました。とはいえ「そろそろ帰ろかな」も「夕暮れひとりぼっち」も、まだ自分の意思で小説を書こうと思ってなかったときの作品なので読み返すのは怖いですね。
小池 自分から積極的に小説を書こうとは思わなかったんですか?
又吉 小説自体はずっと好きだったんですけど、面白い小説を書く人っていっぱいいるじゃないですか。だったらわざわざ自分が書く必要あるんかなって思ってしまって。でも、声かけてくれる編集者さんはいたから、僕のこと説得してくれませんか? って頼んでました(笑)。それなら書かなあかんわみたいな気持ちになる理屈を自分で見つけたいんですってお願いしてました。
小池 そのうちに長いのも書いてみようかな、と?
又吉 そうですね。小説を書く必然性があると思えるだけの理屈を与えてもらって、それが積み重なった結果、書かずにはいられないという状態になればと思っていました。ちょうどそういう気持ちになりつつあったときに西加奈子さんの『サラバ!』を読んで、自分もここに描かれているように、自分のことを自分で決めたいと考え、小説を書きたいと思ったんです。
だからそれまでは読者はお金払って読んでくれるんやから、ちゃんと読むに耐え得るものにしたいって気持ちだけで書いてました。芸人として、舞台を見にきてくれた人を楽しませたいといつも考えているのと同じでしたね。
小池 そこから純文学の方に行ったあたりで、書くことの意識にまた変化があったわけですね。
又吉 そうでしたね。それ以降はもっと小説とは何かを掘り下げて書こうと思うようになったというか。小池さんはどうして小説を書いてみようと思ったんですか?
小池 じつは僕も二〇代の頃は小説を書きたいとは全く思っていませんでした。ただ、近しい人を亡くした直後に、本をたくさん読んだんです。大学の卒業論文でも、僕と同じように親しい人を喪う経験をした人たちが書いた作品をいくつか取り上げて論じました。小説だけじゃなく、亡くなった人との思い出を綴ったエッセイや、精神科医が仕事を通じて見聞きしたものを掘り下げていくノンフィクションまで、さまざまな作品を読んで喪失に対する向き合い方にはいろいろな方法があることを知りました。
だからといって、すぐに小説を自分で書こうとは思いませんでした。死や別れはいくら考えても理解しえないものなわけで、それを小説に書くことは自分にはできないと思ってましたし、今の自分が書いたら感情的に崩れたものになってしまうだろうと感じてもいました。けれどその後、それなりに明るく働いたり、誰かと遊んだりして普通に生活するなかで、何か違う時間を心のどこかで求めていたんだと思います。卒業論文から八年くらい経って、小説を書いてみようと思い立ちました。とはいえ、最初の作品に「わからないままで」というタイトルをつけるくらいなので、小説を書くことで喪失を解き明かせたという感じはもちろんありません。答えを出すというよりも、ただそばにいたいという感覚で小説を書いているような気がします。
わからないままでいるための筋力
又吉 必ずしも答えを小説のなかに提示する必要ってないんやと僕は思います。もちろん答えを確定させることの覚悟や潔さも大事やとは思うんですけど、時間が経ったり状況が変わったりすれば答えなんてまた違うものになるじゃないですか。それよりも僕はわからないという状態のまま理解することの方が意味があるんじゃないかと感じるんです。
わかってない状態で考え抜くっていうのはじつは一番筋力を使うんですよね。だからこそ、なるべくその筋力を使い続けていたいですね。何でも答えを知ってますみたいな人って世の中にたくさんいるじゃないですか。そういう人としゃべってても、あなたはトンネルの途中の非常口から抜け出ただけでしょって思ってしまう。わからないままもっと先に行ける可能性があるのに、なんかもったいないなって。僕が近代文学や純文学と呼ばれる小説を中学時代に読み始めたときも、その感覚が一番好きでしたね。想像力が豊かで、論理的に言葉を尽くして考える力を誰よりも持っている人たちがわからないことに悩んで苦しんでる姿がすごく信頼できたっていうか。
小池 小説は一文字一文字書いていくので、時間がとてもかかるものなんですよね。ある意味で、わからない状態を自分のなかでずっと持続させる装置でもあると思うんです。早急に答えを出すのでもなく、考えることを放り出すわけでもなく、そこにとどまり続ける。小説を書くというのはそういう経験なんだというのは一作目を書き終えたときに感じましたし、今回も書きながらそのことを実感していました。
又吉 『あのころの僕は』の中で、「ゾウのおばあちゃん」って天が呼んでる母方の祖母に「いつかきっと、いろんなことがわかるようになる」と言われますよね。あそこを読んで、めっちゃわかるなぁと思いました。天はそのときは意味を完全に摑みきれてないようなんですが、でも、きっとあの言葉を言ってもらって心強かったはずです。
小池 冒頭にもその言葉を出して、後半でそれがゾウのおばあちゃんの言葉だったことがわかるようにしたのですが、最初に書いたときは自分でもどういう意味を持つ言葉なのかわかっていませんでした。わからないまま、子どもの視点を通して見えてくるものを書き続けていくうちになんとなく理解できたんです。言葉がだんだん意味を持ってきたというのは初めての感触でした。
又吉 それが小池さんの小説の魅力的なところですよね。小池さんが書く文章は意味の広がりがあるんですよ。ディテールはもちろんしっかり書かれているんですけど、言葉を狭いところに閉じ込めていないというか。言葉ってみんなが使うものなので、ある程度、曖昧に設定されているじゃないですか。それなのに僕たちは無理に言葉にいろんなことを委ねるから、本質とずれてしまうんです。でも、小池さんが書く言葉には余白があるから、語義が広がる可能性もある。だからこそ、ほんとうのことへと近づくことができるんだと思います。