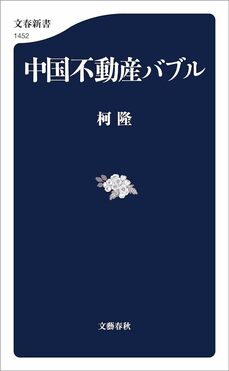中国のデフレはどうなる?
2023年末現在、習政権は金融緩和政策をもって不動産バブルの崩壊を食い止めようとしているように見える。しかし、年末に開かれた共産党中央経済工作会議で習主席が行った演説をみるかぎり、具体策は打ち出されていない。
現状において不動産デベロッパーを救済する融資を実施しても、問題の解決を先送りするだけである。重要なのは構造改革だ。
日本の場合は、バブル崩壊の後処理を行うのに30年かかった。はたして中国は何年かかるのだろうか。現段階では断定することはできないが、日本経済を取り巻く外部環境と中国経済を取り巻く外部環境を比較すると、両者の立場は大きく異なると言える。
日本のデフレは30年間続いたが、輸出製造業は順調に日本経済を支えていた。それに対して、中国には米中対立とサプライチェーンの再編という壁が立ちはだかる。習政権は目の前の状況の深刻さを十分に理解しておらず、国内循環、すなわち、自力更生で経済成長を実現しようとしているようだ。
しかし、中国の経済構造は輸出依存であり、内需だけで成長を持続させるのはそもそも無理なことである。
最近、中国国家統計局報道官の記者会見を聞いていると、都合の悪い経済統計を言葉で粉飾しようとする傾向が強くなっている。具体的な経済統計をいわずに、経済が改善に向かっているというように言葉を濁す場面が多い。
実際のところ、不動産バブルは崩壊して、経済が回復する力は弱くなっているはずだ。国家統計局が正しい統計を発表しなければ、ポリシーメーカーは正しい政策を考案する根拠をもてない。このままいくと、中国は失われた20年ないし30年を喫する可能性が高くなる。
写真/shutterstock