小説家を親に持つと子どもは苦労する?
阿川 玉青ちゃんは、お母さまのことは『身がわり』というエッセイで書いていますよね。
有吉 はい。私が20歳のとき、ちょうどイギリス留学中に母が53歳で亡くなって、突然のことだったので、何だかよくわからないまま、日が過ぎていったという感じでした。それから4~5年たって、やっと母のことを書くことができたんですね。
阿川 24~25歳で、あれだけのことを書いたのか。すごいわ。お母さまは、家ではどんな感じだったんですか。
有吉 母は料理をしたり、掃除をしたりっていうことは一切なくて、本当に書くことだけでした。家のことはお手伝いさんがやって、祖母が秘書的な役割をしていましたね。私の面倒も普段は祖母が見ていて、時間があるときだけ、ワーッと過剰に愛を注いでくるので、子どもとしては迷惑で。いつも仕事をしていましたけれど、「書けない」と悩んでいるのは、見たことがなかったです。
阿川 それは父も言ってました。吉行淳之介さんと二人で、「もう何も書くことがない」「絞っても水一滴でない」と話していたら、お母さまが「お兄ちゃんたち、何言ってんの? 私なんか絞れば絞るほど、ジュージュー、ジュージュー出てくるわ」っておっしゃったらしくて、「有吉はすごいな。絞っても絞ってもまだ書くことが出てくるらしい」って父が感心していたのを覚えています。
有吉 母がそんなことを……。亡くなって30年以上たちますけれど、あらためて思うのは、作家の家は何でもありってことですね。生前は、母への不満もありましたが、あれぐらいでないと小説は書けなかったのだ、と今は思います。だから、阿川さんの『強父論』を読んでも全然驚かなかった(笑)。
阿川 そうでしょ。作家の子どもが集まると、決まって、「うちはひどかった」「いや。うちはもっとひどかった」という話になるものね。私の場合、父のためを思って何かやっても、いつもそれを裏返されるんですね。まだ父が元気だった頃、父と母を京都に連れていったことがあったんです。以前、私が取材で、とてもおいしい料理を食べたので、両親に食べさせたいと思って、「私がおごるから」って3人で行ったんです。
有吉 親孝行ですね。
阿川 そうしたら、帰りの新幹線で、「高山寺に行けたのは良かったよ。高山寺に行けたのは良かった」って何度も繰り返すの。ひどくない??(笑)「阿川さん、報われませんね」って秘書にも言われたわ(笑)。
有吉 でもそれは、お父さまが照れてらしたんじゃないですか。照れがあるから、いつも「佐和子ー!」って叱りつけていたとか?
阿川 照れもあるけれど、やっぱり父は自分の理想の娘像っていうのをもっていたと思うの。たとえば「おいっ、日本酒つけてくれ」って父に言われたとき、「はい」って口では言いながら、内心『試験で忙しいのに』とか思うでしょ。そうすると父はそれを敏感に察知して、「なんだ、今のため息は!?」って怒り出すのよ。「あ、お父さま、お酌いたしましょう」みたいな娘を望んでいたのに、私が全然違うから、癪にさわったんだと思うのよね。
父が亡くなったあと、いろいろな方に言われました。「私も父とうまくいってなくて、死んだ直後は涙も出なかったけれど、しばらくときがたつと、突然ダーッと滂沱のような涙があふれてきた」って。悲しみはじわじわくるんだと。でも、7年たつけど、全然来ないのよ(笑)。夢の中でも相変わらず父は不機嫌で、私は怯えていて、いまだに父を恐れてる。本当に不幸な娘です(笑)。
有吉 そういえば、阿川さんは、最初の頃は、お父さまに文章指導をしていただいていたんですよね。羨ましいなと思いつつ、私だったら見せなかったかもしれないと。親に読まれるのは嫌じゃないですか。
阿川 嫌ですよ。本当に嫌でしたよ。でも、阿川弘之の娘がこんな日本語を使っていると思われたら体裁が悪いということなんでしょうね。
私が最初にエッセイを書いたとき、原稿を編集部に届けようと支度をしていたら、父が「すぐに編集部の人に30分遅れると電話しなさい」「書斎から鉛筆とメガネを持ってきなさい」って。キター!!って感じですよ(笑)。それで私の原稿を読み始めて、「まず名前の位置が悪い」って。
有吉 そこからですか(笑)。
阿川 それからダメ出しの嵐です。「だった、だった、だった、と同じ語尾が3回続く。安機関銃じゃあるまいし」とか、「こういう形容詞を身内に使うべきでない」とか、徹底的に直されて。ただ、内容については、何も言われなかったんですね。「父にこんなひどい目にあった」っていう悪口をもっぱら書いていましたけれど、それに関しては、怒られなかった。そこはさすがに物書きだなと思いました。
有吉 いろいろ口を出しつつ、娘が同じ仕事をするようになって喜んでいらしたんじゃないでしょうか。
阿川 確かに、私が物書きになったことは、喜んでました。「どれほど、俺が苦労して、おまえたちを育てたか、やっとわかったか」「書くことはこんなに大変なんだ、ざまあみろ」って感じではあったけど(笑)、書くようになって、父との会話が増えたっていうのはありますね
有吉 それは羨ましいですね。
阿川 玉青ちゃんが書くようになったと知ったら、お母さまはそれはもうお喜びになったと思いますよ。
有吉 どうかなあ。母は、作家の方が亡くなって、お子さんが何か書いたのを見ると、「私が死んでも恥ずかしいから書かないでね」って言ってたんですよ。
阿川 ウチもそうですよ。でも、出版社というところは、作家がいてそこに娘がいると原稿を依頼するものなんですよ(笑)。やっぱり父親と娘の関係って、どこかミステリアスなところがあるように思われているから、書けるか書けないかわからないけれど、とりあえず依頼する(笑)。娘は、それで鍛錬されて、書き続けることになるんだと思うの。玉青ちゃんは作家になって良かったと思いますか。
有吉 自分が書くようになって、初めて母のことがわかったような気がしますから、良かったと思います。母は多忙で、根を詰めて仕事をしていたので、それで早く死んだと思っていましたけれど、今はその逆のことを思うんですね。母は、体が弱くて、とても20歳まで生きられないと言われていたらしいのですが、実際は、倍以上生きました。それは書いていたからだと。書きたいから、書くのが楽しかったから生きられたんじゃないかって。母には到底及びませんが、自分がやってみて、そんなふうに思うようになりました。
阿川 優秀な子だねぇ。最後にまた小説のことで、ひとつ確認。ジンさんが、お寿司を吸い込むように食べるシーンがすごく印象的で。あれは事実?
有吉 あれもフィクョンです(笑)。お寿司をとてもおいしそうに食べる友人がいて。
阿川 そうなのねぇ。あの描写はよかった(笑)。小説に出てくるジンさんは、今まで玉青ちゃんが出会ったいい男たちの集合体ってことですね(笑)。
「小説すばる」2022年6月号転載
関連書籍
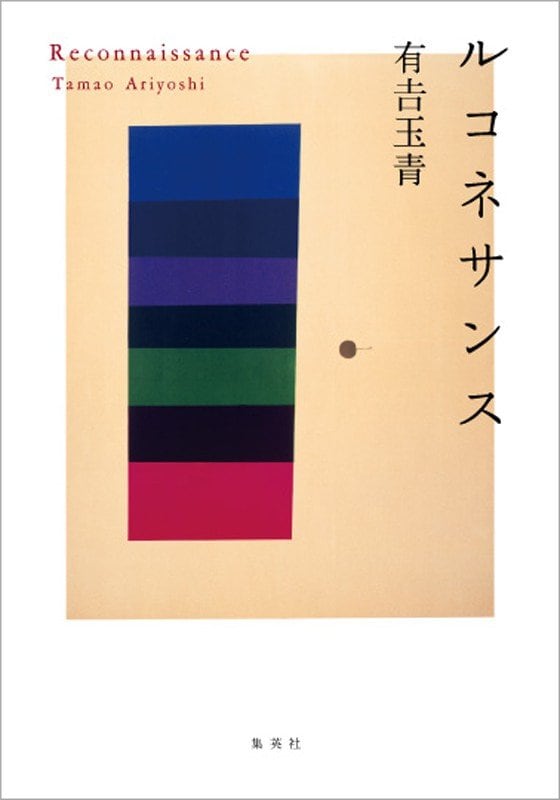
著者:有吉 玉青
集英社
定価:本体1,850円+税

























