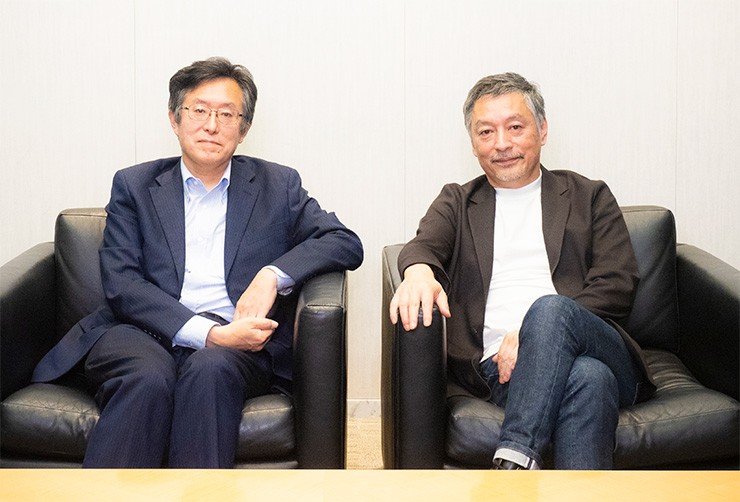日本人の目を通して描く、
不思議なソ連・ロシア社会の空気感
東西冷戦下、ソ連から発信される日本向けラジオ放送「モスクワ放送」で働いた日本人たちがいた。彼らが見たものとは――
第21回開高健ノンフィクション賞を受賞した『МОСТ』刊行を機に、著者の青島顕氏と作家の島田雅彦氏に、「閉ざされた」国とどう付き合うかをテーマに語っていただいた。МОСТとはロシア語で「橋」「架け橋」を意味する。「なぜ?」をきっかけに、隣国の人々への理解につながれば――そんな思いも込めて企画された本対談。まずは青島氏に執筆動機から伺った。
構成=朝山 実/撮影=chihiro.
青島 初めに『МОСТ』が生まれた背景なのですが、2022年にロシアによるウクライナへの侵攻が始まり、ロシアについて何か書けないかと考えました。そこで1980年代から「モスクワ放送」でアナウンサーをしていた日向寺康雄さんの消息を知り、「日本語放送80周年」ということも重なり取材をし、のめり込んでいってしまったわけでして。
今回、島田さんに対談をお願いしたのは、高校生の時に読んだ『亡命旅行者は叫び呟く』(生活に飽いた公務員キトーがソ連を一人旅する中編小説)が印象深かったんですね。60年代生まれの作家が出てきたのが嬉しかったし、そうか、ソ連へは横浜からナホトカ経由で行くんだとか、モスクワは中心から少し離れるだけで、もうスカスカな街なんだとか思ったのをよく覚えています。
島田 当時の社会主義はパラレルワールドというか、たとえば商店を覗いても看板に「野菜」とだけ書いてあって。
青島 「オーバシ(овощи)」と。
島田 石鹼を買おうとしてもハダカで置いてある。ああ、これが唯物主義かと思いました。それでまた買い方も面倒くさいんですよ。レジでお金を払い、レシートをもらって商品を交換しに行く。それくらい商品がない。しかも外貨でないと買えないものが多かった。さらに予告なしに路上で果物を売り始めたりする。
青島 だから外出する際はみんな、網の買い物バッグを持って出かけていた。
島田 ひょっとしたら袋。
青島 日向寺さんは当時、お世話をしていた往年の大女優の岡田嘉子さんから「緑のものでもいいからバナナを買ってきて」なんて気軽に頼まれ、苦労したと話されてましたね。
島田 そういうローテク社会の国がどうやってロケットを飛ばせたのか。そこがもう不思議でしようがない。博物館に行くと、宇宙ステーションの残骸が展示されているんですけど、トランジスタでなくて真空管ですから。
青島 TBSの記者時代にミール(ソビエトの宇宙ステーション)に滞在したことのある秋山(豊寛)さんは、「意外とコッチのほうが安全性は高いんだ」と言っていて、ホンマかいなと思いましたけど。
島田 初期の国際宇宙ステーションが面白いのは、物量作戦のアメリカに対して、ロシアは物がない中でやりくりしていて。アメリカの飛行士がオシッコを捨てようとしたら「おいおい」と慌てるんです。
青島 使えるじゃないかと。
島田 そう。濾過するのか、冷却水にするのか知らないけど。貴重な資源をなんで放出するんだという。
青島 スゴイ話ですね。
島田 もっと面白いのは、ニッチな空間が設けてあって、そこへ頭を突っ込む。プライバシー・スペースがあるんですね。
青島 やはり一人にならないともたないんでしょうねえ。
島田 すべて考え尽くして設計してあるんでしょうね。いきなり話がそれちゃったけど。
世間の「ソ連嫌い」に逆張り
青島 モスクワ放送を聞かれたことは?
島田 もちろんありますよ。(東京外国語大学)ロシア語学科の友人に外国の放送を聞くのが好きなやつがいて。微妙な周波数の調節までできるラジオが流行っていて、中国語学科の人間は、北京からの放送を聞いて毛沢東主義になったりしてました。
青島 モスクワ放送は教条主義的だったのに対して、北京放送は日本人を取り込むのが巧かったと言われますよね。
島田 文化大革命の時代には、紅衛兵のファナティック(狂信的)な主張を当時の若者は面白がっていた。時期として60年代末から70年代初め、アメリカのカウンターカルチャーと重なる。
青島 日本人が社会主義に幻滅する前夜ですね。
島田 まだ憧れの意識を持ち、ラジオを聞いていた人たちはいたんですね。ただ、私の学生時代にはソルジェニーツィン・ショック(68年に『ガン病棟』などを発表し70年にノーベル文学賞を受賞したが、74年に国外追放された)があり、CIAがソ連の反体制知識人をアメリカに亡命させて反ソキャンペーンに利用しようとしていた。日本国内でも反ソ的な風潮が高まり、学生運動も下火になっていました。
青島 私の子供時代には「ソ連嫌い」が定着していましたが、その頃に先生は東京外大のロシア語学科に入られるんですよね。映画『時計じかけのオレンジ』を観てというのを何かで読んだ記憶がありますが、世間のソ連嫌いに逆張りしてやろうということもあったんですか?
島田 冷戦時代をナイーブに受け止めていたんだと思うんですね、私自身は。周囲を見ると声変わりしたての声でビートルズだのをコピーし、リーバイスに憧れ、お年玉でフォークギターを買う。それがみっともなく見えて、大嫌いだった。一方、ロシアとの接点があったかというと、小学生のときに「大シベリア博」でマンモスの剝製を見た程度だけど。
青島 ソ連に行かれたのは81年?
島田 そう。モスクワオリンピックの翌年に語学研修ツアーで1か月ほど滞在したんです。それが初めての外国。大学に入って最初の2年間はロシア語漬けで、少し話せるようになると実地で使いたくなるんですよね。飛行機に乗るのも初めて。ハバロフスクからモスクワへ、アエロフロートで。
青島 そうなんですね。今回の取材では同じ経路で行った人の話を書きました。
島田 『МОСТ』に登場するキーパーソンたちのエピソードは非常に懐かしく読みました。放送局で働く日本人の方々は「外国人」で、「疑わしい人物」としてアウェイな立場にいたわけですよね。ただ、個人的に友人になるとロシア人なりの情がある。それがあって異国で暮らせたというのが伝わってきました。
青島 ありがとうございます。アナウンサーの日向寺さんはモスクワの人たちの情にひかれて、30年働いたと話してました。私自身も短いながらホームステイでモスクワの個人宅に滞在し、彼らの温かさを感じたことがあって、日向寺さんの言葉が不自然だとは思いませんでした。
―― 70年代に20代で日本からモスクワ放送に行かれた人の話を読むと「自分探し」をされていた傾向もありますよね。
青島 あると思います。
島田 70年代は、若者は金がなくてバックパッカーの時代ですよね。
青島 73年にモスクワ放送で働き始めたアナウンサーの西野肇さんに、なぜソ連に行ったのかを聞いてみたんです。テレビ局志望で大学を卒業するとき北海道の民放局から内定をもらえたけれど、将来、道内のどこかの支局にいる自分を考えると耐えられなくて辞退した。それで東京の民放テレビ局でバイトをしていたときに、モスクワ放送から人を派遣してほしいという話があり、「誰でも行けるわけではないから」と決意したんだという。
島田 戦後はロシアからエネルギー資源を輸入したり、逆にブルドーザーを輸出したりする日本企業に先輩や同級生が就職し、モスクワ駐在員になる。それで長期滞在するうちに現地で奥さんをもらった人たちが日ロのパイプ役を果たしていたところはあるでしょうね。
青島 取材した人たちの中にも、そうやって日本にとって不思議な世界のソ連・ロシア社会に溶け込んでいかれた方がいました。歌手の川村かおり(芸名・川村カオリ)さんのお父さんの秀さんは専門商社の駐在員でしたが、泊まっていたホテルの従業員の娘さんと結婚してかおりさんが生まれ、あの国と深い関係になりました。