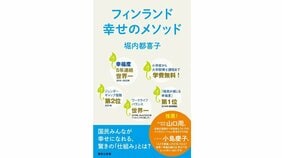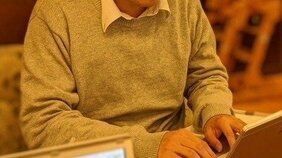整列、行進、身だしなみ
このような私たちのからだにかかわる規律は、体育の授業において、ほかにも多く見ることができます。たとえば、授業の始まりや終わりの際に行われる整列と挨拶があります。この整列がイヤだったという人も、少なからずいると思います。
少し列から外れていたり、よそ見をしていたりすると、すかさず先生の指導が飛んできます。また、挨拶を大きな声でしなければ、何度もやり直しをさせられ、「これ、何か意味あるのかな?」と疑問に思った人もいることでしょう(私もその一人です)。
さらに、運動会などのために、体育の授業で行進の練習をすることもあります。これも、前後左右の間隔や手と足の細かい動きなど、クラスや学年のみんながそろうまで、繰り返しやらされた人もいるかもしれません。「こんな軍隊みたいなことを、なんでやらなきゃいけないの?」という不満は、今でも大学生からよく聞かれます。
これらのほかにも、体育の授業における服装に関するルールも、規律の現れと言えます。体育着(体操服)の裾がズボンから出ていたり、腰パン(死語?)をしていたりすれば、指導の対象となるはずです。また、少し前までは、冬でも半袖と半ズボンで体育の授業を受けるのが当たり前でした(先生は暖かそうなジャージを着ているのに……)。
最近では、長袖のシャツやジャージを着用できるところも増えてきたようですが、それでもやはり、その「着方=身だしなみ」は指導の対象となっているわけです。この点については、体育着よりも、むしろ学校の制服の方に、規律の問題が顕著に現れていると言えます。
以上の例はすべて、体育座りと同じように、みなさんのからだをコントロールすることです。そこでは、列を乱したり体育着を着崩したりすることが、授業の規律を乱すこととして捉えられています。つまり、体育の授業において、みなさんを集団としてコントロールするためには、座り方から並び方、声の出し方から体育着の着方まで、みなさんのからだを徹底的に画一化することが必要だと考えられているわけです。
もちろん、そのようなからだのコントロールが、ある面では必要なことも確かです。たとえば、小学校一年生が遠足に行くときに、学校の外ではしっかりと列を作って歩いたり、静かに並んで座っていたりすることは、安全の面からも、またマナーの面からも大切なことです。
そのような場合、先生の注意がしっかりと伝わらないことは、致命的な問題になり得ます。付言すると、日本が地震などの自然災害の多い国であり、避難のスムーズさが重要であるという特殊な事情も、体育を含む学校教育において、これほどまでに規律が重視されてきたことと無関係ではないように思います。
とはいえ、そのような体育授業における規律の強制には、当然、反発が生まれます。ここまでの話を踏まえると、むしろ「体育ぎらい」とは、体育授業における規律の強制に反発しているのだと言えるかもしれません。
その反発は、頭で考えてというよりも、むしろ感覚的に、からだのレベルで起きています。このことは同時に、「体育ぎらい」が豊かな感性を持っていることを示唆しています。なぜなら、さまざまな規律の強制に何も違和感を抱かない人は、権力に従順な感性を身につけていると考えられるからです。
このように考えると、「体育ぎらい」が必ずしも悪いとは言えない可能性が見えてきます。なお、この感性の問題については、本章の最後に再び触れたいと思います。
写真/shutterstock