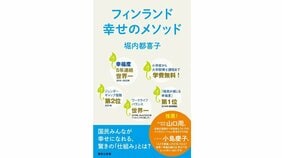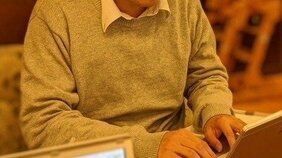「体育座り」のイロイロ
さらに具体的な例を挙げてみます。それは、「失礼シマース」とセットで行われている、いわゆる「体育座り」です。
体育座りと聞いて、すぐにイメージできる人と、「あれのコトかな?」と少し確認を要する人がいると思います。それもそのはずで、地域や学校によっては、同じ座り方のことを「三角座り」や「体操座り」と呼んでいますし、また幼稚園や保育園では「お山座り」と呼んでいるところもあるようです。このように同じ座り方でも、その呼び方にはイロイロあるわけです。本書では、「体育座り」と呼びたいと思います。
なぜここで体育座りに触れたかというと、これまでに、それを巡ってさまざまな議論がなされてきたからです。つまり、この体育座りは、「たかが一つの座り方」と侮ることのできない意味を持っているということです。
たとえば最近では、腰や内臓に負担がかかるため、体育座りは健康によくないという話が聞かれます。確かに、両腕で両足を抱えて、からだをあれだけ丸めていると、いろいろなところに負担がかかりそうです。ただし、一方では、体育座りをすることによって安心や落ち着きを感じることのできる人も、少なからずいるようです。
ここで考えてみたいことは、「だから体育座りは禁止すべき」という主張ではなく、むしろ、その背景にある問題です。それは、体育の授業において体育座りを児童生徒に強制することに関する問題です。一気に、「体育ぎらい」に関係しそうな感じになってきました!

規律としての体育座り
体育座りは、そもそも学校において、集団行動の一つとして始まったものです。つまり、大勢いる児童生徒を、先生たちがコントロールするための方法だったわけです。もちろん、これが必要な場面もあります。
たとえば、小学校で大勢の児童が校庭に並んで座り、校長先生の話を聞くことがあります。集会や学校行事の開会式などがそうですね。そのようなとき、小さな子どもは、当たり前ですが、すぐに飽きてしまいます。そして何が始まるのかというと、そうです、砂いじり(砂遊び)です。足やお尻のあたりの地面に、丸や線を描いてみたりするわけです。さらに、それでも話が終わらないと、小さな砂粒を拾い上げて、前に座っている友達に指で飛ばしたりし始めます。みなさんにも、このような経験があるかもしれません(私だけ?)。
同じ場面で、今度は目線を先生の立場に移してみましょう。先生としては、もちろん子どもたちに話を聞いてほしいわけですが、一方で、まだ成長段階の子どもの集中力が長くは続かないことも理解しています。
また、砂いじりをしている子全員を、いちいち注意するのも大変です。そして、ひらめいたわけです。足を両手で抱えて、その両手を自分でつないでいてくれれば、砂遊びできないじゃん!と。もうお気づきですね。そうです、まさにその姿勢が体育座りなのです。
ちょっと簡略化しすぎた気もしますが、体育座りが必要とされる状況は、少なくとも実践的にはこのように考えることができます。ここで重要なことは、体育座りがみなさんのからだをコントロールする技術として用いられているということです。
少し言い換えると、体育座りは、みなさんのからだの自由を縛るもの、すなわち、一つの「規律」として生み出され、機能しているということです。どうやらここに、体育座りと「体育ぎらい」の一つの接点がありそうです。