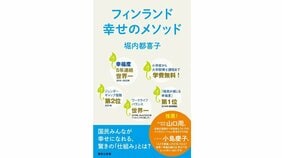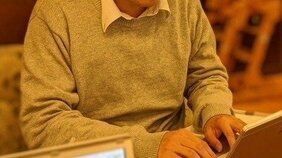ユルい先生が「体育ぎらい」を生む?
すでに「体育ぎらい」の人にとっては、「ユルい」体育の先生は確かに「無害」な存在になり得ます。しかしそれは裏を返すと、まだ「体育ぎらい」になっていない人、つまり、体育が好き、もしくは、好きでも嫌いでもない人にとっては、「無害」ではない可能性があるということです。
たとえば、運動が得意というわけではないけれど、運動したりスポーツしたりするのは別にイヤじゃない、という人がいたとします。その人はもしかすると、もう少し運動をすることで、上達することに喜びを感じることができるかもしれませんし、友達と一緒に動いたりスポーツしたりすることが楽しくなるかもしれません。しかし、そのような人にとって、上述の「ユルい」先生は、その期待や可能性に応えてはくれません(だって、居眠りしたりしているわけですから……)。
つまり、「ユルい」先生は、まだ「体育が嫌い」ではない人にとっては、体育を好きになる可能性を摘み取る存在になり得るということです。なぜなら、そのような「好きでも嫌いでもない人」は、まだ運動やスポーツの面白さや楽しさに触れる経験をしていないだけかもしれず、そのため、そのような経験を体育の授業ですることができれば、少なくとも「体育ぎらい」にはならないで済む可能性が十分にあるからです。
重要なことは、そのような好きでも嫌いでもない人が、現実には多くいるということです。「はじめに」で述べた「あいだ」の話を思い出してください。たとえばそこには、体育の授業をはじめて受ける人のほとんど全員が当てはまります。この日本で毎年どれだけの子どもたちが、はじめて体育の授業を受けるのかを想像してみると、この「あいだ」にいる人が、実際はかなりの人数にのぼることがわかるはずです。そして、それは同時に、「体育ぎらい」の予備軍でもあるわけです。
さらに言うと、そのような「ユルい」先生は、「好きでも嫌いでもない人」だけでなく、むしろ「体育が好き」な人にとっても、その「好き」という感情を損ねる存在になり得ます。すでに「体育が好き」な人のなかには、さらに運動やスポーツに取り組み、もっともっと上達し、その楽しさを味わいたいと思っている人が少なからずいます。そのような人にとって、授業丸投げで居眠りなどをしている「ユルい」先生は、少なくともその興味や関心を高めてくれる存在ではありません。
それゆえ、「ユルい」体育の先生は、まだ体育が好きでも嫌いでもない人と、すでに「体育が好き」な人のいずれをも、「体育ぎらい」にしてしまう可能性があると言えます。これはこれで、「体育ぎらい」にかかわる大きな問題です。
ちなみに、そのような「ユルい」先生に対して私がいつも感じることは、むしろ、そのような先生たちこそ「体育ぎらい」なのではないか、という疑問です。その意味では、そのような「ユルい」先生たちも、本書のターゲットなのです(読んでくれるかな……)。
写真/shutterstock