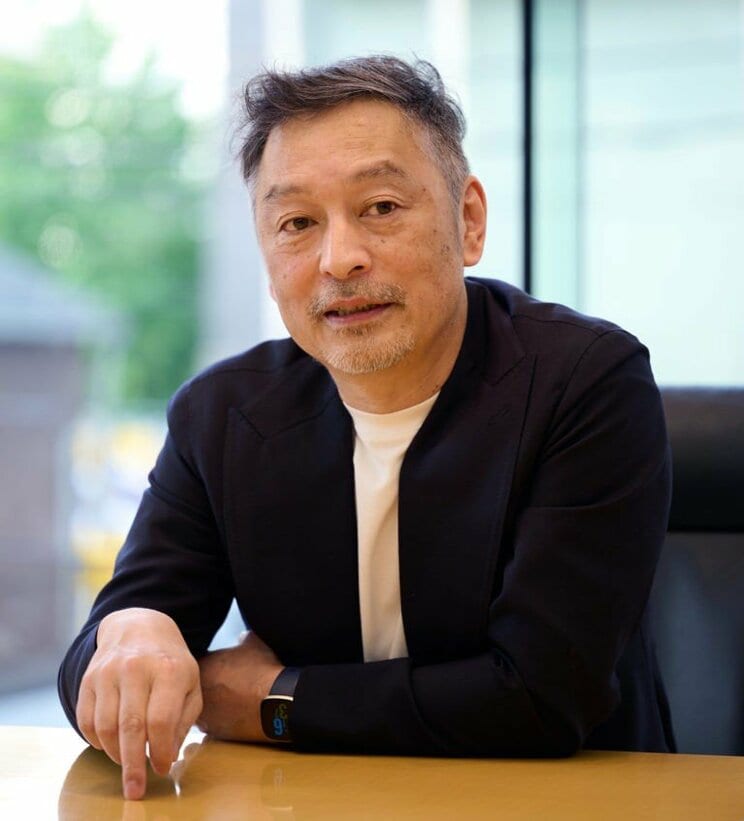
父であり、同時に異端であること
――お子さんを持つ親として、あるいは社会を観察する義務を負う小説家として、お二人は父性が今、大きな変容を迫られていると実感しますか?
金原 そうですね。島田さんがおっしゃるように父権的なものはもはや完全に通用しない時代になっていると思いますし、最近の若い男性はオイディプス的なものには一切囚われていないようにも感じます。男性が子どもにどう関わるかということに関して言えば、一つの過渡期を迎えているのではないかと思います。男性の育児参加や育休取得も一昔前に比べたらかなり増えましたし。、身を粉にして働き、家庭を顧みない男性は今ではもはや害悪扱いです。家庭内でも社会でも評価基順が変わってきたので、そのなかで父性が新たなフェーズを迎えたというのは、実感としてわかります。
島田 だいたい、父親というのは「ええかっこしい」なんですよ。自分に不都合な真実を隠したりして、メンツとかいう犬もくわないものを後生大事に守る癖がある。父権の復活を主張する奴ほど、過去の悪事や失敗を隠して、自己栄光化の言説ばかりを積み上げる。
それぞれの領域で責任のある立場の男たちが自分のやってきたことを赤裸々に告白したら、居場所を失うかもしれない。だから正直な告白は勇気のいる行為なんです。でも、僕はそれができる父親こそが正しいのだと言いたかったし、自伝的小説という体裁をとったのは虚飾に覆われた父性を素っ裸にするのに私小説こそが効果があると思ったからでした。『君が異端だった頃』を、僕は自分のことを「君」という二人称で書いたわけですが、今作で「私」という一人称にしたのはそこに理由があります。一人称の「私」で過去のことを書くと、自然と懺悔録になりますしね。お前の父親はこんなに恥多き人生を送ってきましたよ、と。
金原 でもこの作品で島田さんが懺悔をしているかというと、どうでしょう(笑)。むしろ、この作品には島田さんの父としての、そして作家としての自信が満ち溢れているように感じます。俺は間違ってないんだ、という強い主張も。
島田 正しいことをやる癖がついてしまったので。もちろん書けることと書けないことはありますからね。前作の『君が異端だった頃』で書いたエピソードは三〇年を経過して、時効だったから書けたものばかりでしたし。公文書も私文書も秘密保持期間の目安が三〇年に設定されています。三〇年経ったら、どんな秘密文書も原則公開される。例えば、アメリカの公文書を保存する議会図書館には門外不出とされる極秘資料が多数保管されています。でも、それらだって時効が来れば、次々とオープンにされるわけですよね。だから、三〇年以上前のことに関しては遠慮なく公開していいと僕は考えました。一方、今回の作品では、それに続く自分の人生の三〇年分を書いたから、今の理屈で言えば時効がまだ来ていないことになる。公開することで迷惑を被る人たちがいっぱいいるわけなので、そこは遠慮が働きました。
金原 ミロクくんに関する部分はご本人の許可を得たんですか?
島田 一応、息子のプライバシーに関することも書いてますから、本人の許可をもらっています。それに彼の留学中のことはよくわからないので、本人にインタビューしていますしね。
金原 身内のことを書くのはセンシティヴな問題でもあるので、大事なコンセンサスですね。さっき、島田さんの父としての絶対的な正しさが書かれていると言いましたが、私がこの作品を読んで驚かされたのは、ここに書かれている一貫した信念や思想の強さなんです。『君が異端だった頃』と併せて読むと、それは特に強く感じます。よくぞ、ここまで折れないものを持ち続けてきたなって。
島田 痩せ我慢みたいな部分もあります(笑)。ただ、一貫した信念を感じていただけたのなら、それは「異端」である自分をずっと見つめて書くことができたからかもしれません。そもそも『君が異端だった頃』は青春時代から作家になるまでを書いているから、いかにして僕が異端としての物書きになったか、その遍歴を中心にすればよかった。でも『時々、慈父になる。』は、そんな小説家としての「私」に加えて、父としての「私」という二つの観点で書く必要がありました。ここがおそらく金原さんと共通する部分だと思う。金原さんの作品も、母と小説家という二つの視点が非常にスピーディーに交代しながら自己像を打ち出しているところに、その魅力があります。
では小説家としての「自分」とは何か。僕はあくまでも物書きは異端でなければいけないと思っているし、小説家はエキセントリックなことをやる義務があると考えています。三月に亡くなった大江健三郎さんからも「島田さん、そういうものなんです」と直接指導されたことを強烈に覚えています。私小説を書いてきた近代の作家たちも自分の頭脳と身体を実験台にして小説を書いてきました。さまざまな生活のトライアルを経験し、その上に愚行を重ね、その記録を綴ってきた。その結果、心を病んだり、身体上の病気になったりしたわけで、日本の文士の無頼的なイメージはそこから作り上げられました。だから彼らの小説は異端だった彼らの生き方の記録になっています。それを読むと、僕なんかは大変助かる。前例があってよかった、みたいに思えるというか(笑)。
金原 なるほど(笑)。先人たちに倣っているわけですね。
島田 金原さんだって相当、身体を張って書いてるよね。
金原 いや、そんなことないですよ。そんな身を削るような書き方はしてないです(笑)。やむにやまれず安定をぶち壊さざるを得ないことは何度もありましたが、基本的に私は生活に関しては非常に保守的な人間だと思っています。あまりはちゃめちゃな生活はしないですし。でも、それは私だけの問題ではないと思う。最近の作家は、島田さんがおっしゃったような破滅的な生活を送っている人も少ないですし、スタンスがだいぶ変化していると感じますね。無頼タイプの作家はめっきり少なくなりました。
島田 うん、それは僕も感じます。昭和、あるいは平成の前半ぐらいの作家たちのような野蛮さはなくなった。
金原 『君が異端だった頃』を読むと、中上健次がどれだけ荒れていたかがわかりますね。こんな人が文壇にいたのか……と。今だったら告発、いや普通に逮捕されてもおかしくないエピソードばかりで、そういう意味でもあの作品が貴重な記録であることは間違いありません。
島田 そうなんですよ。なんでこんな危ない奴が放し飼いだったんだ……って思ってしまいますよね(笑)。大江さんだってそうですよ。ノーベル文学賞を受賞して以後の大江さんのパブリックイメージは紳士的な人という感じかもしれないけど、あれはあくまでオフィシャルな顔であって、大江健三郎という人間のごく一部です。若い頃の野蛮さといったら、それはもうすごかった。
金原 そういう昔の作家たちの野蛮さを聞くと、私がどれだけ普通の人間なのかが思い知らされます。普通過ぎて異端なのかもしれません(笑)。
異端は現在可能なのか
――大江健三郎など旧世代の小説家が体現していた異端としての小説家の像が変化しているというお話でした。では、現在、小説家はどうあらねばならないのか。そのあたりをお話しいただきたいのですが、異端とはそもそもどういうことなのでしょうか。英語で言う、アウトサイダーのような存在だと考えて良いでしょうか?
島田 「アウトサイダー」でもいいし、「ヘレティック」でもいい。「異端」という言葉の出どころは大岡昇平あたりにあると思ってください。彼が『野火』を書いた頃、自分を世界文学のコンテクストにおいて、その異端ぶりに気づいたと言います。つまり、ずっとフランス文学を研究してきた彼は、日本語で小説を書く非キリスト教徒の小説家は、ヨーロッパの文学から見れば異端だと受け取られるだろうし、それをこそ目指すべきだと考えたわけです。小説家とは異端であるべきだという考えはそこに原点があるんです。
金原 ただ、時代の移り変わりとともにエキセントリックであることが小説家に求められなくなってきた、ということですね。
島田 そうなんです。昔の文士は小説ももちろん書くんだけど、市民社会に向けて少数意見を述べ、愚行権を行使している面もあった。でも、その役割は時代が変わり、昨今だとより細かい分業が成立し、芸人やブロガーが担うようになってきた。もちろん、芸人、ブロガーも多数意見に与する人気商売ではあるけれども。たとえば、三島由紀夫は、純文学、大衆小説、それから戯曲まで書いて、その傍ら、映画やテレビに積極的に出演していた。
金原 今で言う芸人的な要素を兼ね備えていた、と言えますね。
島田 そうそう。だからこそ、彼はサブカル分野でアイコンになっていたんだと思います。そう考えると小説家に求められる役割はだいぶ変わってきましたね。言論についての責任は相変わらず問われてはいるんだけど、あまり公序良俗に反することを言ってはいけないという雰囲気のなかで、作家自体が小ぢんまりしていたほうがいいみたいな風潮は出てきたのかもしれません。
金原 昔、島田さんがトークショーで、世間が正しいことをやっている間は作家は馬鹿なことができるけど、社会がおかしくなってしまうと作家は正しいことしか言えなくなってしまうとおっしゃっていて、あぁ、今がまさにその時だなと思ったのを覚えています。確か、大震災の翌年だったかな。切実なものとして心に響いた言葉でした。私も東日本大震災の時に、政府に強い不信感を抱えていたので、そういう時に小説を書くと正しいことしか主人公に言わせられなかったんです。自分を取り巻くそういった状況を俯瞰的に捉えられないことに辟易してフランスに移住した頃だったので、島田さんの言葉がすごく腑に落ちました。
だから、現在の世のなかで小説家は、おかしいもののなかで正しいことを叫び続けるおかしな人、にならざるを得ないのではないでしょうか。以前、ある批評家が最近の小説はLGBTQの問題だったり、フェミニズムだったり、ポリコレだったりをテーマとして大々的に取り上げ過ぎると批判していたという話を人づてに聞きました。でも、なんでそういうテーマや言葉が小説を通じて出ていかなければいけないのか、その必然性をこそ考えなくてはいけないと思うんです。そこでしか上げられない声がある。つまり、今生きている社会に歴然とした問題がある場合、小説を書くときにそれを避けて全く違うところから物語を紡ぐことは無理なのではないかと思います。
島田 その通りですね。ただ、小説と批評や論説文のナラティヴは別だということは考えておく必要があるとも思います。アクティビストや専門家が現代社会における問題についてコメントする場合、一人称で自分の意見を言えばいいわけです。でも、小説家はそうじゃない。小説という空間のなかでその問題を扱う場合、正論も異論も同じ器に入れる必要がある。そのなかで複数の意見を戦わせたり、そこから出てくる矛盾を暴いたりするのが小説の役割です。例えば、リベラルな思想を持つ人間のなかにある差別意識のようなものを暴露するのは、小説だからこそできることですよね。
金原 確かに。あまりにも一元的な見方になり過ぎてしまうと小さくまとまってしまい、小説であることの意味がなくなってしまいますね。
島田 だからもっと包括的に、俯瞰的に、絶妙な距離感でもって捉えられるかどうかが重要なんだと思います。
金原 その距離感のなかで、自分自身に対してもどれだけ批評的になれるか、ということですね。他者のみならず、自分にも批判的になれる立場を保っておかなくてはいけない。確かに小説にしかできないことはあると思います。私はエッセイやコラムとかだと自分の主張が強く出過ぎてしまうので、それを諫めてくれるキャラクターのいる小説のほうが書きやすいんです。物語が進行する内、さまざまな立場の人の、あらゆる声が出てくる。そもそも自分自身の中にさまざまな主張があって、整合性のあるものばかりではないということもわかってきます。
島田 もう一つ、普通ならできない内部告発や不都合な真実の暴露も、フィクションの形式を借りればできます。その場合、読者との間にコンセンサスが成り立っていると理想的です。これは小説だけど、実は本当のことが書いてあるんだよね、みたいに。
金原 そうですね。ただ、その受け取り方を間違えてしまうと、著者と主人公を混同してしまう事態が発生することもあります。でも、考えてみると、それは面白いことではあるんですよ。なぜ人は主人公に著者を投影してしまうんだろうと私は以前からずっと不思議に思っていました。もちろん私自身もそういう錯視をしてしまうことがあって、これはこの著者がインタビューで言っていたことだったか、エッセイやコラムで書いていたことか、それとも主人公のモノローグや台詞だったか、というのがごちゃごちゃになってしまうんです。ですが、それはフィクションを楽しむ上で絶対的に切り離せない箇所でもあって、つまり人は「この小説を作った人がいる」という前提で小説を楽しむわけです。AIが書いた小説ではなく、生身の人間が書いたものである以上、そことそこを結びつけるなというのは無理な話で、むしろ著者と主人公と読者、という三者の関係性は意外なほど強く、それこそが読書という行為に深みを与えているのではないかとも思うんです。
































