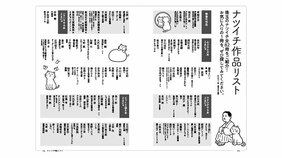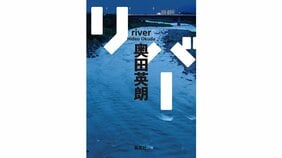新宿からの祈り
二〇一八年六月、当時住んでいたパリを離れ、私は一人日本にいた。本帰国に向けた家探しに全振りした一時帰国だったため、激安ビジホ滞在の超節約旅行だった。フランスから日本への引っ越し、物件の契約、家族四人分の航空券で一財産飛ぶ覚悟をしていたのだ。物件を見て回ったり、合間にマツエクやネイルに行ったり、隙間に仕事も挟みつつ友達とも飲み、戸籍謄本を取りに区役所に赴いたり、不動産屋に契約を交わしに行ったり、預けていた荷物を整理するため東京郊外の実家を訪れ、同時に引っ越し業者に見積もりに来てもらったりして、慌ただしい日々は過ぎていった。
ToDoリストをこなしていくのに比例して着実に目減りしていく滞在日数に寂しさを覚え始めた頃、仕事の会食を終え新宿からホテルに向かう途中、若い男が話しかけてきた。何やってる人? 夜? 昼? 分かった当てる、あもしかしてクリエイティブな感じの仕事? 一人で勝手に話し続ける彼を横目で見るといかにもなホストだった。
「分かった音楽系でしょ! バンド? 曲作ってる?」
割と惜しいなと思いながら首を振り、映画監督? とまで出たのに小説家という言葉は出なかった。一万円あげるからご飯一緒に行こうよ。新宿五丁目の交差点で私の前に立ちはだかると彼は懇願し続け、一方的に自分の話をし、私は道路の向こう側に交番があるのを確認した。彼は唐突に寂しいんだよと漏らして、私は彼に少しだけ共鳴した。延々続く自分語りを聞きながら、十代の頃は周りに軽いノリでホストを始めた友達がちらほらいたけど、なんとなくその頃とは違う匂いがすることに気がついた。今のホストってこんな感じなのかな、と疑問に思いながら「じゃあもう」と立ち去ろうとすると抱きしめられ、警察行くよ! と声を上げて振り払うと、コンビニでチューハイと日本酒を買ってホテルに戻って、清潔という特徴しかない狭い部屋で、私もあまりに寂しくて一時間くらいボソボソと泣いた。
日本最後の夜、入るかなと思っていた予定があったため空けていたけれど、結局予定は入らず一人だった。一人は普通に辛かったけれど、帰国前夜に一人でいるということが、そうでない場合よりも予後をましにするであろうことも理解していた私は、新宿をぶらぶらした後カフェバーに入った。翌日は十時台の飛行機に乗る予定で、一時前には帰ろうと心に決めていた。適当なつまみを食べていると、隣のカップルが帰るかこのまま夜を明かすかの瀬戸際のところで駆け引きをしている様子が伝わってきて、テーブル席では五人ほどの男女混合の観光客と思われる人たちが盛り上がっていた。しばらくすると観光客のうちの一人が「こんにちは。一人なの? 大丈夫?」と英語で聞いて、向かいに座った。彼の気持ちはよく分かった。私も、フランスで十二時近くに女性が一人でバーで飲んでいたら心配するからだ。
「これから誰かと会うの?」
「もうホテルに戻って寝る。私はフランスに住んでて、明日フランスに戻るんだ」
そう言うと、彼はそうなの? と大袈裟に驚いてから、安心したような顔を見せた。
「最後の夜だから、まだ帰りたくなくて」
「そうだったんだね。邪魔しちゃった?」
「大丈夫。あなたはどこから?」
「スウェーデンから。こんにちは。私は学生の時フランス語を勉強しました」
途中からフランス語に切り替えた彼に「フランス語喋れるんだ」と私もフランス語で答える。数分フランス語で会話をしていたけれど、彼の方が先に「もう無理だ」と英語に戻した。しばらくすると彼の友達らが帰り支度を始め、「彼女と残ったらいいよ」と真摯に勧めたけれど「いいんだ。彼女は明日朝早くにフランスに帰るんだって」と彼はやはり真摯に伝え、「ありがとう楽しかった。良い旅を」と握手をして帰っていった。この時、フランス語と英語で見知らぬ人と話したおかげで、少しだけフランスに戻る覚悟ができて、その覚悟はあの時の自分にとって救いだった。こんなふうにいろんな人がごった返す新宿を舞台にした小説を書きたいなと、帰り道ホストに大喜利のようなキャットコールをされながらぼんやり思った。
あれから四年以上が経った。帰国後は日本に再び馴染むのに苦心し、ショックな出来事やあらゆる出会い、コロナの波に揉まれ、あの時から必死に練り上げたプロットの小説は長い時間をかけて完成した。主人公、由嘉里の思い、「この私の手からデータが発信されていくこと自体が祈りで、その祈りはライのためでも私のためでもなく何者のためでもない、この世に存在する全ての分かり合えないもの同士の関係に対する祈りなんだ」。これはそっくりそのまま、私のこの小説への思いと一致している。深海の底に落ちた空き缶のように孤独だったあの時の私が育て始めたこの祈りが、一人でも多くの人に降り注いで、たまに誰かの体を温めますようにと願って止まない。