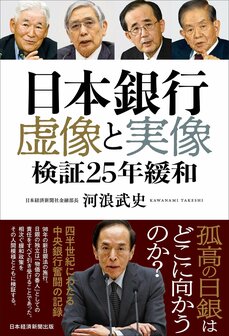バブル経済を放置した80年代の経済政策がそもそもの誤り
日本経済が成長しなければ企業は賃金を上げられない。賃金が上がらなければ家計は消費を増やせない。消費が増えなければ企業は売り上げが増えない。売り上げが増えなければ企業は投資しない。こうした成長鈍化の負の連鎖から抜け出せず、根雪のような物価停滞につながった。日銀はこれを「ゼロインフレのノルム(社会通念)」と表現する。

日銀が主張するように、確かに日本のデフレは1930年代前後の世界大恐慌時に比べれば極めて緩やかではある。1998年度から2012年度の15年間でみると、消費者物価の下落率は平均して年マイナス0.3%程度だ。その程度のマイルドな物価下落であっても「デフレ均衡」から抜け出すのは簡単ではなかった。
資産デフレという観点でみれば、その崩壊は日本経済に多大な悪影響をもたらした。
バブル景気最終盤の1990年、東京23区の商業地の公示地価は1坪あたり2705万円と、83年の7倍を超えた。それが2005年には同449万円と、1990年の6分の1に値下がりする。日経平均株価も最高値の3万8915円(1989年12月)から7607円(2003年4月)まで下落する。
民間銀行は株価下落で含み益という資本の余力を失い、不動産バブルの崩壊で融資先の担保も大きく毀損した。資産デフレが日本経済の金融システムを破壊し、企業の成長投資をストップさせたのは確かで、長期停滞の一端はここにあると言っていい。
日銀は88年から2年で公定歩合を2.5%から6.0%まで引き上げた。大蔵省も土地売買を厳しく制限する「総量規制」を89年に発動。金融政策と金融規制の両面で市場を引き締めすぎてしまい、それがバブルを激しく崩壊させてその後の低迷を招いたという批判は、一見すると正当化されるようにみえる。
しかし、資産デフレは、異常な水準に達した80年代のバブル経済の後始末にすぎない。結局は、経済の実力を大きく超えた資産インフレがその後の経済停滞の起点といえる。バブル経済を放置した80年代の経済政策がそもそもの誤りだったとみるのが適当だろう。