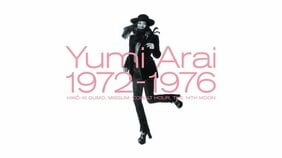異様な背の高さ、下半身の欠損……人々は「赤い女」の何に恐怖しているのか
――「赤い女」は何を象徴していると思いますか。または、何を象徴しているものとして語られてきたのでしょうか。
吉田 ひとつは女性の血ですよね。それも母として子どもを産むことで死んだウブメの系譜に連なる。カシマさんやアクロバティックサラサラにはそれに加え「子殺しの母」といった要素を見ることもできるでは、と考えます。「こわい母」のイメージが70年代くらいから出てくる。それは日本の社会状況とも、ある種リンクしていたと思います。
――というと?
吉田 初期の口裂け女は実は妖怪・怪物ですらない「ただのこわい人」の話でした。それが「おそろしい母親のイメージ」をまとわされていく。これは世の中で専業主婦の教育ママ、母子一体化が進んだ結果かなと。昔の人は母親と子どもがべったりではなく、乳母や家族全体、共同体ぐるみで育てたりしていた。それが戦後、高度経済成長を経て家族は核家族化し、女性は専業主婦化する。住環境の流動化、都市化が進み、必然的に母親と子の一体化が進む。カシマさんが登場する70年代には「母性が崩壊している」という言説を通じて逆接的に「母性が大事だ」ということが語られます。なんでもそうですが、「崩壊している」という言説こそが「それが必要だ」「脅威だ」と声高に強調しているわけですよね。たとえるなら、「お前、頭悪いな」と言う人は自分が頭が悪いと言われることを恐れているから、そう言うように。
もっとも私個人が「口裂け女は怖い母親の象徴」と主張しているわけではなく、むしろ否定的なのですが、ともあれ「教育ママ」への感情の裏返しとして70年代、80年代の人々には「おそろしい母」がもっともしっくりきたのだと思います。
――「赤い女」の身体的特徴についてはどう解釈ができますか。
吉田 非女性的なイメージですよね。江戸時代から塀越しに覗いてくる巨体の女の妖怪としては、けらけら女・屏風闚(びょうぶのぞき)などが想像/創造されてはいますが、背の高さ、大きさの強調はネット怪談の「八尺様」の影響もあるのかもしれません。2000年代以降のやや新しい特徴かな、と。
口裂け女も流行当初は「背が高い」という要素はなかったのが、時代が下ると「大きい女」というイメージが付け足されていきました。統計的に言えば男性に比べて女性がぐんと背が高いということはありませんから、数メートルにも及ぶ巨体の女性は異端なイメージを抱かせるものなのだろう、と。
それから「赤い女」には下半身がないことも多い。テケテケ、カシマさんなどがそうですね。興味深いのは、このふたつは男バージョンも最初はあったのが、いつの間にか男バージョンは駆逐されて女バージョンだけになったということです。トイレの花子さんのように、はじめから女性タイプばかりがクローズアップされたものではない。こうした推移があらわしているのは、下半身が欠損している存在としてこわいのは男より女の方、と感じられた恐怖観ではないか。
ではなぜこわいのか。下半身の欠損とは性器の欠如です。女性器が血まみれになり子どもが産めなくなっている――これはウブメの表象ですよね。産むのだけれども、産めない。そのあらわれだと捉えられるのではないか。