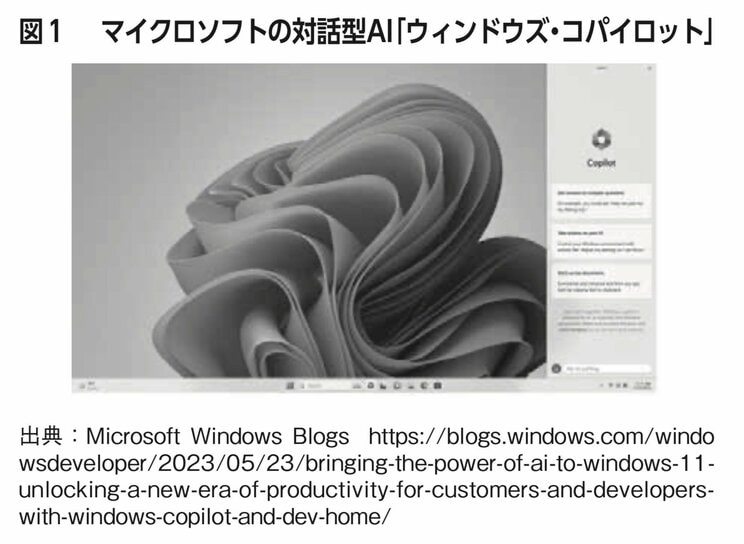言葉の指示でパソコンを操作できるようにする仕組み「ウィンドウズ・コパイロット」の登場
オフィスワーカーの最も身近なツールであるパソコンが、私達人間の言う通りに働くロボットのようになる──米マイクロソフトが2023年6月にプレビュー(テスト公開)を開始した「ウィンドウズ・コパイロット」は、そんな時代の到来を予感させる対話型AIです。
「コパイロット(Copilot)」は副操縦士を意味し、人間が言葉で指示をすることでパソコンを操作できるようにする仕組みです。普段はウィンドウズのデスクトップ画面の最下部にあるタスクバーにアイコンとして常駐しています。
必要に応じて、このアイコンをクリックするとデスクトップ画面の右側に縦長のサイドバーが表示されます。これが私達ユーザーとコパイロット(AI)が対話するためのチャット画面になります(図1)。
このチャット画面を通して、ちょうどChatGPTのようにAIに対して様々な質問をすることができます。これらの質問にAIが答える形で、ユーザーが満足する回答を得るまでチャットが続いていきます。
また各種アプリの起動や操作、パソコンの設定変更、さらには文書ファイルの処理といった作業も、言葉による命令つまり「対話形式」でAIに指示することができます。
たとえば「ちょっと目が疲れたので、パソコンの操作環境を改善したいんだけど」とリクエストすると、AIが目に優しい画面設定を提案して自動的に変更します。
あるいは会議の議事録などの資料をPDFファイルにしてチャット画面にドラッグ・アンド・ドロップし、その資料の要約を指示することもできます。
さらに「気分転換に音楽が聴きたいな」などとリクエストすると、音楽配信サービスから楽曲のリスト等を含む再生画面を表示してくれる、といった具合です。