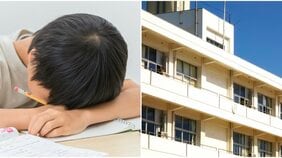「親が声を上げることも大切です」
看護休暇の取得が十分に広がらない背景には、日本特有の要因が隠れているのではと高祖氏は指摘する。
「看護休暇は法律で定められていますので、従業員から取得の申し出があれば事業主は拒否できません。ただ、日本は中小企業が多いので、育休でさえ取りづらい雰囲気は残っているでしょうし、看護休暇に関して言えば、そもそもあまり知られていない可能性もあります」
令和3年の法改正から「時間単位」での取得ができるようになるなど、制度は少しずつ改善されている。それでも現場の負担感は大きく、親自身が「複数の選択肢を持つ」「必要な声を上げる」ことも重要だと高祖氏は続ける。
「親がさまざまな事情で仕事を休むのが難しい場合には『病児保育』などを利用するという方法もあります。いざ子どもの看護が必要となったときのために、事前にそうしたサービスを調べておいて、複数の選択肢を持っておくことも大切です。
制度が使いにくくて仕事と子育ての両立が大変だと感じるのであれば、『今のままでは困る』と声を上げることも必要です。SNSの時代ですから署名活動などを通じて意見を集める方法もあります。
また、企業が柔軟な働き方を取り入れるのも重要です。在宅勤務を使えれば、治りかけの子どもをみながら仕事をすることも可能でしょう。職種にもよりますが、在宅勤務がない場合は、企業に働き方を提案してみるのも一案です。
今は共働き家庭が多く、『子どもが急に熱を出した』なんていうことは多くの親が体験していること。そういう中で、少しでも働きやすい社会にしていくために、親が声を届けていくことが大切ではないでしょうか」
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班