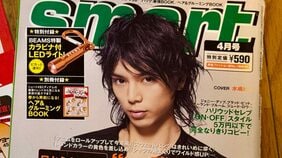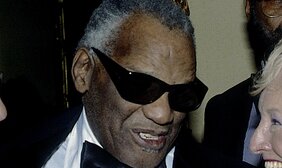エンタメ
会員限定記事
メイド・イン・ジャパン
- #1
- #2
ピンク・レディーがアメリカ進出した際に強いられた露骨な路線とは…当時求められた「ジャパニーズ・ガール」への即物的な欲望
メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法 #1
この記事は会員限定記事(無料) です
続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
この記事のまとめ
- #1ピンク・レディーがアメリカ進出した際に強いられた露骨な路線とは…当時求められた「ジャパニーズ・ガール」への即物的な欲望
- #2坂本九は幸運、ピンク・レディーは健闘、YMOはいわば逆輸入…ではBTSの立ち位置は? アジア人アーティストのアメリカ挑戦が示すもの
次のページ
画像ギャラリー