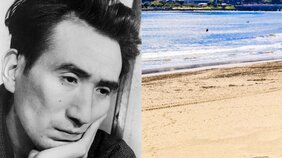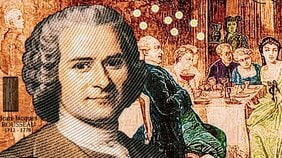衛生学の研究が育んだ珍妙な創作料理
1890(明治23)年発表の『舞姫』や1911(明治44)年発表の『雁』など、数多くの傑作を残した森鴎外。誰もが知る大作家であるだけでなく、陸軍軍医、翻訳家、大学講師、帝室博物館(現在の東京国立博物館)総長としても優れた功績を残している。
この立派な経歴だけ見ると、お堅い常識人という印象を受けるだろう。しかし、鴎外は常人には理解しがたい風変わりな嗜好を持っていた。「悪食」である。
鴎外による悪食の代表といえば、「饅頭茶漬け」が挙げられる。これは白米の上にアンコ入りの饅頭を割ってのせ、お茶をかけて食べるというもの。この饅頭茶漬けなるものを何よりも好み、事あるごとに食べていた。子どもの頃から大の甘党だったとはいえ、なんとも珍妙な組み合わせである。
キテレツな食好みは他にもある。干し柿を白米の上にのせてお茶をかける「柿茶漬け」、焼いた餅を醤油に浸し白米の上にのせてお茶をかける「餅茶漬け」、刺身を醤油とみりんと日本酒で煮た「醤油煮」など、いずれもおいしそう……ではない。
鴎外が好んだ悪食のルーツは大きくふたつ。
ひとつは、“細菌嫌悪”に由来する。
かなりの潔癖症としても知られる鴎外だが、きっかけは4年間のドイツ留学で学んだ「衛生学」である。大学の医学部を出て軍医となった彼は留学を命じられ、ミュンヘンにて細菌学の権威ペッテンコオフェルに学ぶ。さらにベルリンにて細菌学者コッホの衛生試験所で研究に従事した。
そこで細菌学に精通すると、過剰なまでの潔癖症に陥る。とくに“生モノ”に対して強烈な警戒心を抱くようになり、日本に帰国してからは、沸かしていない水は決して飲まず、大好物だった果物ですら生のままでは口にできなくなった。
しかし、果物への欲求がどうにも抑えきれなかったのだろう。鴎外は果物を鍋で煮込んで食べている。果物といえば新鮮なみずみずしさが魅力だが、そんなことより火にかけて細菌を死滅させるほうが重要だったわけだ。
子どもたちを連れて通った西洋レストランでも細菌学・衛生学的なこだわりを見せている。どんな店であろうと「マヨネーズのようなドロドロしたものは食うな」と叱咤するのが常であった。“ドロドロとしたもの”は、人の手によってさまざまな食材が攪拌されているため、手に付着したばい菌が媒介する恐れがあり、また器具を使ったとしても攪拌の過程で空気中に浮遊する細菌が入り込んでいるという強い不信感があったのだ。