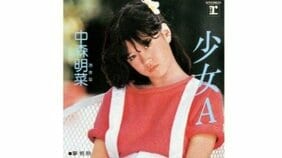時間は単線ではない
小池 彩和が俊輔の求婚を受けいれたのは娘のためで、もし俊輔が浮気するようなことがあっても彼女はきっとがまんできる。そんな彼女が、ほかの誰かといる時間が楽しかったと少し思ったことで家族の運命が狂い始めます。
俊輔が胸のうちで何を考えていたかはあえて説明的に書いていませんが、誰もどうすることもできない、こうすれば良かったのに、というのがない物語です。
私は別に不幸を書きたいわけではないんですよね。幸福も不幸もすべて連関しているんじゃないか。私たちは不幸のただなかにいると、これが早く終わってほしいとか、次はどんな人生が始まるんだろうとか想像しますよね。それはまったく自然なことなんだけど、実際にはそれらはすべて連関していて、幸福も不幸もいちいち大騒ぎすることではないのかもしれません。
その意味でもこれは、夫が余命宣告を受けて、壮絶な闘病生活を経験し、結局は彼を失うことになった自分自身の体験があってこそ書いた小説なんだと思います。今回、永劫回帰とかウロボロス的なものにより強く惹かれたのは、そういうことだと思う。
喪失を体験した人はみなさんそれぞれ悩んで苦しんで、周りからは「早く元気にならなくちゃ」とか「がんばって乗り越えよう」と言われたりもしますけど、私は「乗り越えよう」という方向にはまったく心が動かなくて、「これはいったい何なのだろう」とずっと考えてきました。考えてたどりついたのが、ウロボロス的な時間の流れです。幸福も不幸もすべてが連関しているというのは、私の実感ですね。
だから、物語としては私自身の人生とはまったくかかわりのない小説ですが、小説を流れている大きなテーマは、今この時点の私が考えていることそのものです。
ただ、『神よ憐れみたまえ』を書いたときにも、恐竜が絶滅するエピソードを書いていたりするので、時間の流れへの関心というものは、私自身の中にずっとあったものかもしれないですね。母の認知症がかなり重くなったとき、突拍子もないタイミングですごく昔のことを思い出したりするのを、母の中で時間はどんな風に流れているんだろうと考えたことも思い出しました。
――小説の中でモーツァルトのピアノ協奏曲第21番第2楽章のレコードが流れる場面がくりかえされます。この瞬間、小説の登場人物同様、読者も時間が巻き戻されたような感覚を味わい、今とは異なる別の時間の流れがありえたかもしれないと想像させます。
小池 モーツァルトが流れるなかで食事をする場面は、新しい家族の幸福を象徴するものとして書いています。
死別を体験して、私は自分が、一種のPTSDを発症したのではないかと思うことがあって。それまでとはまったく別の時間が流れているという感覚がすごく強い。しかもその流れている時間は単線ではない感じがするんです。
私の死別体験なんて、たとえば戦場に行ってPTSDを発症した人からしたら百分の一、千分の一のことなのかもしれません。でも、やっぱりそれまで流れていた穏やかな時間がそこで終わったわけで、その意味ではかすかな共通点もあるような気がする。
そういうことを、ずっとめんどくさく考え続けている人間なんです。めんどくさいことをめんどくさいままにしておくと自分が混乱しちゃうので、こうして小説を書くんです。作家で良かった。小説を書くことができる人間で良かったと思いますよ。
作品は「遺書」
――その混乱がひとつひとつ言語化されていき、小説になるという作業がすごいですね。
小池 小説にすることで一つけりをつける、ということもありますしね。
「小説すばる」の最後のページに作家の簡単なプロフィールが載っているじゃないですか。あれを見るたびに、「私がいちばん年上だな」と思うのよ。「私はいつまで書き続けるんだろう」って。
たぶん頭さえはっきりしていれば、こうして書き続けていくんでしょうね。誰かのために書くというより、たぶん自分のためなんじゃないかという気がします。自分のために、何かを表現していくんだと思います。
――長編を完成させて、休む間もなく「小説新潮」で「ソリチュード」という新連載が始まりました。
小池 『ウロボロスの環』のあと、次はまた書き下ろしで長編を書く約束をしていたんだけど、いくらなんでも体力的にすぐには無理だし。
それがある日、小説の神さまみたいなのが降りてきてくれて、書きたい、と思ったのが「ソリチュード」でした。一年間ぐらい、今の自分が考えていることを散文形式で書く予定で、長編に取りかかるのはそれからですね。
かなり前ですが、作家の辺見庸さんが新聞のエッセイに「書くことは全て遺書なのだ」というようなことを書いておられて、強い感銘を受けました。作家ってみんな遺書を書いているんだろうな、と思いました。そう思える作品を残していきたいです。
「小説すばる」2025年11月号転載