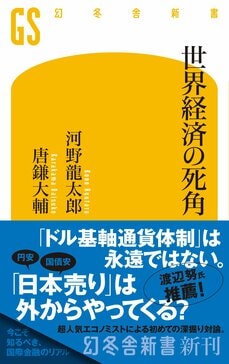日本の組織風土とジョブ型は“食べ合わせ”が悪い
河野 日本社会は「ジョブ型」導入の効果に期待しすぎじゃないか、という唐鎌さんの指摘は重要です。ここで私が言っているのは、あくまでもカッコ付きの日本型ジョブ型のことですが、世界的に見れば、ジョブ型は決して最先端の働き方というわけではありません。
唐鎌 むしろ海外では、ジョブ型など特別な働き方ではなく、ごくありふれた働き方の一つだと思いますね。
河野 ジョブ型は、18世紀後半に産業革命が起こった頃から、欧米で広がっていきました。
欧米ではジョブ型雇用が引き起こす様々な問題がすでに明るみに出ていて、その解決策をずっと模索し続けているようにも見えます。たとえば1930年代の戦間期から1970年代頃までは、アメリカの大企業が日本の長期雇用制に近いような制度を取り入れていました。
また、ヨーロッパのライン川流域にあるオランダ、ドイツ、フランスといった国では、ホワイトカラーは、もともと日本の長期雇用制に近いような雇用形態がとられてきました。こうした特徴などから、これらの国々の制度は「ライン型資本主義」といった名前で呼ばれたりします。
外資系金融機関に四半世紀にわたり身を置いてきた私の印象からすると、今の日本の組織風土とアメリカのジョブ型は、非常に相性が悪いように思えます。仮に、アメリカのジョブ型をそのまま日本の会社に導入したら、一発屋とゴマスリ屋のような人たちが跋扈する事態になってしまいます(笑)。
唐鎌 一発屋とゴマスリ屋ですか(笑)。
河野 言葉は悪いですが、これは真面目な話です。そもそも人の能力というものは周囲の環境がたぶんに影響するので、今うまくいっているのが本当にその人の力量のおかげなのか、疑問に思うこともあります。
実際には、一緒に働いている人との相性が大きく影響しているのではないでしょうか。仕事は運・不運も大きく影響するので、その人が優秀かどうか、直属の上司であっても、短い時間で見極めることはまず不可能です。
長期雇用制の利点は、何人かの上司の目で一人ひとりをチェックして、誰が本当に優秀で、幹部に登用すべきか、かなり長い時間をかけて見定められるところにあります。
一発屋のような人を突然、幹部に加えたら、下手すれば経営が不安定化しかねませんよね。うまくいった場合は「俺の功績」、うまくいかなかったら「部下のせい」、みたいな人もたくさんいますしね。
長期雇用制にガタがきているのは事実だと言いましたが、それなりのメリットもあるわけです。先ほど触れたように選抜の遅さなど改善したほうがよい部分もあるので、その改善に貢献する形で日本版のジョブ型を導入することができるのなら、まるきり無意味でもないとは思います。
唐鎌 ちなみに今、日本企業でジョブ型と呼ばれている制度の多くは、実際には旧来のメンバーシップ型とさほど変わらないように見受けられます。
本来のジョブ型は、「ポストに適した人材を配置する仕組み」だと思います。「ポスト」が大前提として存在していて、そこに「人材」をはめ込む、という手順です。
しかし、多くの日本企業では、「人材」が大前提として存在していて、それに「ポスト」を与える、という手順になっているように見えます。
本来のジョブ型では「ポスト」がなくなれば、はめ込まれていた「人材」も不要、つまり解雇になります。しかし、おそらく今、日本企業の多くで取り入れられているジョブ型では「ポスト」がなくなった場合、「人材」は解雇されずに別の部署へ異動させられて「こちらが新しいポストです」と、違うジョブが与えられると思います。
結果として、日本のジョブ型は、従来のメンバーシップ型の枠組みをほぼ維持したまま、表面的に名称を変えたものにすぎないという印象を抱きます。その善し悪しはさておき、本来のジョブ型とは似て非なる代物だという理解は持ちたいところです。
河野 私も日本で「ジョブ型」といっているものは、基本的にメンバーシップ型の“変種”だと思っています。
文/河野龍太郎、唐鎌大輔 サムネイル/Shutterstock