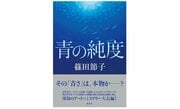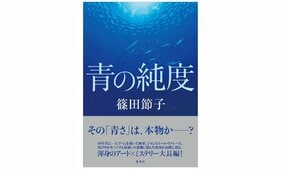ビッグアーティストたちがまとうミステリー性のあるエピソード
――『青の純度』の主人公である有沢真由子は、アート専門誌の編集長を務めたこともある敏腕編集者です。五〇歳の誕生日を迎えた日、熱海のホテルの地下でジャンピエール・ヴァレーズの絵と出会い揺さぶられてしまった経験から、かつてはスルーしていた彼の作品の価値を再検証するような書籍の企画を立ち上げます。バブルの頃、ヴァレーズの絵を高額で売りつける画廊商法は詐欺ではないかと社会問題になり、令和の世で同じ商法が復活しつつあることに真由子は当初憤りを感じているのですが、取材を進めてみると買い手の側には喜びがあった。それまでは美術館に行って鑑賞するだけだったアートを、自分で所有して飾る、というムーブメントはバブルの画廊商法から始まったのではないかという指摘がありました。
高橋 そうだったと思いますよ。ただ、定着はしなかった。日本では難しいですよね。居住空間が狭いから、絵を飾れる壁面が少ないんです。
篠田 窓が大きいですしね。日本では伝統的に、インテリアみたいな形でおうちの中に飾ることは昔からあったわけじゃないですか。ふすまとか屛風とか。
高橋 風鈴とか。ただ、家に絵画を四六時中飾るなんていうのは、西洋の伝統ですね。結局、異文化なんですよ。日本の文化ではないから、絵を飾るというのはどこか居心地が悪かったんでしょうね。
――主人公は画家が在住しているとされるハワイを訪れるんですが、現地取材でジャンピエール・ヴァレーズの絵は、現地では「マリンアート」と称される作品群の一つに過ぎないことを知ります。画家にまつわるさまざまな「謎」を巡る探偵行の中に、アマチュアとプロ、人気が出る作家と人気が出ない作家、新作と贋作の違いは何か……といったアート業界にまつわる「謎」が盛り込まれていきますね。
高橋 面白いよね。今個人的に、非常に気になっているのはアマチュアとプロの問題です。僕が昔「国立西洋美術館」とか「三菱一号館美術館」で仕事をしていた頃は基本的に、歴史的にバリューがある画家をどんどんどんどん深掘りしていく、というやり方で展覧会を作っていたんですね。ところが四年前に東京都美術館に来てみたら、公募団体展だとか、そういうのを年がら年中ここではやっているんですよ。都美術館はお客さんが年間二〇〇万人以上入るんですが、一〇〇万人はミロやゴッホを見に来る人たちで、もう一〇〇万人はこちらで公募展を見る人たちで、層がかなり違うんですよね。盆栽展(国風盆栽展)なんて開館と同じ歴史があって、一〇〇年やってるんです。
篠田 そうなんですね。
高橋 言ってしまえば、アマチュアの世界が堂々と美術館のいわゆるファインアートと同居している。これは、他の国ではまずないですね。もちろん、古くからのサロンというのは一種の公募展なんだけれども、それはファインアートの頂点に位置づけられている。日本の公募展とは全く異なるルールでできているんです。日本には日本の、独自のアートの文化があるんだと、この歳になって痛感しているところなんですよね。
――ジャンピエール・ヴァレーズは金髪の白人で、フリーダイバーでもある。そのビジュアルや経歴が、彼のマリンアートの価値にマジックをかけていた。こういった、画家の人生込みで作品を見るという鑑賞法の是非についてはどう思われますか?
高橋 それって不純だよねという意見も分からなくはないけれども、作品と作家ってやっぱり切り離せないところがあると思う。
篠田 作家本人のキャラクターや見た目と、絵画がワンセットみたいになって売られちゃった例はあるのでしょうか。
高橋 ジャンピエール・ヴァレーズとは正反対な例ですけど、トゥールーズ=ロートレックとかがそうですよね。ロートレックは身体障がいの問題で差別されてきました。見た目と、それから貴族の息子であるといった個人的なヒストリーは、ロートレックの絵が広がるにあたってすごく重要だった。
篠田 物語性ということですね。
高橋 ゴッホもそうです。晩年に精神科の病院に入って最後は自殺した、とか。レオナルド・ダ・ヴィンチもミケランジェロも、ビッグアーティストたちがまとうミステリー性のあるエピソードは、作品と切っても放り離せないところがあります。
篠田 ジャンピエール・ヴァレーズの周りの人たちのように、最初から画家のエピソード込みで作品を売っちゃおうというようなのは……。
高橋 そこまでのことはなかったでしょうね。あの、ちょっと宣伝めいた話をしてもいいですか?(笑) 七月から大阪の大阪市立美術館で始まり、九月からは東京都美術館で開かれるゴッホの展覧会は、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」というんです。ゴッホの弟のテオと、テオの奥さんのヨーがいなかったらゴッホはこんなに世界的な売れっ子にならなかったかもしれません。なったとしても、時間もかかったし、また違うステップに行ったはず。今度の展覧会では、ゴッホの死後の評価を決定づけた、ゴッホのファミリーヒストリーが良く理解されるだろうと思っています。家族に限らず、画家を周りの人がどう支えていたか、生前や死後にどういうふうに画家を盛り上げていったかは、画家の評価を決めるうえですごく大事な要素になっているんです。
篠田 去年こちらで拝見した田中 一村(「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」)もそうでしたよね。
田中一村は、若くして画壇の中央で上り詰めていくということには背を向けてしまい、晩年は奄美大島に移住して独自の世界をどんどん展開していった。生前は評価されなかったんですが、没後に評価が高まりました。なぜかというと奄美の人たちが、田中一村のことをすごく愛しているんですよ。彼の作品を広めようと腐心されているんです。
高橋 周りの人がどれだけ意思を持って、画家の存在を広めていこうとしているか。それがあるかないかで、えらい違いが出るんです。
――今のお話、『青の純度』の後半の展開を知るものとしては心に沁みます。

人から要求されたものを書いていたとしたら
――本作は絵を描く人間、もの作りをする人間の情熱や執念についての物語でもあります。売れたいとか有名になりたいからとかではなく、描きたいから描く。この感覚は、普遍的なものなのでしょうか。
高橋 それがなければやれないですよね。それは節子さんもそうでしょう? 小説、何十冊以上も出しているんですよね。
篠田 数えていないです(笑)。
高橋 数を忘れちゃうぐらい書いている(笑)。
篠田 作り手を突き動かすものを目の当たりにして、感じたこととかってありますか? 私はアーティストの方との直接のお付き合いがないので、それを目の当たりにすることはないんですが……。
高橋 いや、僕もないです。僕はメンタルが弱いから、そういう人たちと付き合うのをつい避けてしまう(苦笑)。物故作家だったら大丈夫なんですけどね。実際、アーティストと向き合って運命を共にするような仕事は、しんどいと思います。例えば、さっき話題に出たギャルリーTが扱った画家の一人に、ベルナール・ビュフェという人がいました。
篠田 フランスの画家ですね。
高橋 一九五〇年代を中心にフランスでは売れっ子作家だったんですけど、最後は自殺しちゃうんです。あんなに売れて、本人もイケメンできれいな奥さんをもらってシャトーに住んでいたのに。近くにいた人は、相当ショックだったと思いますね。
篠田 自殺にまで至ってしまったのは、どうしてだったんでしょうね。
高橋 自分で自分を追い詰めていってしまったんじゃないでしょうかね。周りからは成功したと言われるけれども、自分の表現したいものが思った通りに描けないという葛藤が、積み重なっていってしまったんじゃないか。そういう画家、多いんですよ。歳を重ねるにつれて、自分が立てたコンセプトみたいなものに押し潰されてしまう。
篠田 確かに晩年になるとコンセプトが前に出過ぎてしまって、どんどん意味が分からなくなっていく画家はいますね。
高橋 自然と作風が変わっていくのがいいんですよね。だんだんだんだん、歳を取るに従って自由度が増していく画家を見ていると、見ているこちらもちょっと自由になれる気がする。
篠田 特定の作品が心ならずも評判になっちゃったことで、同じような絵を要求され続けるってこともありそうですよね。文芸の世界ではよく聞くんですよ。これで急に人気が出てしまいましたという作品があると、それに似たものを次もお願いしますという依頼が来て、どんどんどんどん人気は出てくるんだけれども、本人はもう書きたくなんかなくなっていたりするんです。
高橋 篠田さんも、もしかしたらありますか?
篠田 ないです、ないです。人から要求されたものを書いていたとしたら、私の本、もっと売れていると思います(笑)。
高橋 その時の自分が書きたいものを自由に書いている、と。素晴らしいですね。それが一番ですよ。
篠田 私の場合、そういう書き方しかできないんですけどね。
「小説すばる」2025年9月号転載