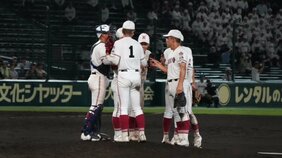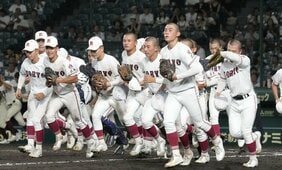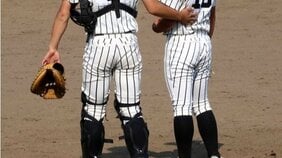体育会系の就活事情について専門家が分析
OB・OGと連携したリファラル採用や『体育会枠』を設ける企業も存在する。こうした制度を活用すれば、体育会系学生は効率的に内定を得るチャンスが広がる。
さらに阿部氏は、企業が体育会系を評価する背景を次の4つに整理した。
(1) 忍耐力・ストレス耐性の高さ
厳しい練習や困難な目標に直面する中で鍛えられたメンタルタフネスがあり、「仕事で辛いことがあってもへこたれなさそう」と期待される。
(2) 規律性・礼儀・自己管理力
部活動での厳しい上下関係やルールに慣れているため、礼儀正しく、規律を守る姿勢が社会人として評価されやすい。
(3) チーム志向・協調性・リーダーシップ
チームの中で役割を理解し、協働する力や、キャプテン経験などを通じたリーダーシップが大きな強み。
(4) OB・OGネットワークの活用力
体育会系学生はOB・OGとのつながりが強く、卒業後もその人脈力を発揮してビジネスでも活躍することが期待されている。
では今回のネット上の議論の発端となった「ハラスメント耐性」説についてはどうなのだろうか。
「確かに、体育会系学生は『言われたことはこなす』『厳しい環境に慣れている』というイメージから、そう揶揄されることもあります。ただ、それはあくまで一面的な見方です」
阿部氏によれば、今の体育会系教育は以前のような精神論一辺倒ではなく、科学的なトレーニングやPDCAサイクルを取り入れた自律的な成長が主流になっているという。
「むしろ企業が求めているのは、指示待ちではなく自ら考えて行動し、改善につなげられる主体性です。そうした“進化した体育会系”は歓迎されつつありますね」
ただその一方で、近年の採用現場では、世代間ギャップや“〇〇ハラ”など多様化するハラスメントへの敏感さなどから、採用担当者が若者との接し方に慎重になる「若者恐怖症」的な傾向も出ている。
そうした中で体育会系学生は、上の世代の人たちが自分たちの価値観のまま接しやすい人材として捉えられている可能性があるという。