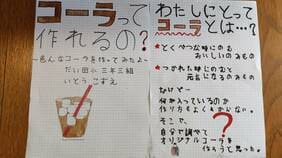「資本の成功」こそが資本主義を終わらせてしまった
――『テクノ封建制』を最初に読んだときの感想をお聞かせください。
大澤 じつは僕は、この本が英語で出版された時に読んでいます。非常に重要なことが書いてあると感じました。
この本のどこが重要なのか。最近は僕自身のものも含めて、「資本主義」という言葉がタイトルに付いた本が非常に多く出ていますよね。なぜかというと、資本主義に対する、ある種のアンビバレントな感情があるからだと思うんです。
一方では「資本主義は自滅するのではないか」、あるいは「終わらせるべきではないか」という感覚があり、他方では「でも資本主義以外に代わるものが見えない」とも感じている。つまり、終わるかもしれないという切迫感と、終わるはずがないという諦念が共存しているんですね。
しかも、その「終わる」には終末論的で破局的なイメージがまとわりついています。だから多くの人が悲劇的な未来を予想し、不安を抱えているわけです。
この本は、そうした世界的な不安や恐怖に対して、非常に独特で説得力のある答えを提示しています。
著者のバルファキスは、『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』(ダイヤモンド社)というベストセラーがあります。同書は自身の娘に語りかける形式だったのに対して、今回はすでに亡くなったお父さんからの問いに答えるという形式になっているところがユニークです。
読んでいると、バルファキスのお父さんは、ただの父親という以上に、非常に立派な人物だったことが伝わってきます。鉄鋼関係のエンジニアとして自分の仕事に誇りを持ちつつ、同時に労働運動のリーダーでもあり、いわば左翼的な立場の人です。人間的にも知的にも非常に優れた人だったようです。
そのお父さんが、1993年、実家のコンピューターをインターネットに初めて接続したその日に、ある問いをバルファキスに投げかけるんですね。その問いが非常に本質的で驚かされます。
「コンピュータ同士が会話できるようになったってことだよな。このネットワークのおかげで、資本主義を転覆させるのはもう不可能ってわけか? それとも、これがそのうち資本主義のアキレス腱になる日が来るのかい?」(『テクノ封建制』p.42)
この問いに対して、当時のバルファキスは明確な答えを持っていなかった。しかし、年月が経ち、今ようやくその問いに対して答えることができるようになった。そしてそれが、この本の大きなテーマにもなっているわけです。残念ながら、彼のお父さんはその答えを聞かずに亡くなられてしまったのですが、バルファキスはようやくその問いに正面から向き合い、答えを出したのです。
その答えとは何かというと、結論だけを言えば、「資本主義はすでにインターネットによって終焉を迎えつつある」というものなんですね。
ただし、お父さんが当時想像していたような、より良い社会への転換として「資本主義が終わる」のではない。むしろその逆で、資本主義よりもさらに悪い、新しい形態に変化してしまっている、ということなんです。
つまり、お父さんの問いに対する回答は「イエス」でありながら同時に「ノー」でもある。
「確かに資本主義は変わった。だが、それはあなたが望んだ方向ではなく、もっと悪い方向に変わったんだ」というわけです。このねじれた形での答えこそが、この本の核心部分であり、非常に知的な読みどころでもあります。
どういうことかというと、資本主義というシステムそのものは終わったかもしれないが、資本は現在もなお力を持ち続けている。そして、その資本は資本主義の枠組みの中であまりにも成功しすぎたがゆえに、自らを変容させ、新しい形態を取るようになった。つまり、資本の成功が資本主義を終わらせてしまった、という皮肉な構造です。
ではその新しい形態とは何か? それが「封建制」です。現代の資本が利益を得ている仕組みは、もはや従来の資本主義的なものではなく、中世の封建制的なメカニズムに近いものになっている。そこがこの本の核心であり、非常に刺激的な論点でもあります。