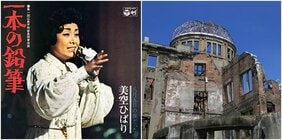相次ぐ家族の死、結びついた原爆の記憶
一家が広島市中心部を離れたのは原爆投下から3日目だった。広島県内の田舎に逃れた。日本の敗戦から4カ月後の11月ごろ、久保田の一家はもともと暮らしていた東京へ戻った。
「よくお元気でお帰りでしたね」。近所の人は親切だった。だが、家族からは「原爆の話はしちゃダメよ」と言い聞かされた。
戦後10年の間に、姉と兄が相次いで亡くなった。被爆後からずっと体調が悪かった母も、床から起き上がれなくなった。
「第5福竜丸事件」が起きたのは、ちょうどその頃だ。第5福竜丸事件というのは、1954年に日本のマグロ漁船がマーシャル諸島のビキニ環礁でアメリカの水爆実験に巻き込まれ、乗組員らが被曝した事件のことだ。この事件は、放射線の人体への影響が注目される契機になり、国内の原水爆禁止運動につながっていく。
久保田にとっても、この事件がきっかけとなり、初めて、病と原爆を結びつけて考えるようになった。白血病になった母は自分を責めた。「広島に連れて行ってしまって、子どもたちに申し訳ない」と。その数年後、母も息を引き取った。
異常なまでの稲光への恐怖が、原爆とつながったのも、この頃からだ。
そして、のどが渇くたびに、久保田の脳裏には、近所のお兄さん、三木の姿がよみがえり、最期に水をあげることができなかった後悔で胸が詰まる。洋服や日用品が焦げると、死体を燃やす臭いが鮮明によみがえり、吐き気をもよおす。
久保田はいまも、広島には足が向かない。「嫌な思い出っていうのはずっと消せないんだって(痛感する)」。その後もずっと、「自分は被爆者なんだ」という思いがついてまわった。
子どもをもつつもりはなかったが、夫の家族の強い希望で25歳の時、長男を出産した。産声を聞いた時、自分の口から出てきた言葉は「指はちゃんとありますか」だった。身近な被爆者が病気になるたびに、「もしかしたら私も」と思ってしまう。
なぜ、こんなにも苦しめ続けられなければならないのか。そう考えると、次第に「この理不尽な苦しみを伝えなければ」という思いが強くなっていった。被爆者団体に所属し、70歳を超えた頃、勇気を振り絞って小学4年生に体験を語った。語ってみると、心の中にずっととどめていたものを、吐き出せた気がした。気持ちが少し、楽になった。
「人生がスタートして8年目で、原爆を体験してしまった」。
被爆の記憶と共に、人生が積み重ねられてきたような気がする。「自分はもういいんです。でも、次の世代で同じことが起きないように、子どもや孫の心にトラウマを残さないように考えてほしい。そのために死ぬまで伝えなきゃって思っているんです」。
久保田は静かに語った。
文/後藤遼太、大久保真紀