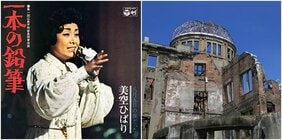銀色とも白ともいえない光
東京都杉並区の久保田朋子(87)は、被爆体験を日常生活の中で思い出してしまう1人だ。
突発的に激しい雨が降った2024年7月上旬のことだ。突然の光と共に、柱の時計がはじけたような音を立てた。リビングの天窓に稲光を見た久保田は、急に息ができなくなった。心臓が縮みあがり、体が動かない。しばらくじっと動かずに、動悸がおさまるのを待つしかなかった。
雷が過ぎ去った後は、決まって食事が取れなくなる。「あの日の光を体が覚えているんじゃないかなって」。久保田はそう言う。
雷の1番古い記憶は小学生の頃だ。空が光ると、母のそばへ駆け寄った。恐怖は、母が亡くなった大学生の頃からより強くなった。反射的に、その場にあるもので頭を覆わずにはいられない。兄はいつも、「お前はいい年して情けないな」とため息をついた。
なぜ、こんなに雷が怖いのか─。
1945年8月6日。久保田は疎開先の広島市宇品町にある祖母の家にいた。
あの日は雲1つない晴天だった。朝7時に起きると、祖母は勤労奉仕に出かけ、すでにいなかった。母は、体が弱い姉を病院に連れて行く支度をしている。「空襲警報のサイレンが鳴ったら、外に出てはダメよ」。母の言葉を聞きながら、久保田はぼんやりと庭を眺めていた。
その瞬間、銀色とも白ともいえない光に包まれた。意識を失った。
どれくらい経ったか分からないが、母の声で気がつくと、隣の部屋まで吹き飛ばされていた。耳の後ろにできた切り傷を止血し、家族で河原に避難することになった。
自宅は爆心地から2.5キロほどのところにあった。外に出ると、瓦や土塀のがれきが30センチほど積もっていた。
爆心地の方向に進んだ。河原は血を流した人であふれ、女性や子どもの泣き叫ぶ声が響いていた。船着き場には、やけどで風船のように顔が膨らんだ少年が座っている。唇は腫れ上がり、目は線だけになっている。その少年は「水、水がほしい」とか細い声を出していた。
その少年の隣に目をやると、祖母の家の前に住んでいた女性がいた。その時初めて、顔が膨らんだ目の前の少年は、よく遊んでもらっていた中学1年の男子学生だと、久保田は気づいた。
少年の名前は、三木一壮。登校前に顔を合わせると、いつも優しく「おはよう」と声をかけてくれた、近所のお兄さんだった。久保田は水をあげたいと思ったが、「水を飲ませると死んでしまう」と周りの大人に諭され、かなわなかった。
翌日、祖母の家の近くを歩いていると、空き地から煙が上がっていた。のぞいてみると、古材を井桁に組んだ中、火が回った三木の遺体が反り返るように跳ねたのが見えた。怖さを感じた久保田はその場から走って立ち去った。なんとも言えない、「ものすごい嫌な臭い」が鼻に残った。
自宅に帰ってこなかった祖母は、眉間に瓦が直撃して亡くなっていた。