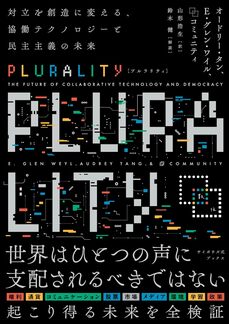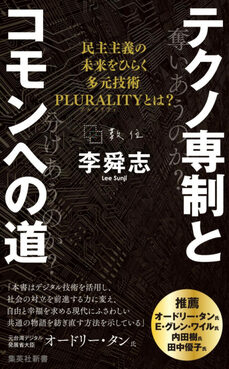「曖昧な存在」から見えてくる世界へ
李 今日お聞きしたかったことがあります。これは三牧先生の共著『自壊する欧米』のお相手の内藤正典先生がおっしゃっていたことで、日本は非欧米圏では比較的中立と思われている、という点についてです。「アメリカのアフガン侵攻で、日本は軍隊を送らず、アフガニスタン人も殺さなかったから、タリバンからは中立と思われている」という一節。このニュートラルな立場から、日本が現在の混迷するイスラエルとかガザやイランの情勢に対してできることって、何か先生、お考えはありますか。
三牧 ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻、そしてイスラエルのイランへの攻撃。いずれもまず国際法に照らして、国際道義に照らして、侵略した側、攻撃した側を批判することは大事です。ただ、実際に戦争をどう止めて犠牲を少しでも小さくするのか、という問題は、そうした善悪の判断とは、少し次元が異なる話になりますよね。
実は昨日、ロシア研究者の上田洋子さんと対談する機会があって、そこで上田さんがイスラエルのイラン攻撃と、何らイスラエル批判をせず、イランだけを一方的に批判したG7の共同声明について、「もしG8だったら……」とおっしゃったんです。以前はG8だったのが、ロシアがクリミア半島を併合したことを受けて、ロシアを除名してG7になったわけですよね。
しかし今のG7の中には、イランと話せるメンツがいない。イランを悪魔視して攻撃に賛成する、同質的な人たちばかり揃っている。だから今のような局面では、イランと話せるロシアのような存在がいた方がよかったのではないかと。
私にはそのような発想はなかったので、蒙を啓かれました。今もウクライナ侵略を続けるロシアを、侵略をやめてもいないのにG7に再び迎え入れることは道義にはかなっていないかもしれません。でもそのことによって開かれる対話があり、停戦や平和に一歩近づけるかもしれない。言われてみると、論理としてはよく理解できる。多様な存在のあるところに、多様な平和の可能性が開かれるわけですね。
石破首相は、イスラエルのイラン攻撃直後は、「到底許容できるものではない」とかなり強い言葉でイスラエルの攻撃を批判した。これは国際法上、正当化が難しい予防攻撃ですので、石破首相の認識は正しいものだと思います。
しかしだんだんその後批判のトーンが薄れていって、G7の共同声明では石破発言の影も形も無くなっていました。しかし、日本という非欧米の存在がいたことで、イスラエルとイランの問題に関しても、G7には潜在的には違う見解が存在していたわけですよね。やはり多様性は大事です。
G7は今まで、「法の支配」や人権、民主主義といった価値を共有していることを強みとし、そうした共同体であろうとしてきた。しかし、G7が様々な意味で限界を迎えている今、G20やBRICSといった、イデオロギー的な共通性よりも、むしろ雑多性を特徴とした、多様な意見や存在を包含した枠組みも活用していかないと、ウクライナ、ガザ、イラン、イスラエルと、違う力学の働く紛争を抱えた世界は、立ち行かない状況になっていくのではないでしょうか。
そういう意味では、G7の中で、日本はいい意味で不協和音をもたらせる存在であってほしいと思います。我々は歴史的にも地理的な条件も、欧米諸国とは様々に異なるわけです。そうした存在として、国連や、非欧米の大半の国々が「イスラエルの軍事行動は、法的にも、道義的にもあってはならない」とあげている声を、欧米に伝える役割は果たしてほしい。
李 そうですね、G7の一員であり、中国もロシアもいないG7の中で、やはり日本というのはヨーロッパでもないし、アメリカでもない、アジア。それでも民主主義を否定はしないし、権威主義国家でもない。そう考えると、日本は貴重なポジションというか、その独自性を今後は生かしていくべきで、生かす機会が増えていくということですね。
三牧 日本自体が曖昧な存在ゆえに、「あの国は非民主主義的だから断交しよう」みたいな、ある国を一方的に断罪し、関係を断つ、といった極端な発想が生まれにくいところはあるかもしれません。逆にアメリカは、自分たちの民主主義に誇りを持ちすぎたがゆえに、「あの国は非民主主義的だから今叩いておいた方がいい」とか、さらには「レジームチェンジ(体制転換)だ」とか、そういう発想にどうしても陥りやすく、軍事力行使のような極端な手段がとられてしまう。
日本の民主主義は、様々にまだ問題を抱えていて、改善に努めていかなければなりませんが、「日本は一応民主主義だけれど、あまり素晴らしい民主主義とは言えない」といった、自国への冷めた認識、不完全さの認識というのがあると、他国に対しても謙虚になれる。
ウクライナ戦争開始から約3年経ち、ガザでのイスラエルの軍事行動も1年半以上続いています。ロシアとイスラエルの軍事行動を何としても止めなければなりませんが、同時に国際社会は、こうした暴力性を抱え、国際法を軽視する国々を長期的にどう包摂していくかという課題にも応えていかなければならない。
非常に難しい問いですが、『PLURALITY』とその最良の解説書である李さんのご本は、こうした世界平和の根本課題についても、大変に示唆的な本であると確信しています。
構成/高山リョウ 撮影/内藤サトル