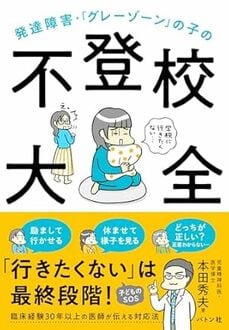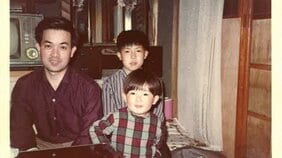不登校41万人は、氷山の一角に過ぎない
文部科学省の調査(2023年度)では、不登校の小・中学生が34万6482人いることがわかっています。同じ調査で高校生の不登校は6万8770人だと発表されました。いま日本では、小・中・高合わせて41万人以上の子どもたちが不登校になっているのです。
しかしその数字は、学校生活になじめない子が増えているという問題の、氷山の一角に過ぎないものだと考えられます。前ページの相談例のように、不登校の定義には当てはまらないけれど困っているという子もいます。
水面下には、学校になじめない「不登校予備群」のお子さんはその何倍もいると考えられます。
写真はイメージです 写真/Shutterstock
発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全
本田 秀夫

2025年6月21日発売
1,760円(税込)
256ページ
ISBN: 978-4866808574
夏休みだからこそ、新学期に向けて「不登校」への対応を考えるチャンスです。
いま一番人気の「不登校」本! 発売即重版‼
Amazon売れ筋ランキングでトリプル部門1位!
(「福祉の社会保障」「生徒指導」「障害者」2025.6.15~30)
●「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍
子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。 休ませて様子を見たほうがいいのか。 それとも、励まして登校させたほうがいいのか。 保護者の方からそのように聞かれることがあります。 学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。 この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。